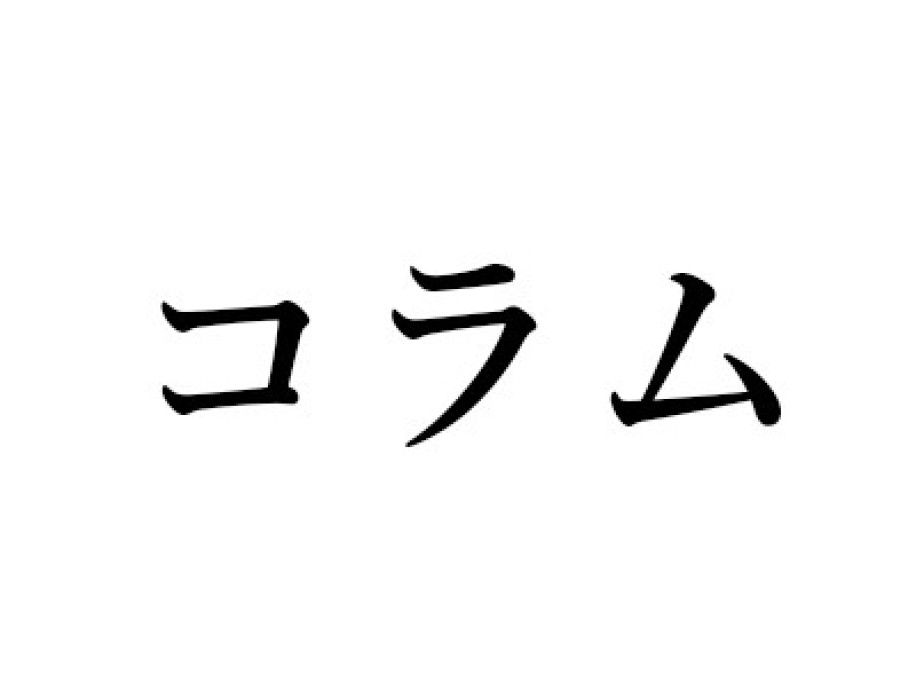書評
『「魂」に対する態度』(勁草書房)
哲学はやり切れない。難解な用語を振り回すから嫌いだ。――こんな偏見の持ち主は、本書を読むといいだろう。〈私〉が生きているとはどういうことか、他者とは何か……といった、誰にとっても基本的な疑問が、誰にもわかるように論じてある。厳密な、だが丁寧でやわらかな語り口だ。
本書の論文は《議論のための「叩き台」として使い捨てにされるべきもの》だと、著者は言う。しかし、論文集全体を読み通すと、ずしりと手ごたえが残る。結局のところただ一つのテーマをめぐる、一貫した思考の筋道が浮き彫りになる。
著者がその導きの糸とするのが、ニーチェとウィトゲンシュタインだ。
哲学は伝統的に《真なる言説と善なる言説は必然的に一致する》ことを自明の前提としてきた。が、真であっても道徳的でない「邪悪な真理」も存在しうる。それを指摘した《ニーチェこそが、哲学の正系》である。
ひとが道徳的にふるまうのはなぜか。その根拠は道徳的でありえない。ゆえに道徳は、根拠のない“力”に支えられている。ウィトゲンシュタインの言語ゲームの考え方に照らすと、そうなる必然が明らかになる。この両者を踏まえ、著者は他我問題を論じ進める。
永井氏によれば、いわゆる他人の心を知ることは困難でない。〈私〉だけに具わっているはずの〈魂〉をもった他者の存在こそ理解不可能な矛盾である。《他者とは……あまりにも遠い隣人》だ。《〈魂〉に対する態度とは、……それに向かって態度をとることができないものに対する、愛や共感や理解を超えた態度》にほかならない。
こうした洞察にもとづき、デリダやクリプキなどの所説を批判的に整理する手並みは鮮やか。また各部の末尾に、これまで寄せられた批判に応える「質疑応答」が付してあるのもよい工夫だ。細かく見れば異論もありえようが、本書の成功は疑えない。読後感もさわやかである。
【この書評が収録されている書籍】
本書の論文は《議論のための「叩き台」として使い捨てにされるべきもの》だと、著者は言う。しかし、論文集全体を読み通すと、ずしりと手ごたえが残る。結局のところただ一つのテーマをめぐる、一貫した思考の筋道が浮き彫りになる。
著者がその導きの糸とするのが、ニーチェとウィトゲンシュタインだ。
哲学は伝統的に《真なる言説と善なる言説は必然的に一致する》ことを自明の前提としてきた。が、真であっても道徳的でない「邪悪な真理」も存在しうる。それを指摘した《ニーチェこそが、哲学の正系》である。
ひとが道徳的にふるまうのはなぜか。その根拠は道徳的でありえない。ゆえに道徳は、根拠のない“力”に支えられている。ウィトゲンシュタインの言語ゲームの考え方に照らすと、そうなる必然が明らかになる。この両者を踏まえ、著者は他我問題を論じ進める。
永井氏によれば、いわゆる他人の心を知ることは困難でない。〈私〉だけに具わっているはずの〈魂〉をもった他者の存在こそ理解不可能な矛盾である。《他者とは……あまりにも遠い隣人》だ。《〈魂〉に対する態度とは、……それに向かって態度をとることができないものに対する、愛や共感や理解を超えた態度》にほかならない。
こうした洞察にもとづき、デリダやクリプキなどの所説を批判的に整理する手並みは鮮やか。また各部の末尾に、これまで寄せられた批判に応える「質疑応答」が付してあるのもよい工夫だ。細かく見れば異論もありえようが、本書の成功は疑えない。読後感もさわやかである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする