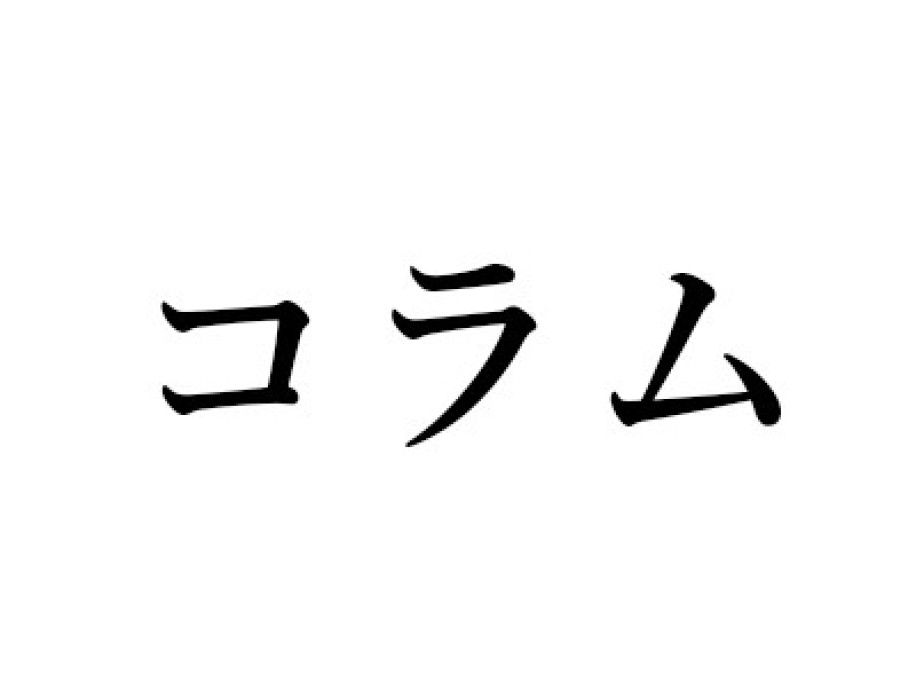書評
『服飾の中世』(勁草書房)
先日、さる日本人デザイナーがファッション・ショーに出品したパジャマが、強制収容所のユダヤ人の囚人服を連想させるとして非難された事件があったが(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)、この批判の要点が、パジャマの縞模様というよりもむしろ黒と黄色の配色に置かれていたことについて、敏感に反応した日本人はあまり多くなかったにちがいない。かくいう私もその一人だった。
ところが、フランス中世と十九世紀の服飾のシンボル作用を扱った本書を読んで、この配色の意味するところがたちどころに理解できた。黄色というのは、中世においては、裏切りや狂気、嫉妬などを象徴する忌まわしい色とされ、政治的な裏切り者、ユダヤ人、娼婦、狂人、道化などの、社会のマージナルな人々に着用させるべき色とされていたのである。たとえば十三世紀のマルセイユ都市法はユダヤ人に黄色の帽子をかぶせることを義務づけたし、フランソワ一世に対する反逆を企てたブルボン大元帥の家の壁は黄色く塗られていた。
こうした「黄色」の象徴的な意味は、中世リヴァイヴァルの著しかった十九世紀のロマン主義時代にも引き継がれた。著者は、バルザックが『従妹ベット』の中で嫉妬深いベットに黄色のカシミア・ショールを着せている部分を取りあげ、中世の色彩の象徴作用に詳しかったバルザックは黄色に対する歴史的な色彩感情をそこに表現していたのだろうと推測する。
この例からもわかるように、本書の関心は一般の服飾史のように衣服形態の変遷を概観することではなく、文学作品や絵画の中にあらわれた衣服の形態や色彩の時代的な表象作用を読み取ることにある。
なかでも、『トリスタン物語』のなかで、トリスタンの死を知ったイズーが船から降りて「留め金をはずしたままで道を急いだ」とある箇所に注目して、中世の生活においてマントのもっていた意味をあきらかにする部分は読みごたえがある。
著者によれば、この部分はたんに「留め金がはずれている」という意味ではなく、あくまで「マントをまとわずに」という意味に解釈すべきであるという。
こうした解釈は、中世に着用されていたマントの実際の形態をよほど詳しく知っていなければ導きだせないものであり、これだけでも専門的知識を極めた人は恐ろしいと思うのだが、著者はそんなことでは満足せず、さらに、中世においてマントがどのような習慣の下に着用されていたかまで考察にいれ、『トリスタン物語』のマントの意味を探っていく。すなわち、中世において、マントは防寒のための外出着ではなく、むしろ室内着であり、貴族階級の男女にとってマントを羽織らないでいるのはよほどの例外的状況にあることだとして、次のようにいう。
アナール派の登場以来、文学や美術を風俗の観点から見直そうとする動きが盛んだが、ここには、そうした研究方法に拠る場合にもっとも必要なスタンスがあるように思われる。
というのも、文学や美術にあらわれた風俗というのは、単に、風俗一般を示すためではなく、あくまで作品の意味を強化するために、選ばれてそこにあるわけだから、いったん風俗を通して歴史に抜けたあと、もう一度歴史から得た知識を携えて作品に立ち戻り、そこでこの風俗が作品内で特権的に示している意味作用を解釈しなければ、あえて文学や美術を題材にすることの意味はないからだ。文学や美術のなかの風俗を扱うと称する研究は、えてしてこうした「立ち戻り」をせずに、文学や美術の研究にも、また風俗研究にも何の益も与えぬまま終わることが多いが、本書は、そうした弊を免れた数少ない例である。
いささか詰め込みすぎて胃にもたれるきらいはあるが、最近では出色の服飾史研究といっていい。
【この書評が収録されている書籍】
ところが、フランス中世と十九世紀の服飾のシンボル作用を扱った本書を読んで、この配色の意味するところがたちどころに理解できた。黄色というのは、中世においては、裏切りや狂気、嫉妬などを象徴する忌まわしい色とされ、政治的な裏切り者、ユダヤ人、娼婦、狂人、道化などの、社会のマージナルな人々に着用させるべき色とされていたのである。たとえば十三世紀のマルセイユ都市法はユダヤ人に黄色の帽子をかぶせることを義務づけたし、フランソワ一世に対する反逆を企てたブルボン大元帥の家の壁は黄色く塗られていた。
こうした「黄色」の象徴的な意味は、中世リヴァイヴァルの著しかった十九世紀のロマン主義時代にも引き継がれた。著者は、バルザックが『従妹ベット』の中で嫉妬深いベットに黄色のカシミア・ショールを着せている部分を取りあげ、中世の色彩の象徴作用に詳しかったバルザックは黄色に対する歴史的な色彩感情をそこに表現していたのだろうと推測する。
この例からもわかるように、本書の関心は一般の服飾史のように衣服形態の変遷を概観することではなく、文学作品や絵画の中にあらわれた衣服の形態や色彩の時代的な表象作用を読み取ることにある。
なかでも、『トリスタン物語』のなかで、トリスタンの死を知ったイズーが船から降りて「留め金をはずしたままで道を急いだ」とある箇所に注目して、中世の生活においてマントのもっていた意味をあきらかにする部分は読みごたえがある。
著者によれば、この部分はたんに「留め金がはずれている」という意味ではなく、あくまで「マントをまとわずに」という意味に解釈すべきであるという。
マントが問題であることは認めるとしても、原義に即して留め金がはずれているだけとする解釈もある。しかしこれはマントの性質からいって考えにくい。右に述べたようにマントは、ウールに毛皮を張るためにかなりの重量をもち、しかも円や半円の形のない衣服であるから、留め金をはずしたまま肩で支えるというのはかなり難しいと思うからである。イズーのように動転している人ならなおのことである。
こうした解釈は、中世に着用されていたマントの実際の形態をよほど詳しく知っていなければ導きだせないものであり、これだけでも専門的知識を極めた人は恐ろしいと思うのだが、著者はそんなことでは満足せず、さらに、中世においてマントがどのような習慣の下に着用されていたかまで考察にいれ、『トリスタン物語』のマントの意味を探っていく。すなわち、中世において、マントは防寒のための外出着ではなく、むしろ室内着であり、貴族階級の男女にとってマントを羽織らないでいるのはよほどの例外的状況にあることだとして、次のようにいう。
マントは貴族の平和な日常生活に欠かせぬ衣服であり、特別の事情がないかぎり脱ぐことのない衣服であり、毛皮という素材のために財産価値をもつ衣服である。王妃イズーがそのようなマントを着ていないのは、やはり彼女の心に与えた深刻な打撃を語るためである。
アナール派の登場以来、文学や美術を風俗の観点から見直そうとする動きが盛んだが、ここには、そうした研究方法に拠る場合にもっとも必要なスタンスがあるように思われる。
というのも、文学や美術にあらわれた風俗というのは、単に、風俗一般を示すためではなく、あくまで作品の意味を強化するために、選ばれてそこにあるわけだから、いったん風俗を通して歴史に抜けたあと、もう一度歴史から得た知識を携えて作品に立ち戻り、そこでこの風俗が作品内で特権的に示している意味作用を解釈しなければ、あえて文学や美術を題材にすることの意味はないからだ。文学や美術のなかの風俗を扱うと称する研究は、えてしてこうした「立ち戻り」をせずに、文学や美術の研究にも、また風俗研究にも何の益も与えぬまま終わることが多いが、本書は、そうした弊を免れた数少ない例である。
いささか詰め込みすぎて胃にもたれるきらいはあるが、最近では出色の服飾史研究といっていい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする