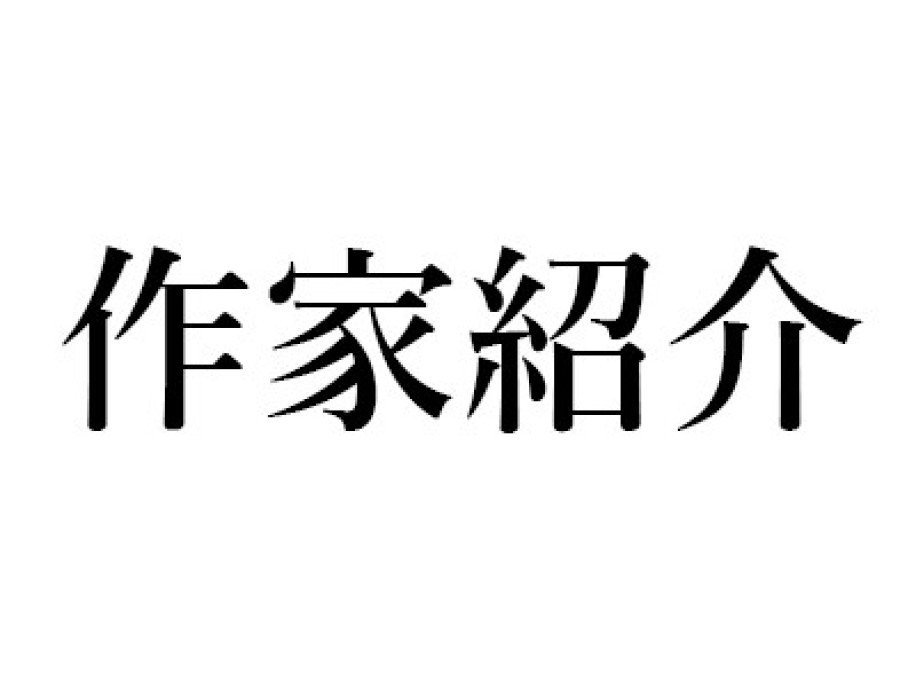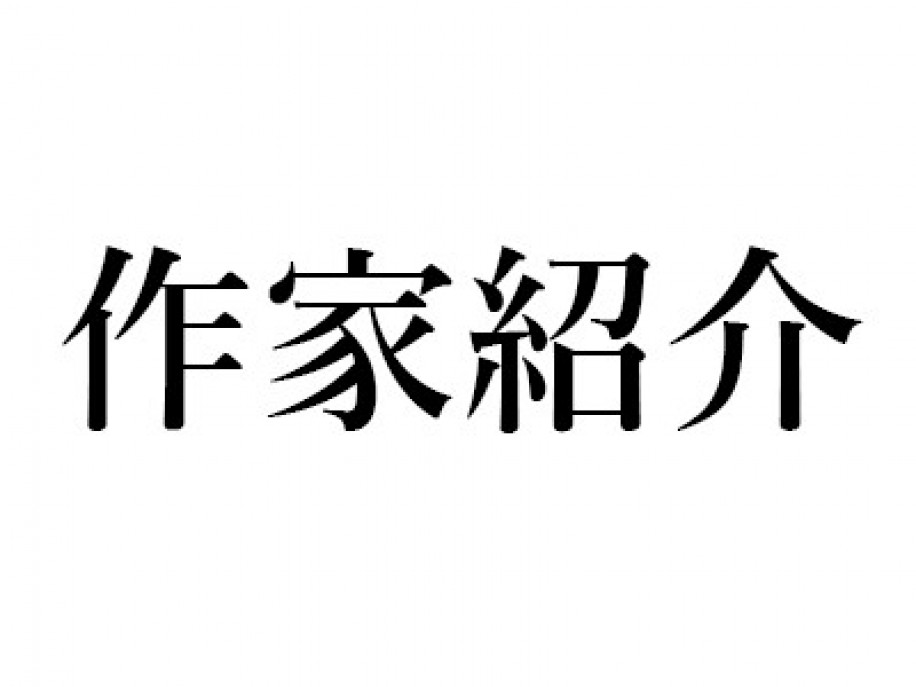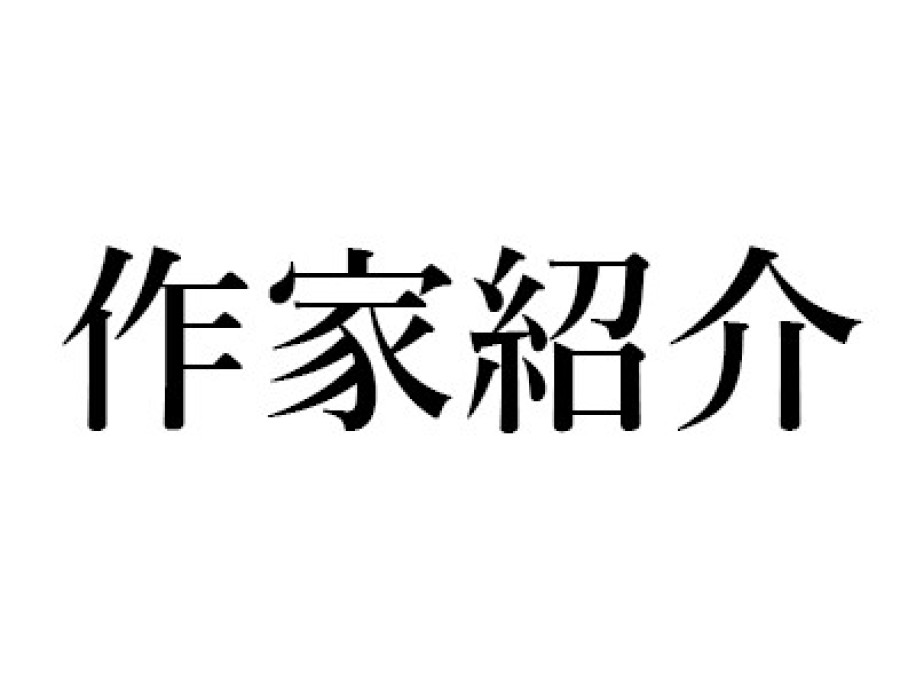書評
『狼たちの月』(ヴィレッジブックス)
トヨザキ的評価軸:
◎「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
というわけで、良い子の皆さんにはフリオ・リャマサーレスの『狼たちの月』を読んでいただきたいんですの。語り手は内戦が起きるまでは小学校の教師をしていた〈ぼく〉。フランコ率いる反乱軍と対立する共和派の民兵となり戦火に身を投じた〈ぼく〉は、しかし、その一年後には幼なじみでリーダー格のラミーロとその弟ヒルド、妻子持ちの中年男フアンと共に山中を敗走しています。反乱軍が送り込む治安警備員の捜索と粛清は容赦ありません。わなに追い込まれ生け捕りにされ、あちこちの村を引き回された末に惨殺される狼の姿に我が身を重ね合わせる〈ぼく〉は――。
食べるものや着るものに事欠きながら、敵と戦うためではなく生きながらえるために山中に潜む四人の姿を描く「第一部 一九三七年」には、ヘミングウェイの小説に描かれるマッチョなヒロイズムなど一片も見当たりません。自由を守るために戦っていたはずなのにただ追われる身に落ち、生きるために強盗までして、やがて仲間を失い、亡命する資金を得るべく誘拐事件を起こしてしまう。その姿のどこにもヒーローの面影はありません。〈ぼく〉は恋人と小さな幸せを育んでいた頃の無邪気さを失い、幼なじみのラミーロもまた〈寡黙でおどおどした少年の面影は残っておらず、とても同じ人間とは思えない。今、ぼくの目の前にいるのは、遠くかけ離れた近づきがたい男〉と化してしまうんです。ヒーローを生むどころか、すべての人からかつての面影を奪ってしまう戦争のリアルを描いて、これは胸が苦しくなる物語なのです。
「第四部 一九四六年」まで時系列に沿って描かれる「ぼく」の潜伏とサバイバルの日々を、作者のリャマサーレスは静かで端正な、もの悲しい文体で淡々と描いていきます。その”声”が、同胞同士が血を流しあい、故郷がフランコ側に提供されたドイツの新型兵器によって焦土と化す無念と、三年に及ぶ戦いで死んでいった人々への切々たる弔意を謳っているのです。
〈ぼく〉の父親が息子に教えるこの言葉が象徴するように、『狼たちの月』は名もなき死者たちへの痛ましくも美しいレクイエムになっているのです。
【この書評が収録されている書籍】
◎「金の斧(親を質に入れても買って読め)」
「銀の斧(図書館で借りられたら読めば―)」
「鉄の斧(ブックオフで100円で売っていても読むべからず)」
名もなき死者たちへの痛ましくも美しいレクイエム
ある仕事のために、ヘミングウェイの『誰がために鐘は鳴る』(新潮文庫)を読んでびっくらこいちゃった。一九三六年に起きたスペイン内戦を扱った小説なんですが、自らも国際義勇兵として参戦したヘミングウェイときたら、内戦という大事を単なるメロドラマのレベルにまで引きずり下ろしてんですの。サイテー。というわけで、良い子の皆さんにはフリオ・リャマサーレスの『狼たちの月』を読んでいただきたいんですの。語り手は内戦が起きるまでは小学校の教師をしていた〈ぼく〉。フランコ率いる反乱軍と対立する共和派の民兵となり戦火に身を投じた〈ぼく〉は、しかし、その一年後には幼なじみでリーダー格のラミーロとその弟ヒルド、妻子持ちの中年男フアンと共に山中を敗走しています。反乱軍が送り込む治安警備員の捜索と粛清は容赦ありません。わなに追い込まれ生け捕りにされ、あちこちの村を引き回された末に惨殺される狼の姿に我が身を重ね合わせる〈ぼく〉は――。
食べるものや着るものに事欠きながら、敵と戦うためではなく生きながらえるために山中に潜む四人の姿を描く「第一部 一九三七年」には、ヘミングウェイの小説に描かれるマッチョなヒロイズムなど一片も見当たりません。自由を守るために戦っていたはずなのにただ追われる身に落ち、生きるために強盗までして、やがて仲間を失い、亡命する資金を得るべく誘拐事件を起こしてしまう。その姿のどこにもヒーローの面影はありません。〈ぼく〉は恋人と小さな幸せを育んでいた頃の無邪気さを失い、幼なじみのラミーロもまた〈寡黙でおどおどした少年の面影は残っておらず、とても同じ人間とは思えない。今、ぼくの目の前にいるのは、遠くかけ離れた近づきがたい男〉と化してしまうんです。ヒーローを生むどころか、すべての人からかつての面影を奪ってしまう戦争のリアルを描いて、これは胸が苦しくなる物語なのです。
「第四部 一九四六年」まで時系列に沿って描かれる「ぼく」の潜伏とサバイバルの日々を、作者のリャマサーレスは静かで端正な、もの悲しい文体で淡々と描いていきます。その”声”が、同胞同士が血を流しあい、故郷がフランコ側に提供されたドイツの新型兵器によって焦土と化す無念と、三年に及ぶ戦いで死んでいった人々への切々たる弔意を謳っているのです。
ほら、月が出ているだろう。あれは死者たちの太陽なんだよ。
〈ぼく〉の父親が息子に教えるこの言葉が象徴するように、『狼たちの月』は名もなき死者たちへの痛ましくも美しいレクイエムになっているのです。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする