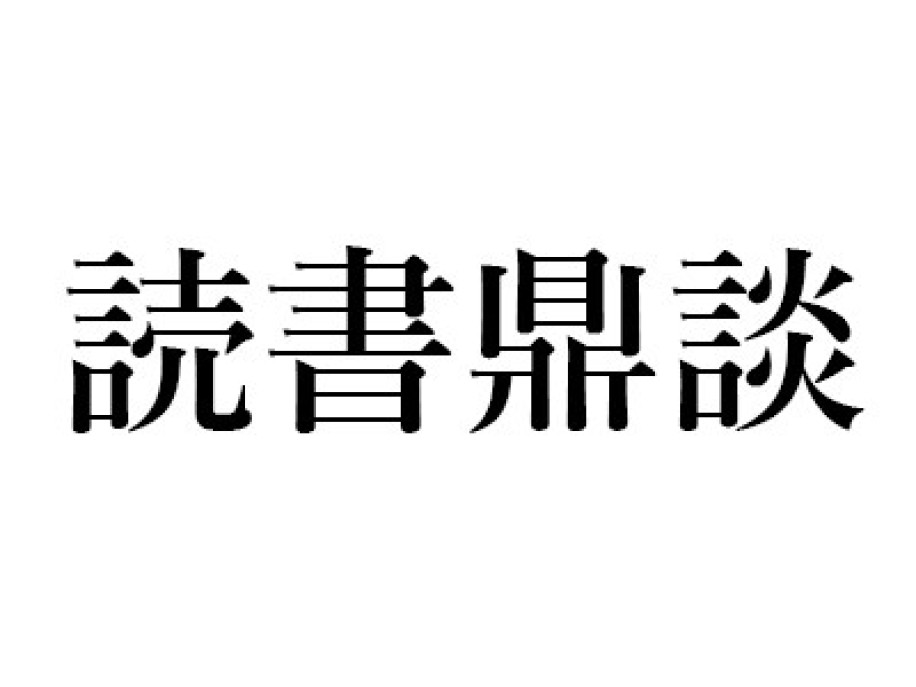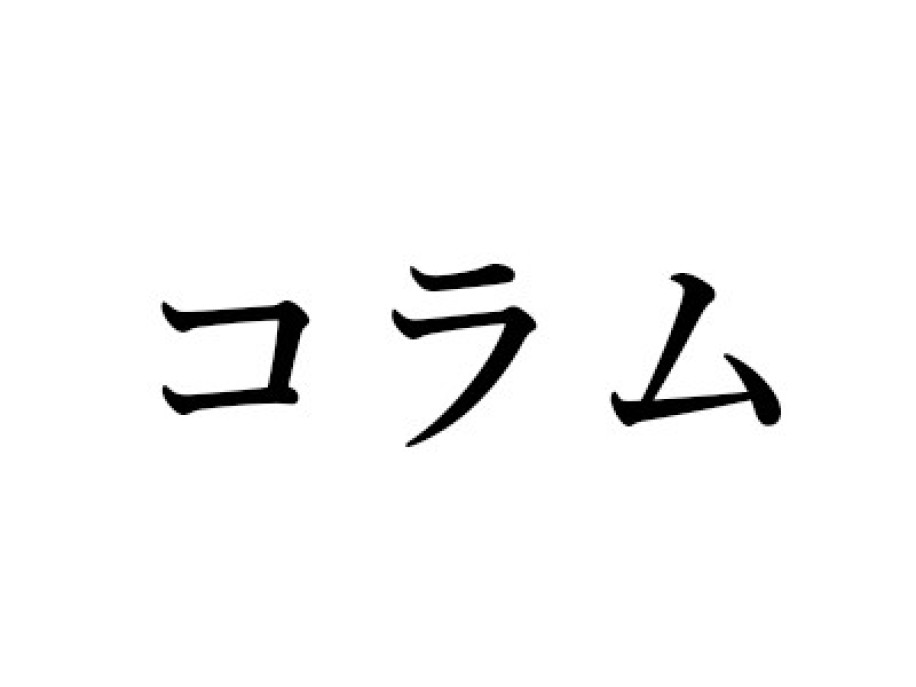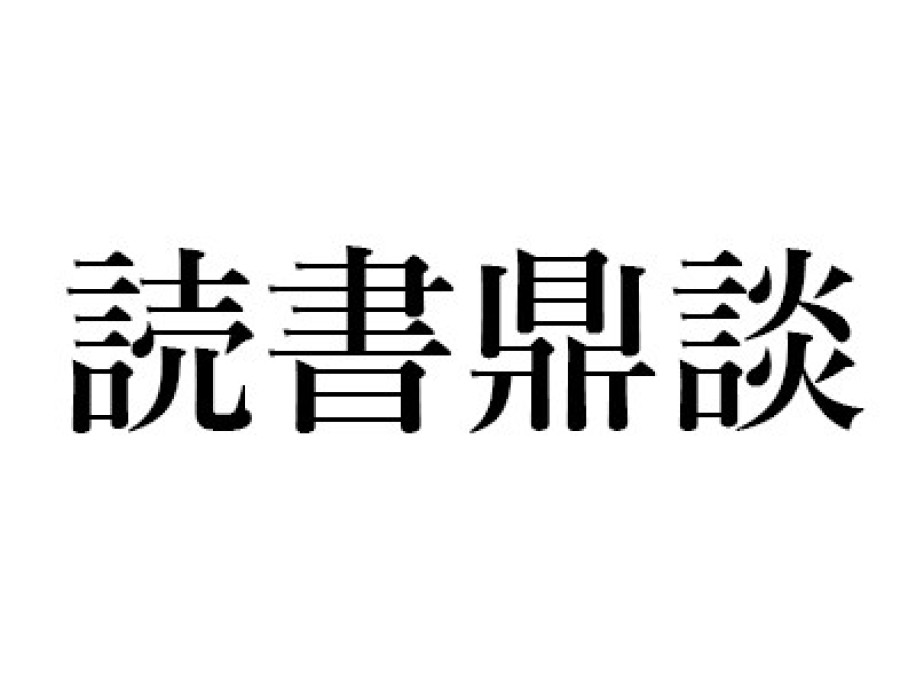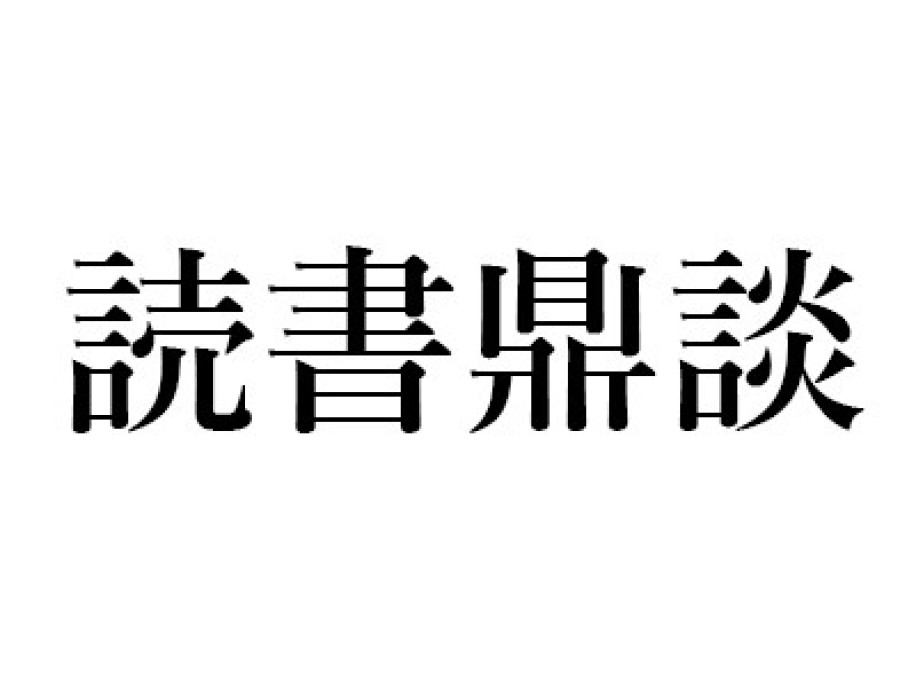書評
『かく咲きたらば』(朝日新聞)
ここ数年、「花」がブームだそうである。確かに、花を贈ったり、飾ったりすることが多くなった。花博も盛況だったし、数ある創刊雑誌が苦戦と言われるなかで「花時間」は大健闘、数ヵ月前の「anan」では「超ブーム!花のすべてを完全取材!花がなくては、もう暮らせない。」という特集をしていた(思わず私も買ってしまった)。(事務局注:本書評の初出は1992年頃)
が、本書を読むと「なーんだ、今に始まったことじゃないのね。昔から日本人ていうのは、花が好きで好きでたまらなかったんだ」という思いが湧いてくる。
梅、桃、桜。百合に朝顔、女郎花(おみなえし)。すみれ、卯の花、忘れ草……。
昨今流行の洋花とはひとあじ違う、地味だけれど懐かしい花たちの登場する和歌が、四百首あまり、紹介されている。
その舞台は、『古事記』『万葉集』から『古今集』『伊勢物語』『源氏物語』、さらには『平家物語』から芭蕉までエトセトラ……自在に広げられている。
おもしろいのは、同じ花でも時代によって、見られかたや担うイメージが、変化しているということだ。それが和歌をとおして、くっきりと伝わってくる。
たとえば、萩の花。
この歌をはじめ『万葉集』に登場する数多くの萩の花は、野趣に富んだものが多い。またあるときは、妻を呼ぶ鹿の声と取り合わされ、情緒的な秋を演出した。
ところが、中世になると、萩はとても寂しい表情をした花となる。
「鎌倉初頭と南北朝内乱期の入口の時代に詠まれた庭の萩のすがたには、もうすでに、あの広々とした万葉の野の気配は全くなく、ひたすら心象を受け止めて佇む孤影の萩のさびしさが生まれている。」という著者の指摘は、まことに興味深い。
「思ひ草」(なんばんぎせる)や「忘れ草」(萱草)のように、実体を離れて、言葉の持つロマンチックな響きが愛された花もある。これらは、恋の歌のなかで、繰り返し繰り返し咲いてきた。
花と文学、花と暮らし、あるいは花と日本人、ということを、楽しみながら考えさせてくれる本である。
【この書評が収録されている書籍】
が、本書を読むと「なーんだ、今に始まったことじゃないのね。昔から日本人ていうのは、花が好きで好きでたまらなかったんだ」という思いが湧いてくる。
梅、桃、桜。百合に朝顔、女郎花(おみなえし)。すみれ、卯の花、忘れ草……。
昨今流行の洋花とはひとあじ違う、地味だけれど懐かしい花たちの登場する和歌が、四百首あまり、紹介されている。
その舞台は、『古事記』『万葉集』から『古今集』『伊勢物語』『源氏物語』、さらには『平家物語』から芭蕉までエトセトラ……自在に広げられている。
おもしろいのは、同じ花でも時代によって、見られかたや担うイメージが、変化しているということだ。それが和歌をとおして、くっきりと伝わってくる。
たとえば、萩の花。
秋風は涼しくなりぬ馬並(な)めていざ野にゆかな萩の花見に 作者未詳
この歌をはじめ『万葉集』に登場する数多くの萩の花は、野趣に富んだものが多い。またあるときは、妻を呼ぶ鹿の声と取り合わされ、情緒的な秋を演出した。
ところが、中世になると、萩はとても寂しい表情をした花となる。
真萩散る庭の秋風身にしみて夕日の影ぞ壁に消えゆく 永福門院
「鎌倉初頭と南北朝内乱期の入口の時代に詠まれた庭の萩のすがたには、もうすでに、あの広々とした万葉の野の気配は全くなく、ひたすら心象を受け止めて佇む孤影の萩のさびしさが生まれている。」という著者の指摘は、まことに興味深い。
「思ひ草」(なんばんぎせる)や「忘れ草」(萱草)のように、実体を離れて、言葉の持つロマンチックな響きが愛された花もある。これらは、恋の歌のなかで、繰り返し繰り返し咲いてきた。
花と文学、花と暮らし、あるいは花と日本人、ということを、楽しみながら考えさせてくれる本である。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする