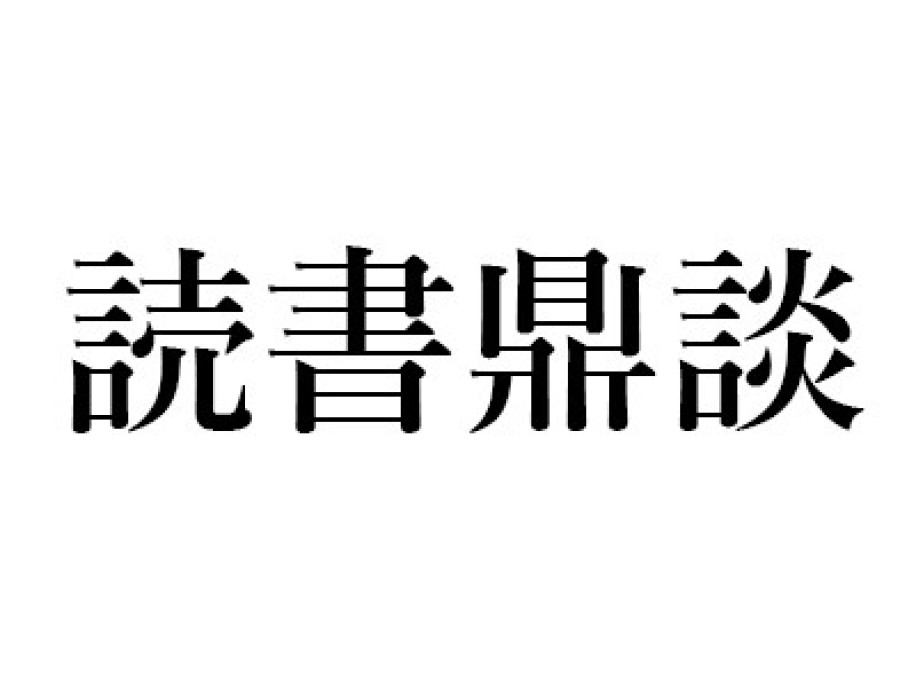書評
『私自身のための俳句入門』(新潮社)
「俳句入門」の言葉にだまされてはいけない。てっとり早く俳句の作りかたを知りたい、と思っているような人には、この本はおすすめできない。
「私自身のための」である。その「私」とは、詩・短歌・俳句のすべてを、すでに自在にあやつる著者、高橋睦郎なのだ。
お手軽な入門書なら、まずこう書いてあるだろう。「俳句とは五七五の定型から成り、季語を含むことを約束とするものです」。もう少し丁寧な入門書なら、こう付け加えるかもしれない。「それは、俳諧連歌の発句が独立して生まれました」と。
なぜ、五七五なのか。季語とは何なのか。俳諧連歌はなぜ生まれたのか。そしてどうしてその発句が独立したのか。本書は、俳句の生まれでた背景と歴史とその必然を、執拗に追求している。
のっけから「俳句は和歌である」と著者は言い放つ。この言葉に象徴されるように、詩・短歌・俳句というセコイ垣根のない発想が、本書の魅力だ。というよりも、これらがいかに一つであり密接につながっているものであるかを、教えられる。
そういった自由な発想から、たとえば「俳句だけの共通財産とされる季語や切れ字も、歌の共通遺産としての本歌取りのきわめて俳句的に特殊化したかたちととることも可能ではあるまいか。」という新鮮な見方がもたらされる。
なかでもおもしろかったのは、「や」をはじめとする切れ字の働きについての見解だ。
五・七・五音律という有限の空間に切れ目を入れることで、その有限を無限にしようとするのが切れ字ではないか、と著者は言う。
「日当りの梅咲くころや屑牛房(ごぼう)」が「日当りの梅咲くころを屑牛房」だったらどうだろうか。前者の完結感に対して、後者は後続を予想させる感じ。つまり前者は、五七五のなかに切れ目を持つことで、そこに無限の宇宙を見出し、後者は続きを待つ姿勢で、いまだ発句の域を出ていない。
「神と人との相聞から季節感が生まれた」というところから出発する季への思いも、この著者独特のもの。俳句を俳句として生き残らせる道は、中心を季に置き、季の本質をさぐりつづけることにしかない、という意外なほど保守的な結論は、これまた意外なほど斬新な道筋を通って導かれる。ぜひあなたも、説得されてください。
【この書評が収録されている書籍】
「私自身のための」である。その「私」とは、詩・短歌・俳句のすべてを、すでに自在にあやつる著者、高橋睦郎なのだ。
お手軽な入門書なら、まずこう書いてあるだろう。「俳句とは五七五の定型から成り、季語を含むことを約束とするものです」。もう少し丁寧な入門書なら、こう付け加えるかもしれない。「それは、俳諧連歌の発句が独立して生まれました」と。
なぜ、五七五なのか。季語とは何なのか。俳諧連歌はなぜ生まれたのか。そしてどうしてその発句が独立したのか。本書は、俳句の生まれでた背景と歴史とその必然を、執拗に追求している。
のっけから「俳句は和歌である」と著者は言い放つ。この言葉に象徴されるように、詩・短歌・俳句というセコイ垣根のない発想が、本書の魅力だ。というよりも、これらがいかに一つであり密接につながっているものであるかを、教えられる。
そういった自由な発想から、たとえば「俳句だけの共通財産とされる季語や切れ字も、歌の共通遺産としての本歌取りのきわめて俳句的に特殊化したかたちととることも可能ではあるまいか。」という新鮮な見方がもたらされる。
なかでもおもしろかったのは、「や」をはじめとする切れ字の働きについての見解だ。
五・七・五音律という有限の空間に切れ目を入れることで、その有限を無限にしようとするのが切れ字ではないか、と著者は言う。
「日当りの梅咲くころや屑牛房(ごぼう)」が「日当りの梅咲くころを屑牛房」だったらどうだろうか。前者の完結感に対して、後者は後続を予想させる感じ。つまり前者は、五七五のなかに切れ目を持つことで、そこに無限の宇宙を見出し、後者は続きを待つ姿勢で、いまだ発句の域を出ていない。
「神と人との相聞から季節感が生まれた」というところから出発する季への思いも、この著者独特のもの。俳句を俳句として生き残らせる道は、中心を季に置き、季の本質をさぐりつづけることにしかない、という意外なほど保守的な結論は、これまた意外なほど斬新な道筋を通って導かれる。ぜひあなたも、説得されてください。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする