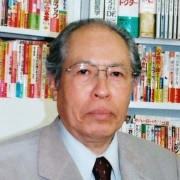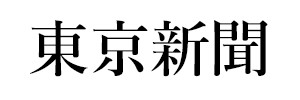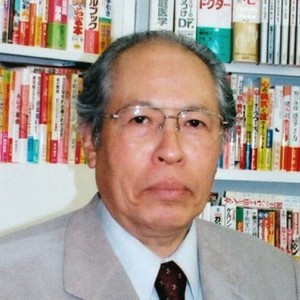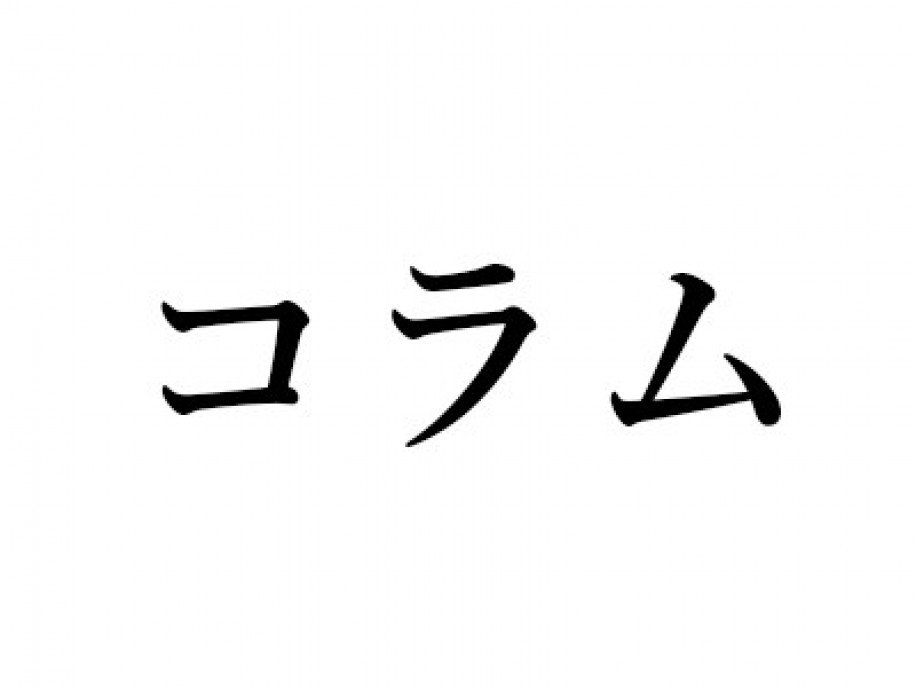書評
『ガリ版ものがたり』(大修館書店)
創作・政治と結びつく歴史
ガリ版は既に若い世代には馴染みが薄いものだろうが、中年以上の日本人にとっては、懐かしくも重要な思い出の一部である。それは教育や企業活動をはじめ、演劇や放送の台本、文学青年の同人誌活動などに至るまで、多方面から近代日本の文化を支えた印刷技術だった。本書はそんなガリ版の歴史を研究すること三十年、ガリ版に魅せられた著者の熱い研究成果である。日本におけるガリ版第一号機は、滋賀県出身の堀井新治郎父子により、明治二十七年(一八九四)に開発された謄写版である。参考にしたのはエジソンのミメオグラフというシステムだが、これは原稿づくりにタイプライターを用いたもので、日本人としては漢字を表現できるよう、美濃紙にロウ引きを施した原紙や、製版のための鉄筆とやすりの同時開発が不可欠であった。エジソンとは別物である。
堀井父子は会社を設立、官庁や学校などを中心に販売促進活動を行った結果、明治後期から大正時代にかけて全国津々浦々に普及した。しかしこの新時代の事務機が宮沢賢治のような個人の創作活動や草の根の政治運動と結びついていくとは、当初だれも予想しないことであった。本書はその中でも謄写版を「孔版芸術」にまで高めた草間京平や、豆本作家としての武井武雄らに焦点を合わせているが、第一次大戦におけるドイツ人捕虜たちが、徳島収容所で発行した「ディ・バラッケ」というガリ版刷りの新聞には、その情報量や高度の内容において、いまなお深い感動を与えられるものがある。
日本のガリ版史は、近代精神の発達と深く結び付いていて、その魅力は手作業の創意工夫によって、個性や作品性を発揮し得ることであった。これこそがガリ版の今日的意義であり、昨今のワープロやパソコンがこれほどの文化的な厚みを獲得するのはいつのことか、考え込んでしまうのは評者だけではあるまい。
ALL REVIEWSをフォローする