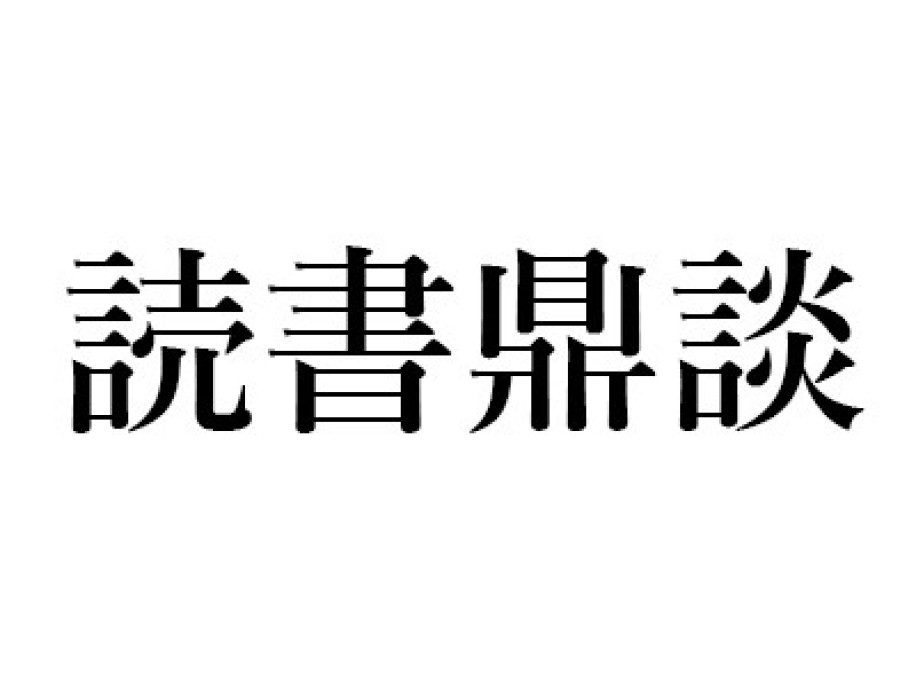書評
『建築から都市を、都市から建築を考える』(岩波書店)
建築は、人間を置き去りにしてはいけない
今年7月17日、新国立競技場の建設計画の「白紙撤回」が表明された(事務局注:本書評執筆時期は2015年)。市民や識者、建築家による反対運動の成果として拍手したが、いっぽう、どこか腑(ふ)に落ちない思いを抱いたのも事実である。衆院本会議での安保法案可決は同月16日、その翌日、唐突に発表された「白紙撤回」に安保法案可決とのあざとい天秤(てんびん)を感じたのは、もちろん私だけではないだろう。そもそも議論を尽くした上での決定ではなかった。根深い不信感は、その後、デザインビルド方式の入札の進展が不可視であることを考えれば、よけいに拭いづらい。本書は、新国立競技場の建設計画の危険性と倫理性についていち早く指摘、反対運動の主軸となってきた建築家、槇文彦の語りで構成されている。聞き手は近代建築史家、松隈洋。絶好の聞き手を得て、前半は半世紀以上におよぶ建築家の軌跡、後半は日本の建築と都市が孕(はら)む問題点と展望、一冊をつうじて問いかけるのは、空間という価値の大きさだ。
すでに広く知られるように、槇文彦が手がけた建築物は、代官山ヒルサイドテラスや京都国立近代美術館をはじめ、都市空間と建築物が地続きとなり、ごく自然に市民の日常生活に関わる設計がなされている。つまり、都市に普遍的な尊厳が与えられ、生活者ひとりひとりの存在が尊ばれているということ。終始一貫して商業主義的な建築に偏ることのない槇文彦の建築物に身を置くとき、わたしが今日まで感じ続けてきたことは、建築物によって公正性と根源的な自由が守られているということだ。だから、足が向く。
その人生は、近代建築史の歩みそのものである。弟子として学んだ丹下健三。アメリカではバウハウスの設立者グロピウスに学び、ル・コルビュジエの個性に触れ、都市デザインにおける人間性を尊重したセルトのアトリエで働く。帰国後は、成長する生物として都市をとらえる黒川紀章らのメタボリズムの勢いを目の当たりにし、前川國男、谷口吉郎らの世代からモダニズムを引き継ぐ。その思考と洞察は、建築家たちが近代の歴史と格闘しつつ獲得した収斂(しゆうれん)のかたちともいえるだろう。
ニーチェの言葉「孤独は私の故郷である」を座右におく。その公共建築の基本理念は、つまり、個的な深い精神性と分かちがたく結びついていると知り、腑に落ちた。都市空間とは、人間が孤独を楽しめる場所でありたいという認識に、現代を生きる同時代人としての眼差(まなざ)しがある。建築が安易に消費されず、普遍的な社会性を獲得するためには、だからこそ「人間をどう考えたか」という思考運動が読み取れなくては、という指摘がひたすら重い。
美しさより「歓び」を感じられる建築でありたい。この、1928年生まれの建築家の語りに心おどる思いだ。かつて江戸時代、人々が集い、老若男女の幸福な笑みがこぼれた「名所」のような空間が神宮外苑に出現したら、どんなにうれしいだろう。
ALL REVIEWSをフォローする