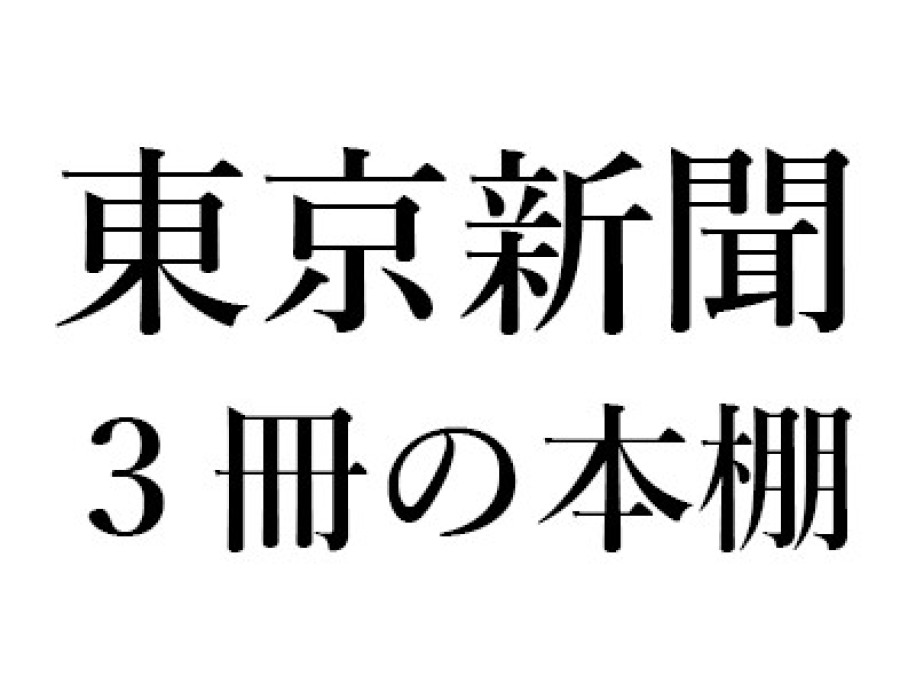書評
『コルセットの文化史』(青弓社)
変身願望のたまもの、紀元前から
『風と共に去りぬ』をご覧になった方は、スカーレットに扮したヴィヴィアン・リーが乳母にコルセットを締めてもらっている場面を記憶されているにちがいない。ヴィヴィアン・リーは気絶しそうになりながら、きつい紐締め(タイト・レイシング)に耐えていたが、われわれは、なぜあんなに体に悪いことをするのだろうと不思議に思ったものだ。本書はまず、衣服が発明されたのは防寒などの実用目的ではなく、「かくあらまほしい」と願う女性の変身願望のたまものであるという説を紹介したあと、コルセットこそはこうした「身体を思うままに変容させる、その造形用具」であったとする。変身願望が生まれた紀元前一五〇〇年のクレタ文明から、コルセットは存在していたのだ。
もっとも、女性の美の基準は時代によって変わる。ゆえにギリシャ・ローマなどのようにコルセットがない文明も存在した。現に「ミロのヴィーナス」の胴は太い。
コルセットの再登場には中世末期をまたなければならない。この時代からヨーロッパの宮廷では胸と尻を大きく強調するシルエットが流行するようになったため、胴を締める本格的なコルセットが発明されたのだ。その構造は最初、騎士の甲冑をヒントにした鉄製のものが多かったが、やがて鬚(ひげ)鯨の鬚(正確には幼魚や軟体動物などを口の中で擦り潰すためのヤスリのような骨質の薄板)、俗にいう鯨骨(ホエール・ボーン)を張り骨に使ったものに変化する。一七世紀頃から欧米の捕鯨業が繁栄したのはこの鯨鬚を採取するためだったといわれるほどだ。
鯨骨を多量に使ったコルセットは一人では紐締めするのは不可能なので、召使いなどの手助けを必要とした。風刺画などには男も加わった召使いたちが三人かかりで紐締めしている光景が描かれているが、それをみると、紐締め作業は「締める側にとっても重労働だったことがよく伝わってくる」。コルセットはフランス革命で一時追放されたが、王政復古とともに復活し、十九世紀を通じて、女性の胴を締め上げつづける。
ウエストが細ければ細いだけ美人とされたので、寄宿舎でも女生徒に十二、三歳頃から、コルセットの着用が推奨され、「ウエストを細くすることも教育内容の一環と位置づけられていた」らしい。
では、実際に女性たちがどれくらい胴を締めつけていたのかというと、十九世紀末に理想とされたのは十七インチ(約四十三センチ)。オーストリア皇妃エリザベートは若き日には十六インチ(約四十センチ)を誇り、フランスの女優ポレールはなんと三十五・五センチだった。
これほど強く締めつければ、当然、健康への影響が懸念される。医師たちは、コルセットは女性の健康をそこなうとして、反コルセット運動を起こしたが、意外なことに、今日の科学的見地からするとこれらの医師の弾劾は根拠がないらしい。現代の女性に十九世紀のコルセットを着用させて実験を試みたところ、肺機能の低下や腹筋・背筋の衰えは観察されるものの「十九世紀の医学雑誌が脅しているような死に至る病との直接的な因果関係は証明できなかった」という。
現代の女性はコルセットからは解放されたが、代わってダイエットやエクササイズなどによる「内なるコルセット」があらわれてきている。女性の変身願望は不変のようである。
コルセットの入手方法から一人で装着する法まで書かれたコルセット百科である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする