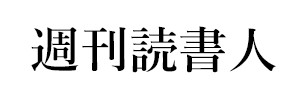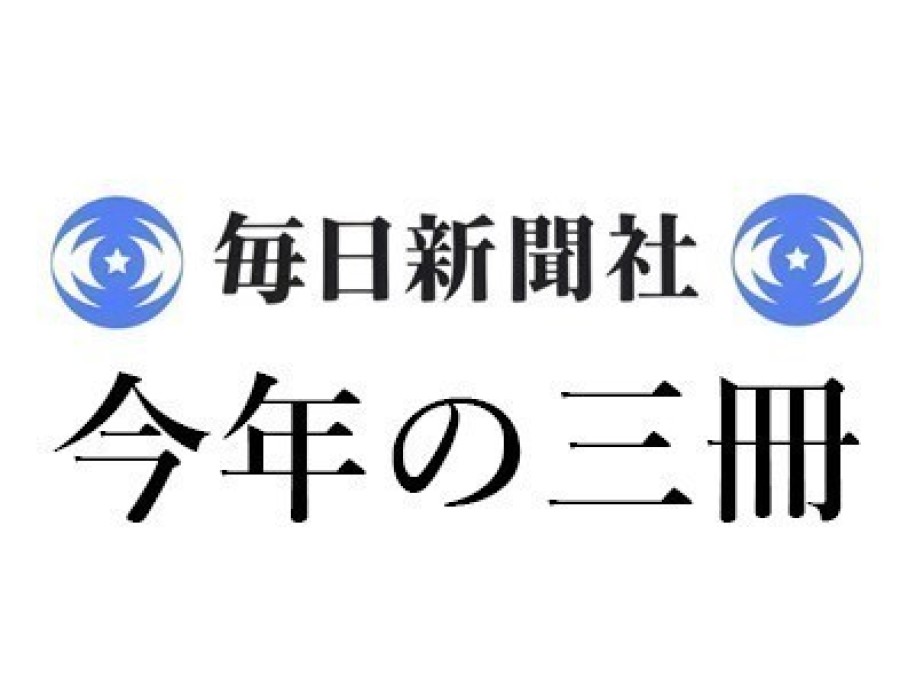書評
『アフリカ的段階について―史観の拡張』(春秋社)
「アフリカ的段階」とは、「アジア的」へのアンチテーゼである。
マルクスが「原始共産制」とのべたものを、なぜ「アフリカ的」と言い換えなければならないのか? このことを、吉本隆明氏の思想の必然性に即して考えてみる。
本書の通奏低音をなすのが、ヘーゲルである。ヘーゲルは十九世紀の初め、歴史を人間精神の集合的な発展の直線的過程として記述するスタイルを編み出した。モルガンやデュルケムの発展段階説も、マルクスの歴史学説も、ヘーゲルの変奏だと吉本氏はみる。それに対してアフリカ的とは、これ以上さかのぼれないプレ・アジア的な段階。ちょうど「大衆の原像」のように、どの社会の、どんな想像力の働きの初源にも見出されるものだという。
アメリカンインディアン・チェロキー族出身の作家が書いた『リトル・トリー』という自伝小説。記紀(『古事記』、『日本書紀』)の神話世界。アフリカ各地の部族の伝承。英国の女性旅行家による、アイヌ民族観察記『日本奥地紀行』。セイロン島の王権について紹介する『セイロン島誌』。時代も場所もさまざまな民族誌の重層的な織り合わせを読み進んでいくうちに、吉本氏が「アフリカ的段階」をどうイメージしているかが浮かびあがってくる。
集合的な想像力の初源のかたちに焦点をあてている点で、本書は『共同幻想論』とよく似ている。『共同幻想論』は、柳田国男の『遠野物語』を素材に、原初的な共同社会の集合的心性(共同幻想)のあり方を記紀の神話世界や古代王権の起源にまでつなげた、巨大な仕事であった。吉本氏はなぜ、それに満足できないで、再び本書を構想したのであろうか?
本書が『共同幻想論』と決定的に異なるのは、疎外論のスタイルと決別している点であろう。吉本氏は、マルクスの歴史学説や西欧近代を至上とする歴史観とまったく違った場所に出るために、初源の位置を「アフリカ的段階」と呼び直したのだ。
「アフリカ的段階」は、初源ではあるが、それ以後のどの段階でも反復して見出されるものである。《アフリカ的ということを段階として設定することは人類の原型的な内容を掘り下げることが永続課題だとすることと同義である》(一四四頁)。そしてもはや、疎外論に特有なねじれはない。『共同幻想論』では、自己幻想や対幻想と共同幻想が“逆立”することが、もっとも本質的であった。逆立しているからこそ、共同幻想は自己幻想や対幻想のあり方と相剋的であり、いずれは解消されることを運命づけられていた。これはマルクス主義にいう、国家権力の廃絶テーゼを言い換えたものである。いっぽう逆立を抜き去った疎外論は、ある原初的なものが直線的な発展の過程をたどるという、素朴な発生論と似かよったものになる。
このため本書は、『共同幻想論』にくらべると、やや平板な印象を与える。発生論のメリットは、発生の過程におけるねじれや屈折、不可逆な創発的現象を織りこめるところにある。原初的なものが繰り返し、逆立する構造を持たずに、発展のどの段階にも見つかるだけなら、それは単に「基本的」と呼べばよく、わざわざ「原初的」とよぶことはないだろう。「アフリカ的段階」を原点とした場合、そこにあとからどんな異なるものが付け加わっていくのか、本書からははっきりしない。人類社会の初源に「アフリカ的段階」を想定することによって、どういう新たな認識がえられるのかが見えにくい。
そこでこう考えてみることができる。本書は、新たな仮説の提示に主眼があるというよりも、これまでの仕事を総括するひとつのマニフェスト(宣言)である。まず第一に、吉本氏自身が、ヘーゲル、マルクス以来の疎外論の文体を最終的に離脱したことの宣言。言い換えれば、マルクスの深い受容から出発した吉本氏の思想が、構造主義以後の世界認識として、本書のようなかたちに収束することが必然であるという表明。第二に、日本の現実に密着してきた吉本氏の思想が、人類社会のあらゆる時代、あらゆる場所でも妥当するはずだという、普遍性の宣言。マルクス主義的なフレームを前提にしているうちは、日本の現実がどんなに特殊であっても、疎外の帰結には違いないから、世界史のなかに(たとえば「アジア的」として)位置づけられると期待できた。そのようなフレームを前提しなくなれば、吉本氏は自分の達成を、「アフリカ的段階」が保証する普遍性のなかに改めて位置づけねばならないことになる。本書はそうした意味で、《史観の拡張》(副題)なのである。
※事務局注:本書評は旧版へのもの。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
マルクスが「原始共産制」とのべたものを、なぜ「アフリカ的」と言い換えなければならないのか? このことを、吉本隆明氏の思想の必然性に即して考えてみる。
本書の通奏低音をなすのが、ヘーゲルである。ヘーゲルは十九世紀の初め、歴史を人間精神の集合的な発展の直線的過程として記述するスタイルを編み出した。モルガンやデュルケムの発展段階説も、マルクスの歴史学説も、ヘーゲルの変奏だと吉本氏はみる。それに対してアフリカ的とは、これ以上さかのぼれないプレ・アジア的な段階。ちょうど「大衆の原像」のように、どの社会の、どんな想像力の働きの初源にも見出されるものだという。
アメリカンインディアン・チェロキー族出身の作家が書いた『リトル・トリー』という自伝小説。記紀(『古事記』、『日本書紀』)の神話世界。アフリカ各地の部族の伝承。英国の女性旅行家による、アイヌ民族観察記『日本奥地紀行』。セイロン島の王権について紹介する『セイロン島誌』。時代も場所もさまざまな民族誌の重層的な織り合わせを読み進んでいくうちに、吉本氏が「アフリカ的段階」をどうイメージしているかが浮かびあがってくる。
集合的な想像力の初源のかたちに焦点をあてている点で、本書は『共同幻想論』とよく似ている。『共同幻想論』は、柳田国男の『遠野物語』を素材に、原初的な共同社会の集合的心性(共同幻想)のあり方を記紀の神話世界や古代王権の起源にまでつなげた、巨大な仕事であった。吉本氏はなぜ、それに満足できないで、再び本書を構想したのであろうか?
本書が『共同幻想論』と決定的に異なるのは、疎外論のスタイルと決別している点であろう。吉本氏は、マルクスの歴史学説や西欧近代を至上とする歴史観とまったく違った場所に出るために、初源の位置を「アフリカ的段階」と呼び直したのだ。
「アフリカ的段階」は、初源ではあるが、それ以後のどの段階でも反復して見出されるものである。《アフリカ的ということを段階として設定することは人類の原型的な内容を掘り下げることが永続課題だとすることと同義である》(一四四頁)。そしてもはや、疎外論に特有なねじれはない。『共同幻想論』では、自己幻想や対幻想と共同幻想が“逆立”することが、もっとも本質的であった。逆立しているからこそ、共同幻想は自己幻想や対幻想のあり方と相剋的であり、いずれは解消されることを運命づけられていた。これはマルクス主義にいう、国家権力の廃絶テーゼを言い換えたものである。いっぽう逆立を抜き去った疎外論は、ある原初的なものが直線的な発展の過程をたどるという、素朴な発生論と似かよったものになる。
このため本書は、『共同幻想論』にくらべると、やや平板な印象を与える。発生論のメリットは、発生の過程におけるねじれや屈折、不可逆な創発的現象を織りこめるところにある。原初的なものが繰り返し、逆立する構造を持たずに、発展のどの段階にも見つかるだけなら、それは単に「基本的」と呼べばよく、わざわざ「原初的」とよぶことはないだろう。「アフリカ的段階」を原点とした場合、そこにあとからどんな異なるものが付け加わっていくのか、本書からははっきりしない。人類社会の初源に「アフリカ的段階」を想定することによって、どういう新たな認識がえられるのかが見えにくい。
そこでこう考えてみることができる。本書は、新たな仮説の提示に主眼があるというよりも、これまでの仕事を総括するひとつのマニフェスト(宣言)である。まず第一に、吉本氏自身が、ヘーゲル、マルクス以来の疎外論の文体を最終的に離脱したことの宣言。言い換えれば、マルクスの深い受容から出発した吉本氏の思想が、構造主義以後の世界認識として、本書のようなかたちに収束することが必然であるという表明。第二に、日本の現実に密着してきた吉本氏の思想が、人類社会のあらゆる時代、あらゆる場所でも妥当するはずだという、普遍性の宣言。マルクス主義的なフレームを前提にしているうちは、日本の現実がどんなに特殊であっても、疎外の帰結には違いないから、世界史のなかに(たとえば「アジア的」として)位置づけられると期待できた。そのようなフレームを前提しなくなれば、吉本氏は自分の達成を、「アフリカ的段階」が保証する普遍性のなかに改めて位置づけねばならないことになる。本書はそうした意味で、《史観の拡張》(副題)なのである。
※事務局注:本書評は旧版へのもの。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする