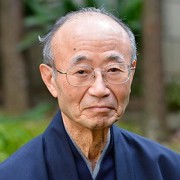書評
『日本思想史骨』(構想社)
幕末の国学と「一神教への呻き」
この新保さんの新著にふれて私は、近ごろ珍しく潔い、そして勁(つよ)い文章に出会ったという思いを禁じえません。新保さんは出光石油という企業につとめながら、すでに「内村鑑三」「批評の測鉛」などの目の覚めるような反時代的な批評の礎石を、この軟弱な思想風土、軽薄な文学砂漠のどまんなかに打ちすえてきた人です(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1994年)。本書の主題は、村岡典嗣という今やほとんど忘れかけている思想史家の仕事を掘りおこし、批評の大道の何たるかを究めようとした点にあります。村岡典嗣は早稲田大学を出て、のち東北大学教授として日本思想史を講じた地道な学究ですが、とりわけ本居宣長や平田篤胤について先駆的な業績を後世にのこしたことで知られています。
たとえば冒頭に、村岡典嗣の「本居宣長」は宣長についての旧約聖書であり、小林秀雄の「本居宣長」は宣長についての新約聖書である、といった刺激的な言葉が出てきます。また平田篤胤の神道思想の中からキリスト教の影響のあとを摘出した村岡の観点をクローズアップして、幕末における国学の流れの中に、「一神教への呻(うめ)き」という激しい思想の葛藤を浮かびあがらせようとしているところがきわめて印象的であります。
幕末期にこのような「一神教への呻き」に似た思想運動があったればこそ、明治に入って内村鑑三のような、「絶対」を仰ぎみる垂直的な思索が生みだされたのだというのが、新保さんの見取り図なのです。そしてこの閃光のような輝きに着目するとき、日本の思想史はたんなるのっぺらぼうの叙述を脱して、精髄としての「日本思想史骨」へと変貌するのだというわけです。
本書にはこの外、藤村、独歩、島木健作、中島敦などを論じた短文がのせられていますが、いずれも衝迫力のある硬質の文章で綴られており、腹の底から元気を喚びおこす快いリズムが脈打っています。著者のさらなる健闘を祈らずにはいられません。
ALL REVIEWSをフォローする