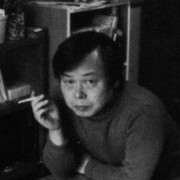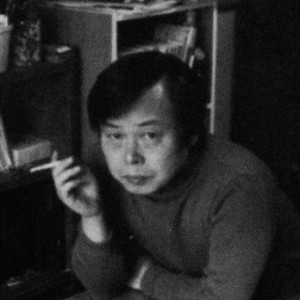書評
『赤頭巾ちゃんは森を抜けて―社会文化学からみた再話の変遷』(阿吽社)
狼を待ちながら
いまさら赤頭巾ちゃんでも、という人もあるだろうが、アメリカには現実に狼がうようよしているらしい。「今私が教鞭をとっている大学では、女性はレイプや暴行対策のため、図書館や教室やキャンパス内で警笛をやむなく携帯しているが、こういった研究施設は決してめずらしくないのだ」こうした研究施設で書いた赤頭巾ちゃん研究なら、実戦気分が横溢してさぞかし迫力があるだろう、とまずは思う。実際、著者は男性だが、戦闘的フェミニストであるらしい。ペローやグリムの赤頭巾ちゃんが、ブルジョア道徳成立以後の、女性のセクシュアリティーの歪曲から生まれた近代の改作であることを明らかにしたうえで、ペロー=グリム以後の赤頭巾ちゃん像を描いてみせる。前者はアリエスやフーコーのいう「子供の誕生」以前、セクシュアリティー以前の、狼がおとなしくて赤頭巾ちゃんがたけだけしかった中世民衆世界にさかのぼることによって、後者は三十一編の赤頭巾ちゃん再話もしくはパロディーをアンソロジー編集することによって。
じつをいうと著者の理論的分析は、すでに論じられてきた個別研究をフェミニズム社会学の方向にそって要約したもののようで、さほどの新味はないような気もする。その点、アンソロジーのパロディー作品は具体的に、ことばの現場で改作童話をこてんぱんにぶっこわしてしまうので、いたってさわやかである。一例が、場末の酒場のマドロスがヘベれけになって語る、赤頭巾ちゃんも狩人も、なんでもかんでもぺろりと食べてクジラになり、そこらの街角に上陸してきたという怪おばあさんについての、キャバレー詩人リンゲルナッツのしりめつれつのたわごと。パロディーは原話からデタラメに独立するほど、原話以前の原話、神々以前の神々に近づくという好例だろう。
著者によれば、ブルジョア的赤頭巾像をくつがえすにはあと二百年かかるだろうという。かりに二百年かかって狼が絶滅し、八歳から八十歳までの狼を知らない赤頭巾ちゃんがずらりとならんで、ゴドーを待つように狼を待つ日がくるとしても、いま十八歳の赤頭巾ちゃんには手後れである。いまここで、赤頭巾ちゃんとして狼にたわむれるには、アンソロジーからよりどりみどり、お好きなタイプの狼をえらぶにしくはない。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年7月8日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする