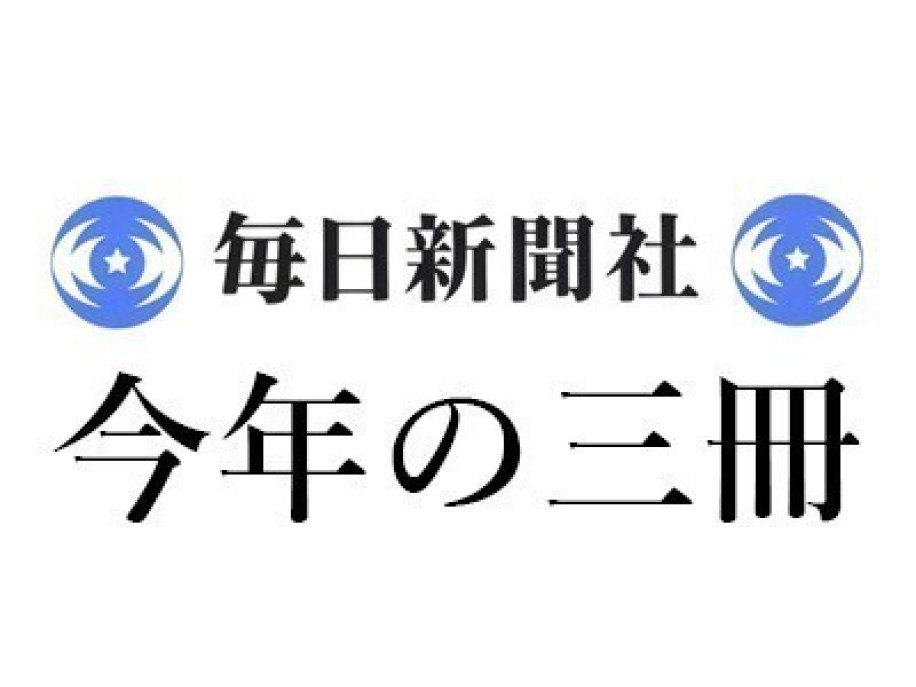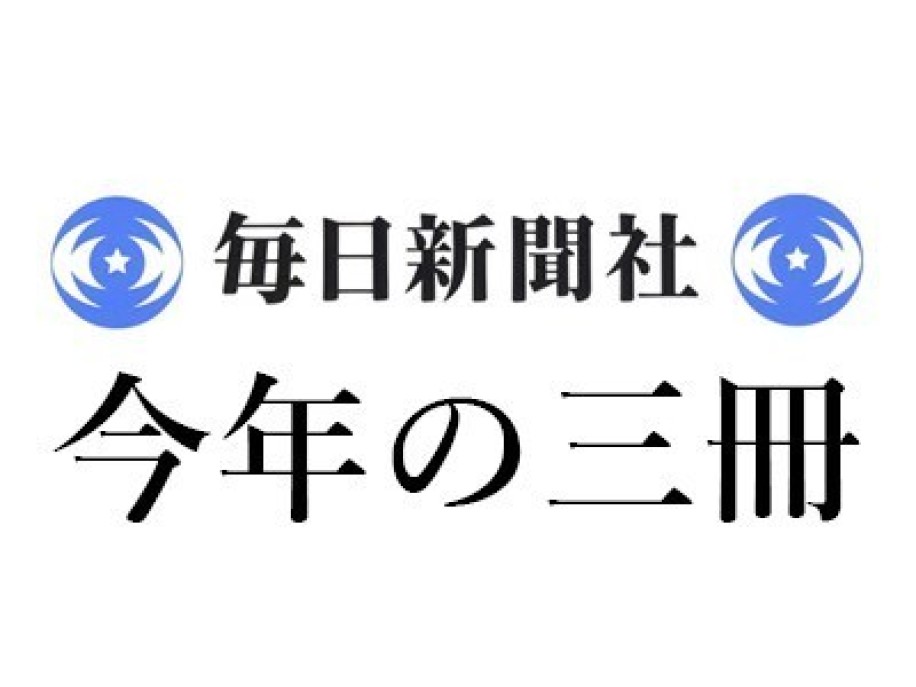書評
『野良ビトたちの燃え上がる肖像』(新潮社)
ただの人でいられない語り手たち
恐ろしい小説が書かれた。近未来小説というのは、だいたい数十年から百年後ぐらいに時代が設定されているが、本作は、二年後に世界スポーツ祭典が東京で開かれる(東京オリンピック)という記述からして、ごく近い二〇一八年あたりの日本を舞台にしているようだ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2016年)。たった二年後にこんなことが起きるか?という疑問はまったく感じなかった。むしろ、もう起きつつある、起きているのだという現実感がそくそくとして迫ってくる。主役たちは、東京と神奈川の間を流れる「弧間(こま)川」の河川敷に住みついた家なき人々だ。近くの町にある日、「野良ビト(ホームレス)に缶を与えないでください」という、「野良猫に餌を与えないでください」と同じ調子の看板が立てられる。河川敷住人の多くはアルミ缶拾いをして生計を立てており、その缶をやるな、というのである。一方、富裕層はアメリカ式の「ゲーテッドタウン」内のタワーマンションに暮らす。警戒厳重なゲートで外界と仕切られた超高級住宅地であり、これが河畔に建設されたことで、界隈(かいわい)の雰囲気が勢い変わってきたらしい。自分にとって不可解、不愉快、不都合なものは排除してよいという空気が流れだした。それはこの国全体の「不寛容」と連動していると、河川敷住人のひとりは言う。
鉄塔専門のペンキ屋だったが転落事故にあった「柳さん」(仲間の形見である最愛の白猫「ムスビ」と同居)、元板前で競馬予想の得意な「梶さん」、元電気屋で拾った家電を修理して売る「細田さん」、元土建業で釣り名人の「徳田さん」、寝たきりの老父を介護する「ケンさん」、暴力夫から逃げてきた「三村さん」と娘……。ひとり異分子なのは「木下」という青年だ。雑誌記者だったが廃刊になり、河川敷を住みかとする。川べりにはホームレスが溢(あふ)れ、弱者がさらに弱者を虐待するようにもなる。ミャンマーでごく少数のロヒンギャ(イスラム教徒)はここでも迫害にあう。
住人らの抱える事情はそれぞれでも、日本経済のしわ寄せをもろに受けている点では共通する。本作の背景にあるのは、「大企業が儲(もう)かれば社会全体が潤うと宣伝して政府が推し進めた経済政策」の失敗だ。中小企業は倒産、ホームレスが増大した。さらに怖いことに、景気を口実にして政権批判ができないよう、「景気が悪いことを言うと罪になる『不景気煽動(せんどう)罪』」が立法化されようとしている。ホームレスの大群は「東京世界スポーツ祭典」の開かれる東京近郊にいないはずのものであり、まとめて隔離・移送する計画が動きだす。しかし収容するにもまず人数を減らす必要が……。
終盤、攻撃された住人が「おれら、(退治)ゲームのキャラクターじゃねぇぞっ」と叫ぶ場面では、同時期刊行の羽田圭介『コンテクスト・オブ・ザ・デッド』も想起した。あるとき世界中にゾンビが出現するという、社会風刺&文壇批評小説だが、生活保護申請者やホームレスたちがゾンビ化して一掃されたり、ゾンビの隔離分離政策が立てられたりする。そう、同調圧力に決死の抵抗を試みるのは、今年話題をさらった村田沙耶香の『コンビニ人間』も同じである。「野良ビト」「ゾンビ」「コンビニ人間」……もはやいまの日本を描くには、語り手はただの人ではいられないようだ。
『野良ビト』に一つだけ望むことがあるとすれば、残り三十ページでの急な視点変更である。住人のほとんどを「さんづけ」する独特の文体には、どこかから共同体を俯瞰(ふかん)的に描く大きな眼差(まなざ)しも感じていただけに、このナラティブの切替えは起きないことを願っていた。
ALL REVIEWSをフォローする