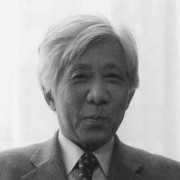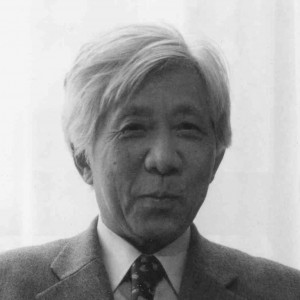書評
『荷風と東京 『断腸亭日常』私註』(岩波書店)
実像見据え細部に迫る
十年前に出たエドワード・サイデンステッカーの好著『東京 下町山の手』は永井荷風の霊にささげられている。荷風こそは導きの師、道行きの友だったと、この恐るべき知日家のアメリカ人は書いていた。荷風を導き手として東京論を試みる。これは奇手でもなんでもない。正攻法の一つでさえある。しかし、ものには程度がある。前後四十二年に及ぶ「断腸亭日乗」をすみずみまで読み込んだ上で、あらゆる細部に立ち入って「荷風と東京」を浮かび上がらせるアイデアは確かに心をひくが、なまはんかなことでやりおおせる仕事ではない。少なくとも五年ぐらいは、一意専心、他のことを全部棚に上げる覚悟がいるだろう。
本の帯に川本三郎の"ライフワーク"とあるが、掛け値のないところだと思う。
川本氏は東京歩きの名人だ。特に東京の東部をこつこつと精密に歩いてきた。その、マニアックとも見える歩行者の足音が、今度の大著の至る所に反響している。現場へ行く。それが、大方針だ。たとえその現場が、荷風の見たものとは似ても似つかぬ無機的な風景になっていようとも。
荷風は父親の遺産で暮らした。家族をつくらず、もっぱら私娼(ししょう)を買った。人間の葛藤(かっとう)劇に加わらない"観察者"だった。わびしい東京の裏町を偏愛しながら、山の手・麻布のがけの上で孤独を決して手放さなかった。そういう実像を見据えながら、川本氏はしんそこ荷風を愛し、荷風と一体にさえなる。背水の陣という言葉が浮かんでくるほど、川本氏の姿勢は鮮明で、留保の濁りがない。
いろいろ書いたが、この一千枚の大著は誘惑的な情報でいっぱいだ。書物と街頭と、その両方から集めてきた生きのいい情報が、落ち着いた、大人の語り口で、ふんだんに提供されている。大きいが、重くない本だ。
ALL REVIEWSをフォローする