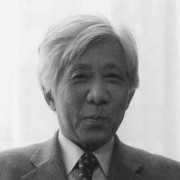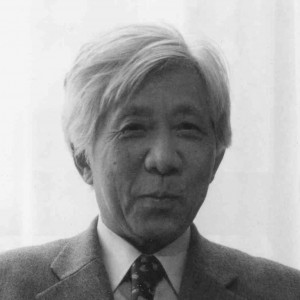書評
『1900年への旅―あるいは、道に迷わば年輪を見よ』(新潮社)
百年前の日欧の人物像
世界をあげての大騒ぎのすえ、何はともあれ西暦二〇〇〇年は到来し、すでにして四分の一を消化した。だが、二十一世紀はまだ来ていない。これから年末まで、「二十世紀とは何だったのか」という企画がはなやかに競われることだろう(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2000年)。寺島氏の新著は、ちょうど百年分、視点を後退させる。西紀一九〇〇年に、パリやロンドンはどんな国際関係の中にあったか。英国の首都に着いたばかりの漱石は、まず何を考えたか。この年フロイトは、問題の書「夢の精神分析」を出版している。そしてロンドン西方の小さな町イートンでは、あのケインズが、名門パブリック・スクールの三年生として、猛勉強の日々を送っていた。
ヒトラーはどうか。オーストリアのブラウナウに生を受けたアドルフは、一九〇〇年、小学校を卒業してリンツの実科学校に入学している。スペインのフランコはこの時八歳、イタリアのムソリーニは十七歳、西欧独裁者トリオはまだとても揃い踏みをするところまで行っていない。
こんなふうに書くと、この本、エピソード集と取られかねないが、とんでもない話で、これは文献調査と現地歴訪をともども目いっぱいに果たした“問題提起”の書だ。「オッペケペー節」で有名な川上音二郎の欧米巡業が、サムライ、ハラキリ、ゲイシャのたぐいの安っぽい“日本”を白人たちの脳裡に植え付けたのでは、と強烈な疑義を呈するあたりにこそ著者の面目がある。
ヨーロッパと渡りあった日本人は、西園寺公望から南方熊楠まで、広瀬武夫から森鴎外まで、いかにも、と思われる人物が登場する。しかし、代理公使クーデンホーフ伯爵と結婚してオーストリアに渡り、波乱の生涯を送った江戸商人の娘青山光子に、寺島氏はいちばんの共感を寄せていると見た。
初出メディア
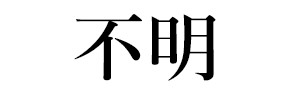
初出媒体など不明
正しい情報をご存知でしたらお知らせください。
ALL REVIEWSをフォローする