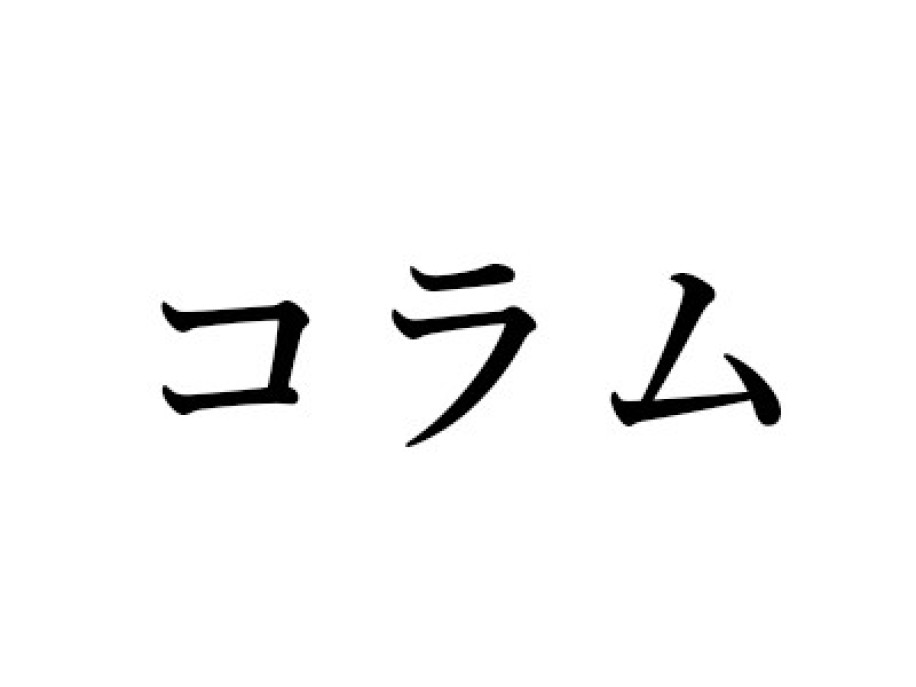書評
『光る源氏の物語』(中央公論社)
王朝貴族の昼と夜
日本人が世界に誇れる長篇小説といわれる「源氏物語」。しかし、日本人のどれだけの人が読んだことがあろうか。かくいう私とて、ほとんどはつまみ食いの状態で、読み通したことなど一度もない。いくら読んでもさっぱりわからない。わからないから面白さもあまり伝わってこない。注釈書を横に置いて読むうちに、ただただストーリーの展開だけを追う始末なのである。
それがどうか。本書を読むにつれ、本格的に「源氏物語」を読んでみたい、という気になってきた。新たな魅力がひきだされ、その面白さが伝わってくるからに他ならない。
このなかで国語学者の大野晋は、物語の作者の目をもって、小説家兼批評家としての丸谷才一は、小説の作り手の目をもって、それぞれ「源氏物語」の内部に、さらに作者紫式部の内実に踏みこむ。こうして物語論と小説論とがかわされ、「源氏物語」の全貌が明らかにされてゆく。あたかも大野式部と丸谷式部の対談といった風情があり、何とも興味深い。
たとえば、大野は、「源氏物語」の前半をa系列とb系列の巻に分類し、それに作者の構想を絡ませて、次のように解剖する。「『源氏物語』の作者はきわめて論理的で明快な頭をもっていますね。ごてごてした筋の物語なんか最初から書いてない。a系を通して読めば、お話は非常に単純ですっきりしていて……結局めでたしめでたしで終るお話がつくられている」
また「紫式部はシメトリーが好きな人で、AといえばマイナスA、BといえばマイナスBと必ず照応するんですよ」とも。
丸谷は小説の作法という観点から、作者の書きっぷりを解剖する。
「ここはとてもいい場面のはずなのにベッド・シーンがあまり上手じゃないですね。たとえば藤壷がどんなにすばらしい女なのかを描写する……形容だくさんの言い方は、理屈としては筋は通っているけれども、小説的陶酔には導かない。訳していて、まあ、なんてへたなんだろうと思いました」
あるいは、「恋愛につきまとう滑稽な趣を宮中風俗によく生かして大変面白い。こういうのは風俗小説的な魅力が非常によく出ていますね」と。
二人とも思ったことを率直に、薀蓄(うんちく)をかたむけて話をするから、同席しているような気分にさせられ、ついついひきこまれてしまう。しかも放談のようなザックバランさをもちながらも、実によく勘所は押さえている。要所要所の文章が引用され、丸谷による訳が付されているので読みごたえもある。
ところで、「源氏物語」の困るところは、文章が曖昧模糊として何がどうなり、おこったのかわからない点である。男女の仲をあれほど扱った物語なのに、その点がわからないでは話にもならない。そのため「実事のありなしをいつもきちんと押さえていかないと、『源氏物語』は読めなくなります」ということになる。
丸谷 いいところですね。あそこは裸でしょう?
大野 裸かどうか、ちょっとそこはぼくには……。
丸谷 だって、女房は御衣を隠し持っているわけだから。
大野 ええっ?そんなに続いているの、ここ。
二人とも好きなんですね。ほんと。
ひとつひとつのディテールを大事にすること、ことばへの感性を養うこと、自らの目をもって読むこと、それらによって「源氏物語」の可能性が大きく広がることを本書は教えてくれた。
秋の夜長は「光る源氏の物語」といった塩梅(あんばい)の本である。
ALL REVIEWSをフォローする