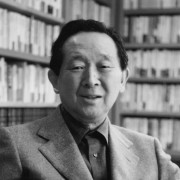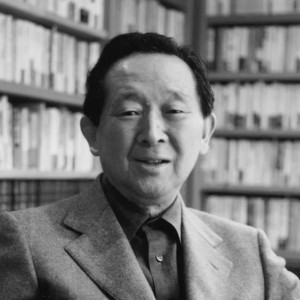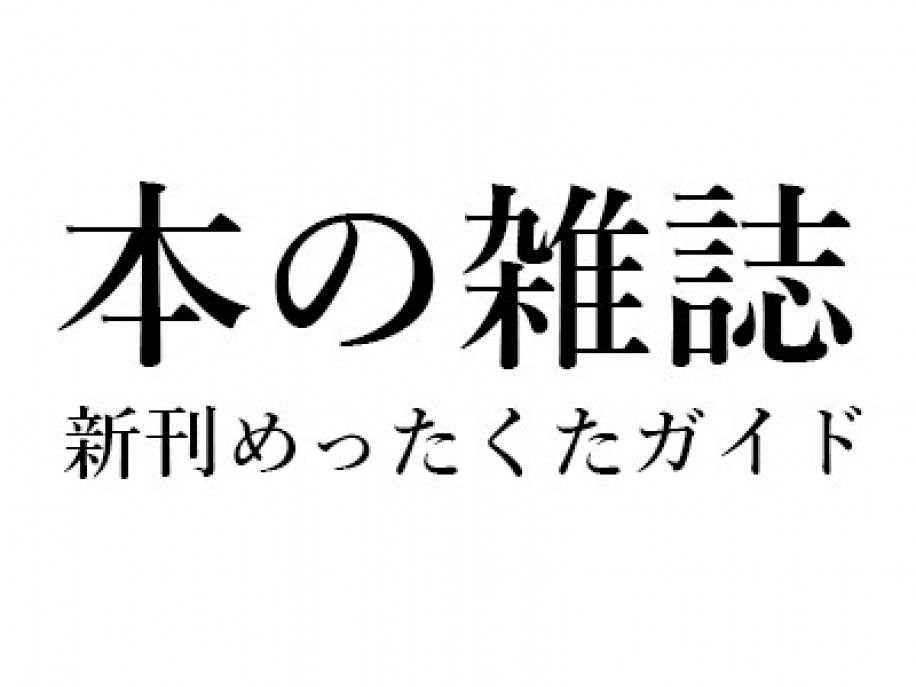書評
『小説 大逆事件』(文藝春秋)
明治四十三年の大逆事件で逮捕された被告たちの供述書をこの小説で順を追って読んでいくと、事件が広くかつ緻密な計画によって進められていたかのような姿が浮かんでくる。
しかし、この広さと緻密さは検察の頭のなかに描かれていたもので現実には存在していなかった。
事実は宮下太吉という長野県明科(あかしな)製材所の職工長が、彼独特の無政府主義思想から天皇を襲撃しようと思いついたところからはじまったのだ。荒畑寒村と離婚し、ついで幸徳秋水とも別れた管野スガと三名の男がそのための爆弾製造に参画したらしい。
しかし「西園寺内閣は社会主義者の取り締りが甘い」と批判した元老の山県有朋が、赤旗事件、不敬事件を天皇に上奏したために、引責辞職せざるを得なくなったような当時の権力構造がこの事件を放っておかなかった。後を継いだ第二次桂内閣の司法省刑事局長(大審院検事兼務)は、
「一人の無政府主義者もなきことを、世界に誇るにいたるまで、あくまでも撲滅を期する方針」を立てて捜査検事に檄(げき)を飛ばし、事件は全国的規模のものに拡大されていった。
社会を驚かせるには、著名人や意外な徳望家が逮捕者のなかにいることが好ましかった。幸徳秋水と新宮の人望のある医師大石誠之助の名は検察にとって必要だったことが多くの被疑者の供述の変化のなかに読み取ることができる。結局、逮捕者は二十六名に及んだ。裁判は非公開で行われ、一年たらずの四十四年一月に判決が下った。うち十二名の死刑囚に天皇の御聖断で無期懲役の減刑が行われ、新聞は「広大無辺の聖恩」とその慈悲を讃えた。
この事件は、いつか誰かによって書かれなければならなかったのだ。思い入れを廃し、実証的に事柄を追って全体像を浮び上らせる様式を作家として確立した佐木隆三は最も適切な著者であった。誤れる〈不敬思想〉と短慮のために大勢の人々を巻込んでしまった宮下太吉が、存在感を持った人物として描かれているところにも、この作品の成功と著者の筆力を感じることができる。
【この書評が収録されている書籍】
しかし、この広さと緻密さは検察の頭のなかに描かれていたもので現実には存在していなかった。
事実は宮下太吉という長野県明科(あかしな)製材所の職工長が、彼独特の無政府主義思想から天皇を襲撃しようと思いついたところからはじまったのだ。荒畑寒村と離婚し、ついで幸徳秋水とも別れた管野スガと三名の男がそのための爆弾製造に参画したらしい。
しかし「西園寺内閣は社会主義者の取り締りが甘い」と批判した元老の山県有朋が、赤旗事件、不敬事件を天皇に上奏したために、引責辞職せざるを得なくなったような当時の権力構造がこの事件を放っておかなかった。後を継いだ第二次桂内閣の司法省刑事局長(大審院検事兼務)は、
「一人の無政府主義者もなきことを、世界に誇るにいたるまで、あくまでも撲滅を期する方針」を立てて捜査検事に檄(げき)を飛ばし、事件は全国的規模のものに拡大されていった。
社会を驚かせるには、著名人や意外な徳望家が逮捕者のなかにいることが好ましかった。幸徳秋水と新宮の人望のある医師大石誠之助の名は検察にとって必要だったことが多くの被疑者の供述の変化のなかに読み取ることができる。結局、逮捕者は二十六名に及んだ。裁判は非公開で行われ、一年たらずの四十四年一月に判決が下った。うち十二名の死刑囚に天皇の御聖断で無期懲役の減刑が行われ、新聞は「広大無辺の聖恩」とその慈悲を讃えた。
この事件は、いつか誰かによって書かれなければならなかったのだ。思い入れを廃し、実証的に事柄を追って全体像を浮び上らせる様式を作家として確立した佐木隆三は最も適切な著者であった。誤れる〈不敬思想〉と短慮のために大勢の人々を巻込んでしまった宮下太吉が、存在感を持った人物として描かれているところにも、この作品の成功と著者の筆力を感じることができる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする