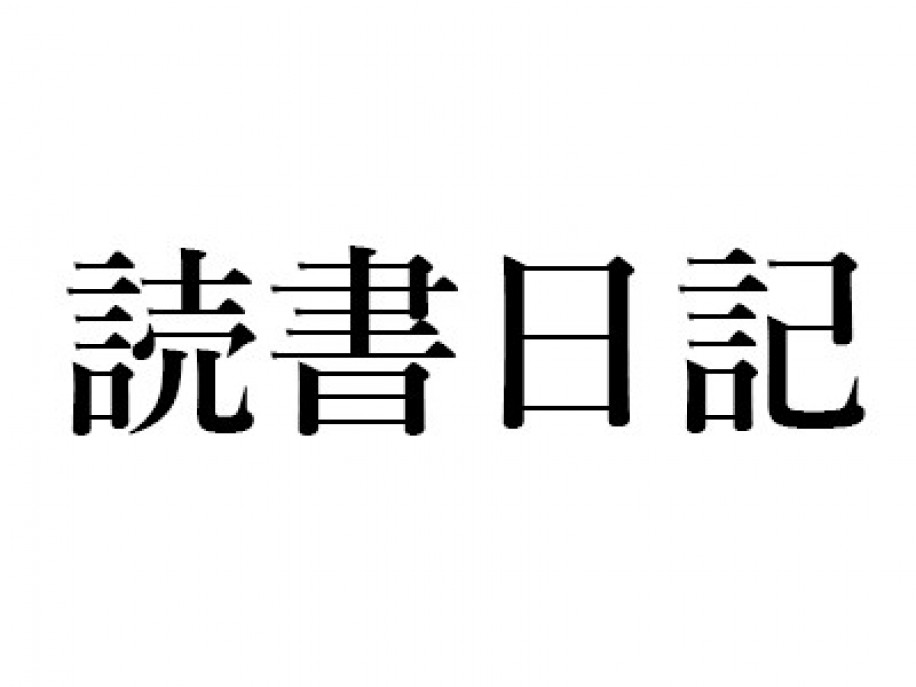書評
『江戸時代 古地図をめぐる』(NTT出版)
「お上りさんの武士用」「つけとどけ用」などいろいろと
コレクターの時代が始っているように思う。この頃、主義主張や人生をテーマとした本よりは、物を集めてきた人の話のほうがよほど興味深い。コレクターおよびコレクションという営みに関しては、すでにいくつかの法則が発見されている。その一、男だけが役に立たないものを集める。これは身近な例をふり返るとすぐ納得できよう。その二、コレクションには上限がある。たとえばマッチのラベルを例にとると、その製作点数は有限で、数万点を集めるとそこで上限に達する。実際、日本では達した人物がいて、彼の出現によってこの分野の膨張は急速にしぼんだ。
日本の古地図、とりわけそのほとんどが刊行された江戸時代の古地図の収集についてはかつて岩田豊樹という上限が存在し、岩田氏の亡き後、上限に迫るかどうかを注目されている山下和正がこのたびはじめて本を出した。
といっても、自分のコレクションの貴重さを語ったり、集大成したりする内容ではなくて、コレクションを通して身につけた古地図という魅力的な領分への入門書である。九十五点の地図を見開きで紹介し、そこに解説を付しているのだが<江戸図><一般道中図><巡礼道中図><航路図><島図><河川図><海岸図><温泉図>などなどの著者独自の分類がまず目を引く。コレクターにとって、膨大なコレクションをどう分類するかは重要なテーマで、大量に集めた人ほど良い分類を提案できる。<島図>とか<温泉図>とか奇怪な分け方のように思うが、上限に迫る中で自ずと成った二十八の分類であり、図書館の地図分類は参考にすべきだと思う。この分類に従ってページをめくってゆくと、江戸時代の日本人はよくもマアこんなにいろんな地図を出したものかとあきれる。同時代のヨーロッパにくらべても独自の発達をとげていたという。
たとえば、幕末の京都で出された<京都明細之全図>。「全国から上洛した各藩兵や、志士浪人、新撰組などが町民を巻き込む形で入り乱れ、市中は緊張が高まっていった。そのような世相を反映して、各藩邸、禁裏御所、各公家などの位置を端的に示し、主としてお上りさんの武士用に作ったのがこの図」
たしかに言われてみると、坂本龍馬も土方歳三も、京に入ってまず買ったのは地図のはず。町の中を追いつ追われつするには良い地図は欠かせない。悪い地図の方が負けるのだから。
大阪で文化三年(一八〇六)に出た<浪華御役録>というのも面白くて、天満にあった町奉行所の与力・同心の住宅地の詳細図で、一人一人の名前と居所が記されている。なんでこんな社会性の乏しい地図が刊行されたかというと、つけとどけ用で、実に社会性は高かったのである。
温泉の地図(道中図と市街図)の発達は日本独自だそうで、たとえば嘉永五年(一八五二)の<出羽荘内湯之浜温泉図>を見ると、温泉宿の他に、米屋の三治郎、髪結の亀吉、豆腐屋の甚兵衛、そしてムマサシ(馬刺屋それとも馬喰?)の万太郎さんの家まで記入され、鄙(ひな)にはまれな充実ぶり。
なお、著者は日本を代表する建築家の一人でもあるが、岩田豊樹との出会いによって古地図という底無し沼にはまってしまったそうだ。法則その三、類は友をはめる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする