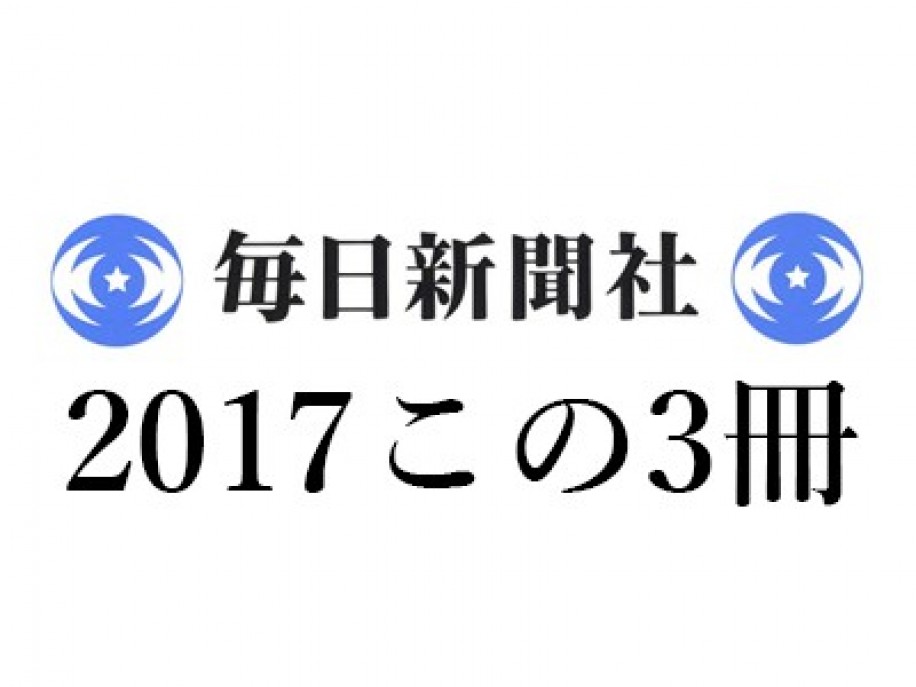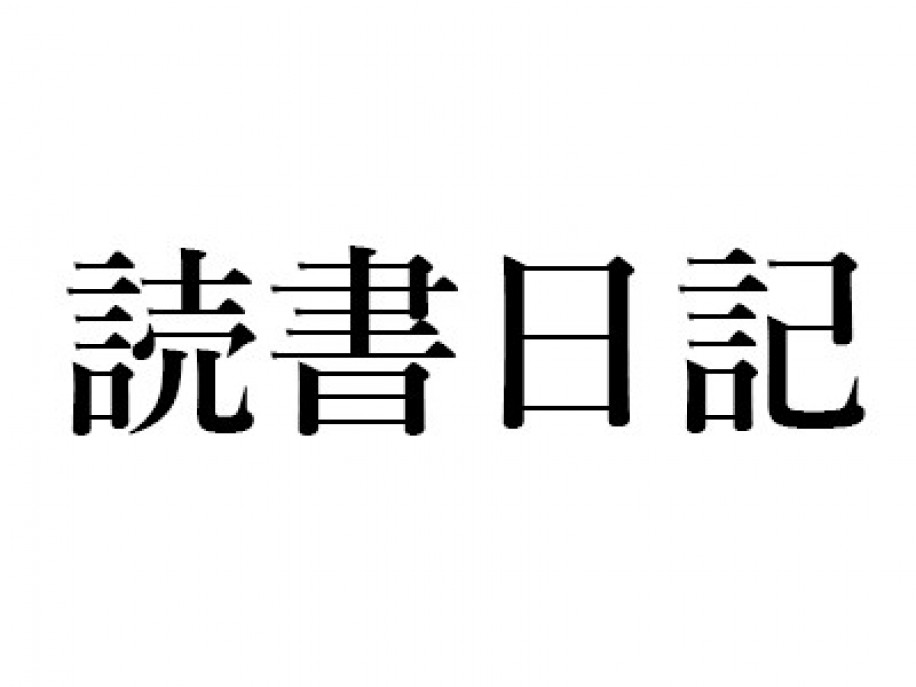書評
『移りゆく「教養」』(NTT出版)
説教くさくない教養論
『移りゆく「教養」』を読む
近ごろの学生に「教養がないねえ」といってもつうじにくい。しかし、そんな慨嘆ばかりしていると、教養論はますます説教くさくなり、現実離れをしていく。そもそも教養主義者というのは、知識の所有に専念し、ひけらかすきらいがあるから、ちょっぴり嫌みが入った説教くさい人である。本書(苅部直『移りゆく「教養」』NTT出版、二〇〇七年)の教養論が新鮮なのは、そうした説教くささとは無縁であるからだ。
著者は教養とはカルチュアであるとして、「人と人がさまざまな活動をおたがいに行なう上で、前提にしている共通のものの考えかた」(一三頁)とかみくだいて説明している。
そこで教養の意味を政治的教養につないでいく。政治的教養は、狭い意味での「政治」ではなく、他人との関係のなかで生きる知恵のことであり、そうした知恵を伝えあい、更新していくことである。
著者のいう政治的教養は、近年提唱されているシティズンシップ教育(市民活動によって全体の決定にかかわり、共同体を支えていくための市民性教育)につながっていくものである。
と書くと、抽象論かとおもうかもしれないが、長野県飯田市で著者自身がおこなったフィールド・ワーク(公民館活動や「いいだ人形劇フェスタ」)にふれながら論じられているから、地に足のついた教養論となっている。
読書だけが教養ではないことは確かだが、人間が言葉によって世界と他者を理解し、自己表現していくかぎり、読書なくして教養はなりたちにくい。
著者はこういう。「読書」は教養へとむかう「踏み台」となり、教養の営みと「伴走」するものである、と。至言である。
エリート主義的教養論にくみしないが、さりとて大衆迎合のポピュリズム教養論に棹さしているわけではない。柔らかな文体と目配りのきいた論述がひかり、説得力に富んでいる。
ALL REVIEWSをフォローする