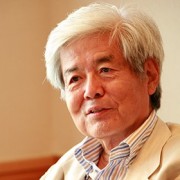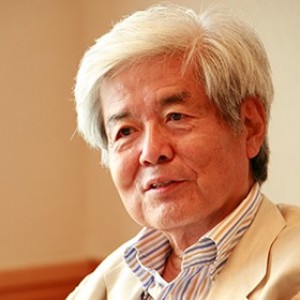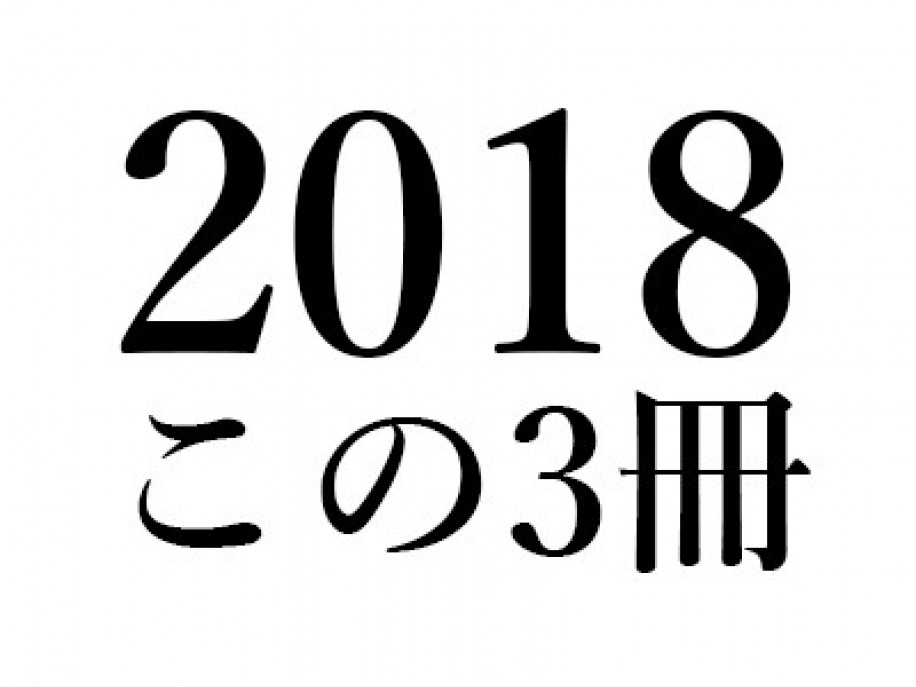書評
『脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出』(新潮社)
自らの病を経て真に理解
四十代の初めに著者は脳梗塞(こうそく)になる。そのいきさつを描いたのが前作『脳が壊れた』(新潮新書)である。今回はその続編で、脳梗塞の結果生じた高次脳機能障害について報告している。漢字を七つもつなげたこの用語は、あまり良い表現ではない。専門用語だからやむを得ないとはいえ、口語としてはとくに使いにくい。じつは著者の妻も似たような障害を持っている。夫婦の会話の中で、だから「脳コワさん」という表現が生まれた。本書はその「脳コワさん」の苦しみをまさに活写している。
他人の病気の話なんて、読みたくないよ。その気持ちはわかる。しかし「脳コワさん」つまり高次脳機能障害は、かならずしも病気とはいえない。現に著者夫妻はその状態で日常生活を送り、著作をし、社会生活に参加しているからである。つまり本書は負の状態を抱えた人たちが、いかに生きるか、その人生の模索を基本の主題としている。じつはそれは著者が病前ルポライターとして書いた『最貧困女子』(幻冬舎新書)の主題に通じる。自らの病を経て初めて、著者は自分が取材してきた人たちをいわば真に理解した、と感じる。人生にはこうした皮肉なことが起こるらしい。
著者の症状の一つに離人体験がある。教科書的にはよく知られた、自分のことなのに現実感が乏しく、他人事(ひとごと)のように感じられる状態である。私も医学生の時にこれを習い、患者さんも診たことがある。しかしその理解がいかに「理解ではなかった」かは、著者の語りからよくわかる。「全身をサランラップでグルグル巻かれたような」という表現を著者はしている。さらにその状態がじつはきわめて苦痛である。その苦痛に気づかなければ、他者は離人体験を「ただぼんやりしている」としか考えないはずである。「猛烈な閉塞(へいそく)感・窒息感がある」ので、「その現実感のなさから逃れたくて、自分の身体を鋭い刃物で切り刻みたいという強い衝動に駆られた」と著者は書く。この体験を著者は「井上陽水」と表現する。羊水に包まれたような、という感覚と、語呂合わせをしているだけだが、ネットにあげてみると、「自分にも陽水がいる」という返事が、いくつも返ってきたという。
陽水以外にも紹介したい症状はいくつもある。架空アイドル現象、夜泣き屋だいちゃん、イラたんさん、初恋玉などなど。むろんなんのことやら、さっぱりわからないであろう。これらについては、本書をぜひ読んでいただきたい。間違いなくその方がいい。なぜなら本書の第一の価値は脳機能障害のある患者自身が、自分で報告をしているという点にあるからである。こうした障害では言語能力が失われることも多いので、患者自身がこのように明確な訴えができる症例が少ない。現代医学はいわゆる客観性を重んじるあまり、患者自身の訴えを軽視する傾向がある。それは著者の医師に対する批判を読んでもよくわかる。
本書はいくつかの意味で、僥倖(ぎょうこう)の産物とも言える。第一は右(ALL REVIEWS事務局注:上)に述べた著者の言語能力が優れていることである。第二は、病前からの著者の関心が、それと気づかず、じつは「脳コワさん」たちにあったということ、さらには、連れ合いがそういう人であり、家庭での理解に恵まれたことである。本書を私は知り合いの臨床家二人に読んでもらったが、二人ともに高い評価をくれた。医師、看護師に限らず、いわゆる問題児や社会的に問題がある人に関わらざるを得ない仕事の人たちには、必読書であろう。
ALL REVIEWSをフォローする