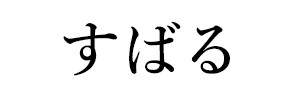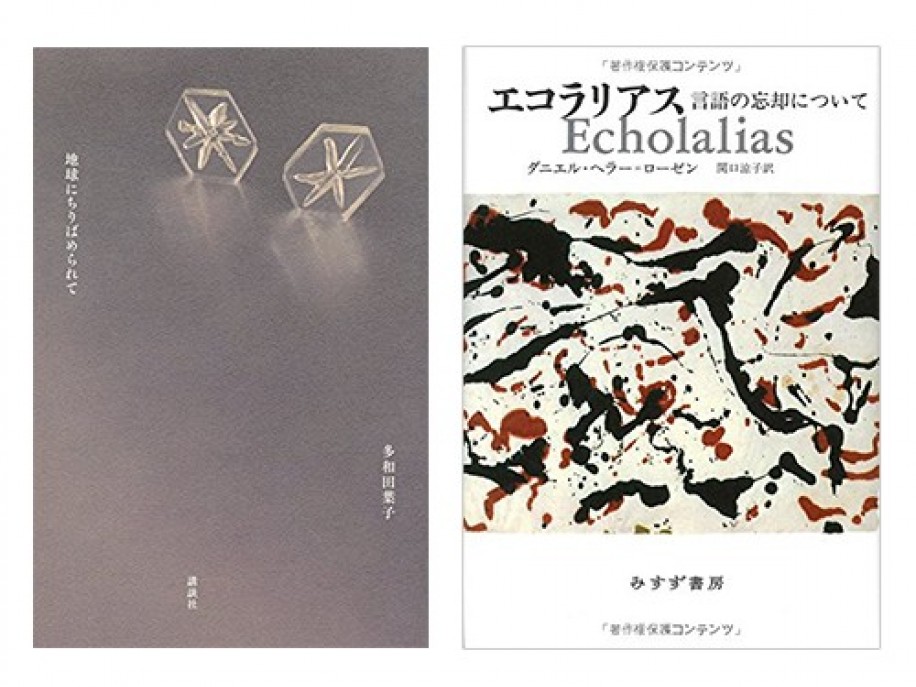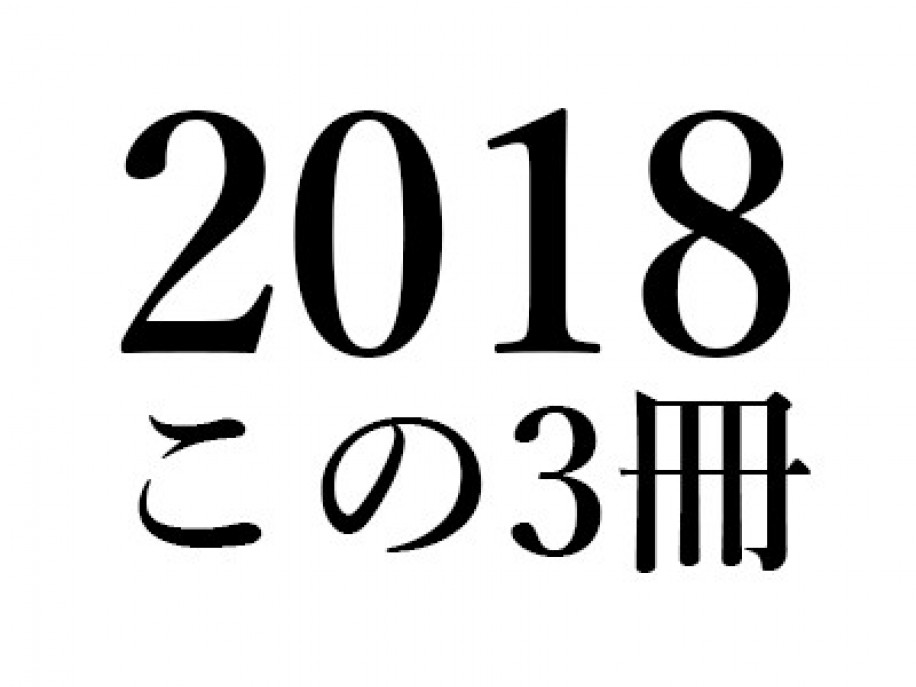書評
『エコラリアス』(みすず書房)
言語の谺(エコー)を聴く――言葉は死ぬのか?
言語学者デヴィッド・ハリソンの「言語が亡びるとき 世界の諸言語の絶滅と人類の叡智の風化」(未訳)、そして同書を踏まえたと思しき水村美苗の『日本語が亡びるとき』が世に出たのが、いまから十一年前と十年前である。とくに後者は日本語読者に大きな衝撃をもたらした。人類の長い歴史のなかでは、多くの言語が消滅してきたし、それは自然の成り行きだった。ところが、近年、世界のグローバル化と英語の覇権の強大化に伴い、小さな言語の「死ぬ」スピードが加速度的に増しているという危惧が、それらの書では呈されたのだ。
ハリソンはつづけて『亡びゆく言語を話す最後の人々』(川島満重子訳)を書くため、話者わずか数人という絶滅寸前の言語の記録にも尽力し、シベリアの奥地で、地形と水流の位置および向きと深く結びついたトゥバ語に接し、言語文法に対するチョムスキー的な考えを一変させる。つまり、言語の統語論と意味論は別物とみなす考えに反発し、「文法とはその土地の風景に『埋め込まれて』いる」とさえ断言した。だから、インディアンのワショ語の衰退とともに、居住地の湖が荒廃することもあるし、逆に環境の悪化で言語が途絶えることもある、と言えるのだ。
ともあれ、ここしばらく、言葉にコンシャスな人々の間には、言語の「死」に対する漠たる(あるいは強烈な)不安があった。さて、ここに、比較文学者ダニエル・ヘラー=ローゼンのきわめて刺激的な『エコラリアス』の邦訳書が登場する。本書は、言語の消滅あるいは忘却をむしろ起点に語られていく言語哲学書だ。言語とは、忘却と引き換えに習得されるものだと、著者は第一章で宣言する。
では、言語の死とはいかなるものか? 言語はいつ死んだと言えるのか? それはよく言われるように、話者の最後の一人が亡くなった時ではなく、伝達する相手を亡くした時ではないのか? いやいや、ある谷の方言は、最後の話者である老人が亡くなってから十年後にその地を訪れてみると、話者の孫や生徒のなかに「幽霊」のように生き返っていた。そんなこともある。
ヘラー=ローゼンは問う。そもそも言語は本当に死ぬのか?と。「言語の死」という言葉がいささか不用意に使われていたことに気づく。学者たちは言語の死亡時刻を特定し、死亡証明書を出したがるが、それは、本書にも登場するエドガー・アラン・ポー流にいえば、「早まった埋葬」なのではないか。ひとつの言語はある日、急に生まれ、なにかを境にぱたりと死ぬわけではない。より大きな、強い、威信のある言語に取って代わられたり、吸収されたり、自ら不活性になったりしたように見えて、その存在は他言語のなかに持続するのではないか。ヘラー=ローゼンは生き物の「生き死に」とのアナロジーから、言語を務めて解放しようとする。
言語はときに流離を強いられるが、流亡が言語の衰退、滅亡を意味するとは限らない。ヘブライ語詩の「黄金期」は、この言語で詩が生まれた祖国からユダヤ人の書き手たちがすっかり遠ざかってしまった後の、イスラーム時代のスペインに出現したことを著者は特記する。アラビア語の韻律を取り入れたヘブライ語の詩集成が現れ(これは、アラビア語が「廃語」の位置に落ちたように言われたそうだが)、その複合性がヘブライ文芸の命脈にもなった。
タイトルに使われているEcholaliasとは「谺する言語」、反響言語のこと。幼児がおとなの言ったことをおうむ返しに口にするのなどもそれにあたる。ヤコブソンいわく、まだ喃語を話している段階の乳幼児はあらゆる音声を発音できる。ところが、母語の音声システムに適応するうちにその能力を失ってしまうという。その時点から、ひとつの言語の習得が始まったと言えるのだ。しかし喃語の記憶はすっかり消えてしまうわけではない。たとえば、オノマトペに現れたりする。
言ってみれば、わたしたち成人の言語は”喃語の極み”の谺(エコー)であり、忘れ形見のようなものなのか。
世界のあらゆる言語にエコラリアス(残響)を聴くヘラー=ローゼンは、本書の解説者の弁を借りれば、「言語を忘却することで人は言語を獲得し、そのようにして獲得された言語は他の言語の痕跡を谺として残存させる」という「寓話」を、カフカ、カネッティ、ブロツキー、ダンテ、オヴィディウスの例を引き、文学、哲学、言語学、神話、精神分析などの博識を駆使しながら、じつに「幾重にも変奏」する。
そのなかで、フランス語の起源が語られ、失語症に関するフロイトの知見が引用され、この「寓話」は啓示に充ちたさまざまなフレーズを醸成する。たとえば、
ある言語が別の言語に変化する時には、常にその残余がある。(第九章)
ある言語の中に、もうひとつの言語の影を見ることは常に可能だ。(第十一章)
hの文字は(…)言語の中にわたしたちの呼吸が残していった痕跡なのだ。(第五章)
アレクサンドリアのフィロンは論文「言語の混乱について」で、「混乱させる」行為は純粋に破壊するのでも単純に創造するのでもないと述べたという。それはむしろ、「元々あった様々な特質を破壊し(…)、独自で異なった物質を造り上げることである」。ヘラー=ローゼンはその後に、ダンテの言葉を引く。
人間の言葉は(…)バベルの混乱の後わたしたちの都合の良いように作り替えられたのであって、その混乱と原初の言語の忘却に他ならない。
発話する生き物である人間は、つねに忘れつづけ、変わることで、創造する動物でもあるようだ。目眩がするほど豊潤な知に彩られた言語哲学の宇宙がここにある。
ALL REVIEWSをフォローする