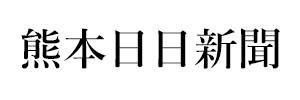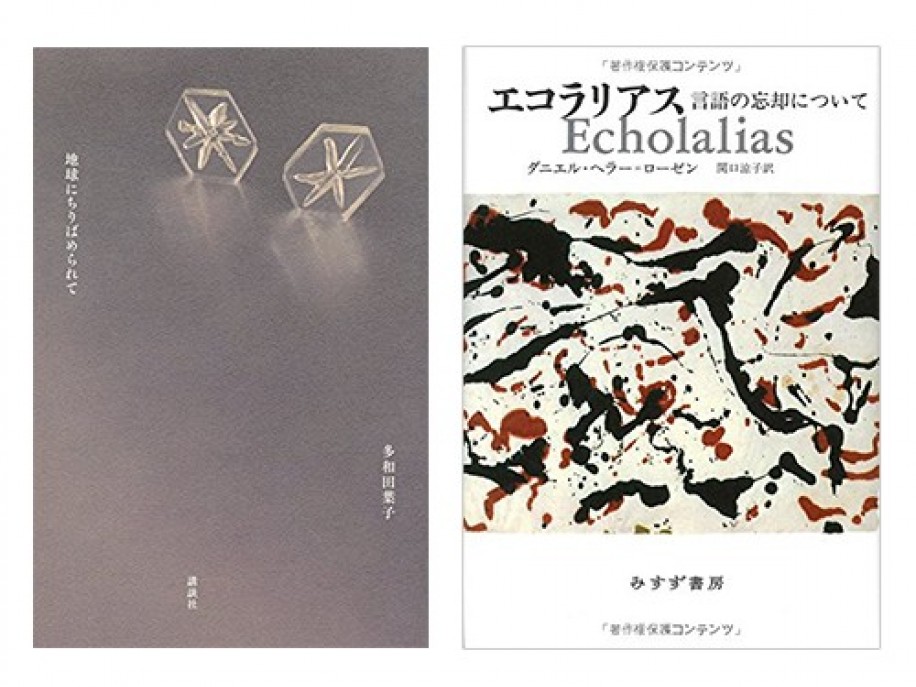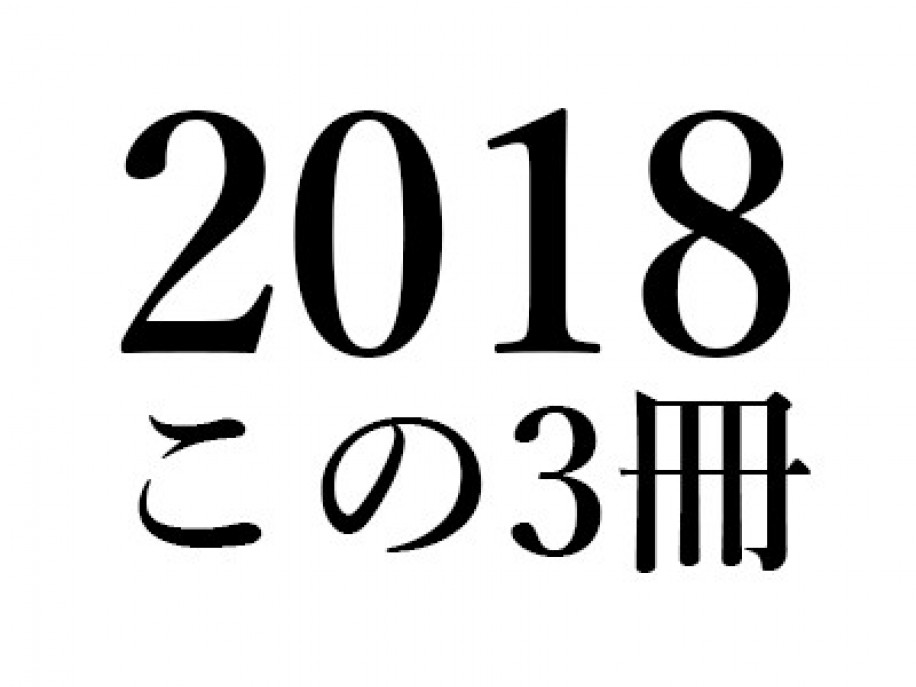書評
『エコラリアス』(みすず書房)
詩論として読める言語哲学
「エコラリアス」(Echolalilas)とは、「エコー(反響)」と「ラリア(話)」の複数形。本書では「谺(こだま)する言語」と訳されている。これだけでも魅力的なタイトルなのだが、副題に「言語の忘却について」とあると、詩を書いている人間にとっては(いや、表現者の誰にとっても)、ゾクゾクするほど魅力的なタイトルだ。言葉とはいったい何なのだろうか。言葉を手にする前の、言葉を知らなかった赤ん坊の時代にわたしたちが見た世界とは何だったのだろうか。
かつてボードレールはこんなことを言った。幼児体験の記憶を成人になっても豊富に持っている人間しか詩人になれない、と。確かにそうだ。半世紀以上、詩を書いてきた人間としてわたしもそう思う。しかし、幼児時代とは、言葉がまだ生まれていない時代のことではないか。それを記憶と呼べるだろうか?
「誰でも知っているように」と、著者は本書の第一章「喃語(なんご)の極み」の冒頭で語り始める。「子供は、初めのうちは言葉を話さない。幼児は雑音めいた音を発するが、それは人の言語の中に含まれている音を先取りしているようでいて、根本的に異なっている。聞き取れるような単語を発語しはじめる時点では、幼児は、語学の才に恵まれ数カ国語に通じた成人でもかなわないような発音能力を有している」
そしてここから、言語学者ロマン・ヤコブソンの観察が紹介される。「幼児が前言語段階から最初の単語を獲得するにいたる際、つまり本来の意味での言語的な第一段階で、様々な音を発する能力をほとんど失ってしまう」
驚くべきことだ。幼児がそれまで持っていた無限の発音能力が「忘却」されてはじめて、言語の習得がはじまる。わたしたちが「母語」と呼んでいるものに適応するまでに、言語以前の「音」を忘れてしまうのだ。
ほんとうにそうなのか? 著者は実に柔軟にこの疑問から話を進めている。忘れてしまった発音能力。それを示す幼児の「喃語」は、成人が話す言葉のなかに「谺」のように残っている。
第二章「感嘆詞」では、動物の鳴き声や機械や自然の発する音を真似(まね)たオノマトペ(擬音語、擬態語)が、谺する言語の一つであり、また、オオ!や、アア!という感嘆の叫びも、谺する言語だという。
「人間が最初に発した言葉の形態」が感嘆詞であり、それが生まれた瞬間から人間の言語は存在する。人間は異質な音を発することで、「外への呼びかけ」という言語の本来の役割を果たす。そして、そのときの言語は、「言語そのものを越えて」、「自らの前にありその後に続く、沈黙、非言語に自らを開く」。言語自身が「言語を越えて」、「沈黙」にも近づく。
本書が言語哲学の本であるにもかかわらず、優れた詩論としても読めるのは、このような指摘があるからだ。人間はそのとき、すでに幼児時代の発音能力を忘却しているのだが、その「記憶を思い出すことも完全に忘却することもできないまま」でいる。
まことに不思議な手触りをもたらす本である。哲学書でありながら、エッセー集としても読める手触り。死んでから天国に住む詩人たちが、かつて地上で書いた自らの詩を忘れている、というアラブの寓話(ぐうわ)(第二十章「詩人の楽園で」)などは、記憶と忘却が分かちがたいこと、そして忘却のなかに投げ出されたところから、わたしたちの言葉が始まるということをよく示している。詩人でもある関口涼子の翻訳は、著者の緻密な論理をまことにこなれた日本語に定着させている。わたしは本書をこれから何度もひもとくだろう。
ALL REVIEWSをフォローする