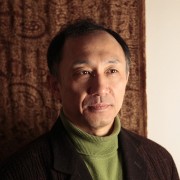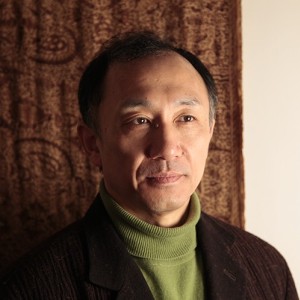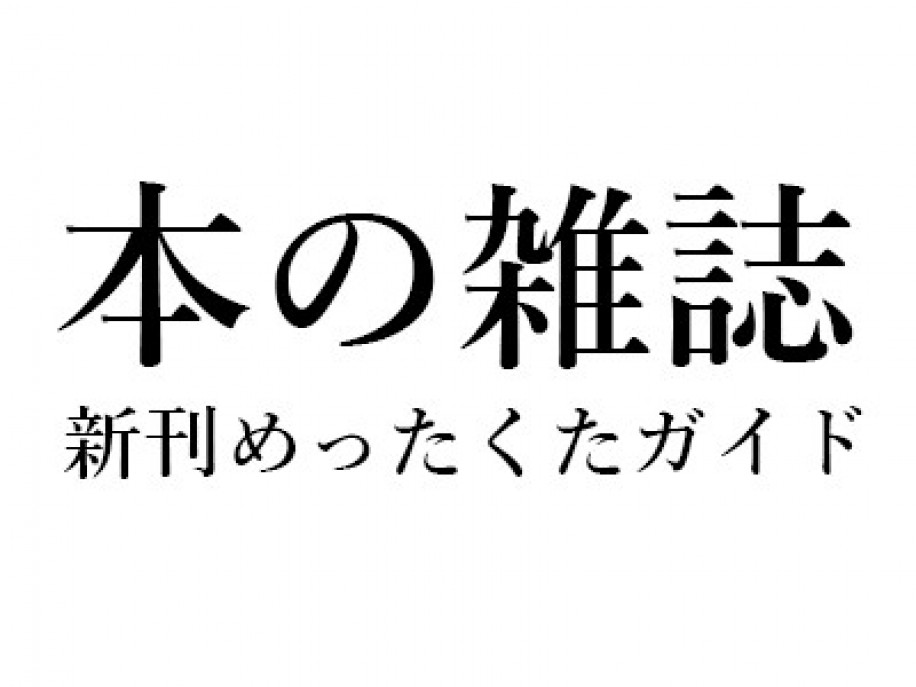書評
『日本の醜さについて 都市とエゴイズム』(幻冬舎)
「日本人論」であることに力点
タイトルにある「醜さ」とは街並み・景観のこと。ヨーロッパでは古びた建物をそのまま使い続け、必然的に建築物は街並みに溶け込んでいる。ビルひとつを新築するにも図面を当局に提出、街の建築委員会による外観(意匠)の審査にもパスしなければならない。それゆえ従来の街並みを損なう表現は現れにくい。それに対し日本では、周囲に配慮するようなビルは稀少(きしょう)。いずれもが他とは異なり、目立つことを競っている。ひとつひとつの建築物が美しくとも、集合としての「街並み」や「景観」についての共通理解はなきに等しい。街並みや景観を無視した現状が、本書の言う「醜さ」である。その意味では、松原隆一郎『失われた景観―戦後日本が築いたもの』(PHP新書、2002)およびアレックス・カー氏の『犬と鬼―知られざる日本の肖像』(講談社、02)以来の一連の著作に連なる、日本の景観に対する憂慮の書と言える。
ところが著者は述べる。「この誰が見てもあきらかな違いにもとづいて、日本人論を展開した人は、ひとりもいない」。資料の博捜で知られる著者だから、私たちの本を見落としたはずがない。とすれば本書は景観論でありながら、むしろ「日本人論」であることに力点がある。
続々と挙げられる現象は多様で、著者らしいユーモアを含む。本国のチェーン店には存在しない、フライドチキン店舗前のカーネル・サンダース像。岸に手摺(てす)りがほとんど設置されないベネチアの運河。対照的に安全重視から多数架けられた日本の歩道橋。狭い土地しか持たない地権者が気鋭の建築家に設計を依頼し、とんがった住宅が建った住宅街。爵位を持つ個人の所有でありホテルに転用されている英・独の城。城のイメージを再転用した日本のラブホテル(「目黒エンペラー」)。
また、鎌倉末期の頃の建物(パラッツォ・ベッキオ)の一部を今なお使い続けるフィレンツェ市役所。ローマにおける幾多の重要建築物を空襲から保護するため停戦を申し出た第二次大戦時のイタリア。対照的に、「精神さえすこやかであれば」「法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ」と戦時中に言ってのけた坂口安吾の「日本文化私観」。これらを通じて著者は、日本人の街並み・景観意識を考察する。
まず重視されるのが、地権者の権利だ。景観法や条例に違反さえしなければ、どんな奇抜な外観の家でも建てられる。また、幼児性。子どもを誘惑する魂胆が露骨な人形を路上に置くのは商店主の矜恃(きょうじ)の問題であろう。運河の手摺りや道路の歩道橋は、景観よりも安全重視を物語る。名建築も古くなると次々に壊すのは経済重視からで、家賃やテナント料目当て、相続税・固定資産税対策であろう。文士が歴史的建築を失っても構わぬとするのは、形あるものより精神を優先するからだ。
さらに著者は、こうした問題から目をそらせてきたのが社会科学者だったと言う。大塚久雄や丸山眞男は先の戦争で国家に搦(から)め捕られ抵抗しなかった日本人の主体性欠如を批判し、西欧型の近代化を唱えて戦後の論壇をリードした。日本人の集団主義は封建制の残滓(ざんし)ゆえで、個人主義こそ確立せよ、と。これに対して著者は、周囲を無視して好き勝手に建築する日本人はよほど個人主義的で、いまだ爵位を持つ人が存在し地権者の自由を制限する西欧は集団主義的だと指摘する。社会科学者には「建築は語るに値しない」という偏見が垣間見える。安吾のみならず戦後の左派も精神のみに注目したのだろう。景観論がえぐり出す日本の問題は、予想外に根が深い。
ALL REVIEWSをフォローする