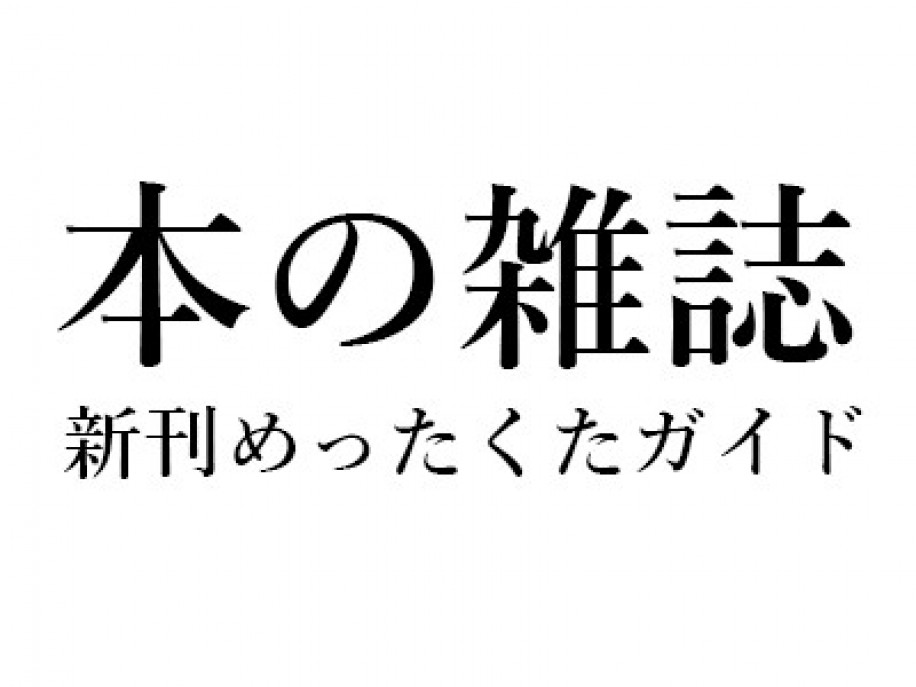書評
『美人論』(朝日新聞出版)
美人は悪と結論した明治以来の品定め
まさか今時、こういうテーマの本が刊行されるなんて、まずは著者の日頃の研鑽と勇気に拍手を送りたい(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1991年)。本を書いたり社会的発言をしたりする人の間では、他人の容貌についてとりわけ女性の容姿の良し悪しについて公然と口にするのはいけないことだとされている。活字もだめだし、テレビなんかだと致命傷になりかねない。しかしその一方“雨夜の品定め”は、男同士の間ではまるで衰える気配はない。
美人論というのは、本音と建前の落差が激しく、気軽に触れると火傷必至のテーマなのだが、こういう危ないテーマを前にすると著者はなぜか気力が湧いてくるタイプらしい。すでに実績もある。七年前のデビュー作『霊柩車の誕生』では、誰もが気にしながら誰も改めて考えたこともない霊柩車のあの特異な姿について語り、次作の『つくられた桂離宮神話』では日本美の至宝として世界に流通する桂離宮について“どこが美しいのか分からない”と告白した。世間や知識人の間に厳としてある権威や無意識のうちに疑わざるものとしてある常識に光を当て、その質と量を正確に計る、というのが著者の一貫した姿勢である。
この質と量を正確に計るという姿勢は美人論の場合も一貫していて、明治の文明開化から平成の現代まで近代百二十余年間に日本人が繰り広げた美人についての言説が、あの本この雑誌から採集されて次々と登場する。よくもまあ克明に集めたものだ。たとえば、
加藤弘之「美人は、往往、気驕り心緩みて、却つて、人間高尚の徳を失ふ……之れに反して、醜女には、従順・謙遜・勤勉等・種種の才徳生じ易き傾あり」(明治39年)
林真理子「フェミニズムの女性学者U・Cさんが、田中優子、猪口邦子と並んで、三大美形のアイドル女流学者って雑誌に書いてあったの(笑)。私、もう引っくり返っちゃって……あの人が美形の学者なら、私だって美貌の女流作家って言ってくれたっていいんじゃないの!? 一体基準はどこにあるわけよ」(平成元年)
こうした大量採集の言説から著者は、明治このかた手をかえ品をかえ、美人は表向き悪とされてきた、と結論する。ここまでが研究者としての著者の仕事で、この先が社会思想家・井上章一の真骨頂になる。
美人性悪説や女性を容姿で判断してはならないという常識に対し、いつものようにウッチャリをかける。おれは美人が好きだ、と。
井上章一は、これまでウッチャリで勝ってきた。相手の文化的権威が大きければ大きいほど、世間的常識が根深ければ根深いほど、技は見事に決まり、観客としてはヤンヤの喝采(かっさい)だった。
ところが今回、いつものように決まっていない。得意の二枚腰がくだけてしまったのか、美人と重なったまま体が開かず土俵下に落ちた。原因は美人体験不足と指摘されている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする