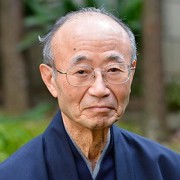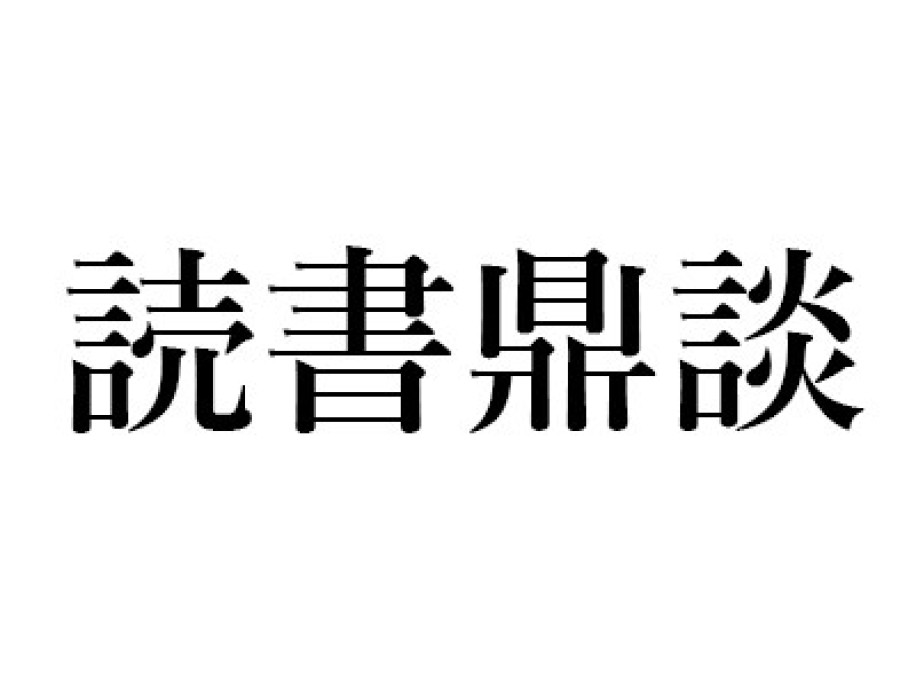書評
『世阿弥は天才である―能と出会うための一種の手引書』(草思社)
鋭い作品分析、人物像に迫る。
世阿弥を天才と称するのは誰にでもできるだろう。だが彼が天才であることを証明するのは、容易なことではない。ところが本書は、どうやらそれに成功したようだ。世阿弥という人間を時代背景の中に浮かびあがらせ、その能楽の特色を多層的に分析している手さばきが鮮やかである。歌舞、面、観客と急所を押さえて世阿弥のねらいをえぐりだしていく呼吸も間然するところがない。
だがそのことよりも何よりも本書は、そのあとに展開される作品論の一つ一つにおいて水をえた魚のような生気を蘇(よみがえ)らせる。謡曲における前場(前シテ)と後場(後シテ)の緊密な関係を、その歌舞的契機に視点を定めて掘り下げていく手法が一貫していて説得的である。また作品にたいする鋭い読みがおのずから世阿弥の人間を浮き彫りにする仕掛けになっているところも捨て難い。
たとえば彼の修羅能(敦盛、八島など)は平家物語の主題を自在に料理して作り変えているが、そこにみられる時間観念には近代人的な感覚が反映しているという。また本書の興趣は、世阿弥の作品の特質を長男の元雅や女婿の禅竹の作品と比較しながら明らかにしている点ではないだろうか。たとえば世阿弥の夢幻能を元雅の「弱法師」と比べ、元雅の曲では信仰の問題が重く扱われているのにたいし、父の方は信仰を気楽に利用し、気楽にそれによる救済を描いているといっている。
さらに世阿弥(井筒)と禅竹(定家)を比べ、世阿弥は男の理想としての女を美しく描いたが、禅竹の女はそのものずばりの現実の女であるといって、両者の対照をきわ立たせるといった工合である。
作者は三歳のときからクラシックバレエを習い、やがて仕舞を稽古(けいこ)するようになって二十年を超えるのだという。その身体の体験がいま世阿弥の言語世界と幸運な出会いをはたし、気持ちのよい共鳴現象をひきおこしている。出色の世阿弥論といっていいだろう。
ALL REVIEWSをフォローする