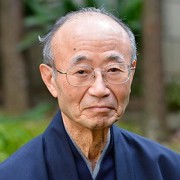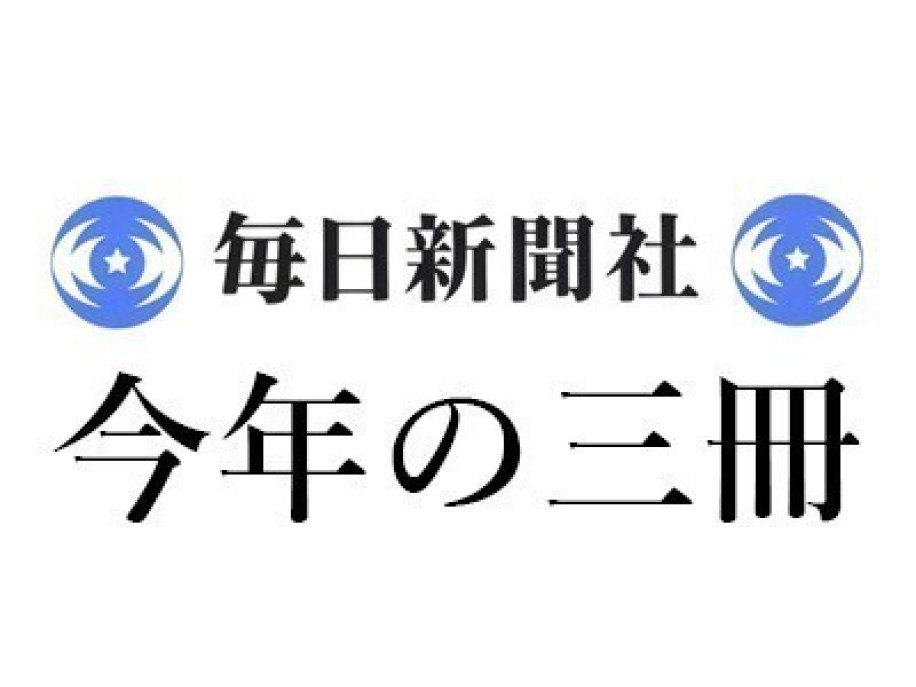書評
『王の身体 王の肖像』(筑摩書房)
「歴史図像学」熱っぽく展開
魅力的なタイトルである。「王」の身体への凝視を通してその精神的なあり方に迫る。「王」の肖像を鏡として、その権威の象徴性を解剖するのだという。そのための素材が、絵巻や肖像画などの絵画史料である。まず、主題からいこう。ここでいう「王」には天皇と将軍が含まれている。京都の天皇と関東の将軍だ。日本の歴史における二重王権の問題であるが、それが絵画史料ではどのように表現されているのか。歴史学の領域ではカンカンガクガクの蓄積がのこされているが、それが図像ではどうなっているのかということだ。
その一つ、中世の文献によると、日食・月食がおこると天皇と将軍の御所がムシロで覆われることになっていた。それは何故か。著者は絵巻の中から裹頭(かとう)や覆面の人間をすくいあげ、それが穢(けが)れの拡散を防ぐ身体作法であったとのべて、王権と触穢(しょくえ)の関係に説き及んでいる。その二つ、よく知られた後醍醐天皇の肖像画をとりあげ、そこに表されている神仏混交の異形性の意味を問うている。これにはすでに網野善彦の仕事があるが、その欠を補い新しい視点を展開しようとしている。
つぎに、方法はどうか。絵巻や肖像画などの図像には美術と歴史の二面が含まれている。著者は歴史学者であるから、その素材を絵画史料という面から料理している。絵の世界を文献とつき合わせてその制作年代を割りだし、制作者や依頼者の実名をあぶりだそうというわけだ。それだけではない。そこには歴史図像学のための方法原論が、熱っぽく華々しく打ちあげられてもいる。
とすればその方法は、主題をどのようにえぐりだしているのか。著者はたしかに足場をしっかり固めて、太刀をふりあげている。しかしその切っ先を対象にむけてふりおろすためには、あまりにも歴史の側に身を寄せ、慎重な身構えに終始している観がある。「王」の身体内部の骨にまで切りこむ試みを、今後に期待せずにはいられないのである。
ALL REVIEWSをフォローする