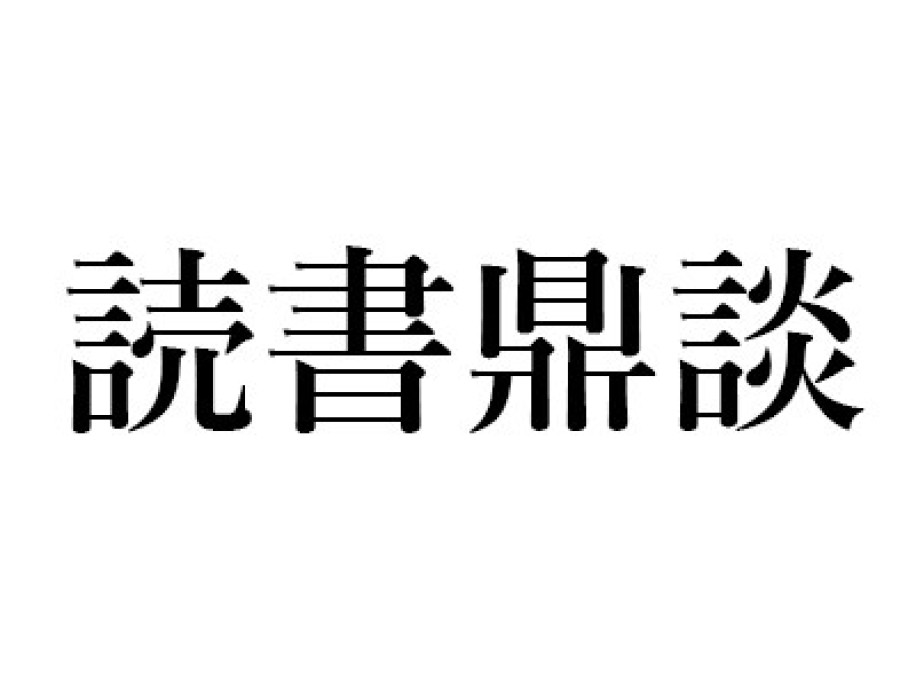書評
『風姿花伝』(岩波書店)
夭折という言葉は、まだ残っているのだろうか。わたしは知らない。もう長いこと、この言葉に出会っていないからだ。
かつては夥しい夭折者が存在していた。征夷大将軍として雄大な和歌を詠みながらも、わずか27歳で暗殺された源実朝。抒情と含羞の合間で壮絶な人生を生きた中原中也。時代劇映画に新しい風をもたらしたと話題を呼びながら、中国戦線で病死した山中貞雄。戦後の混乱のなか早熟な詩を書き続け、わずか17歳で自殺をした長沢延子……。数えあげてゆけば、夭折者のリストはかぎりなく続くことだろう。それははかなげにして、無念さの遺るリストである。
結核と政治的動乱が夭折者を作り出した。ジャズとロックンロールの世界では、それにドラッグを加えるべきかもしれない。ペニシリンが発明され、戦争に由来する混乱が一段落すると、夭折者は急速に少なくなってきた。しばらく前まではエイズによる芸術家の受難が新聞を賑わせたこともあったが、それもいっこうに話題にならなくなってしまった。
要するに、夭折は時代遅れのものとなってしまったのである。若く死んだからといって、書いた詩や小説がヴィンテージものとなる時代は、とうに昔のことになってしまった。
「人生は短いが芸術は長い」という格言は、今では逆さまになってしまった。次々とすべてのものが商品として消費されてしまう現在の社会では、芸術の寿命は驚くほどに短いのだ。それに比べて、人生は退屈なまでに長いときている。
ある必要があって、世阿弥の『風姿花伝』を読み直すことがあった。14世紀から15世紀への転換期にこの天才的演劇人によって執筆され、長い間、秘中の秘の巻物とされてきたこの書物には、教えられるところが大きい。たとえば彼は、12や13の子供がみごとに能を舞ったとしても、それを本当の「花」、つまり芸術的達成とは見なさない。それはどこまでも「時分の花」、若さがゆえに華やいでみえるだけのことにすぎないと、退けてしまう。能役者としての真実の花が開くのは、さらに修行と研鑽を積み、34、5になってからのことだと説く。夭折の美学などありえないという立場である。
では、年老いてしまった者には「花」はありえないのだろうか。世阿弥はひとまず「麟麟も老いては駑馬に劣る」という俗言を引いたあとで、しかしながら本当に才能のある役者であるならば、すべての華麗さや派手さが喪われてしまったあとにでも「花」が残るものであると説いている。その証拠に、自分の父親は52歳で、死の2週間ほど前であるが、みごとな舞を披露したと聞いている。細かなことは若い者に任せておいて、自分の力でできる程度の簡単なことを、ほんのわずかでかまわないから演じてみるだけでいいのだ。その方が「花」は、以前に増して優れたものに見えるだろうと、世阿弥はいっている。けだし長い経験から来る実感なのだろう。
夭折者への思い出に耽るのはいい。だが、すべてが脱落してしまった後に遺る「花」の達成にこそ、われわれは心を配るべきではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
かつては夥しい夭折者が存在していた。征夷大将軍として雄大な和歌を詠みながらも、わずか27歳で暗殺された源実朝。抒情と含羞の合間で壮絶な人生を生きた中原中也。時代劇映画に新しい風をもたらしたと話題を呼びながら、中国戦線で病死した山中貞雄。戦後の混乱のなか早熟な詩を書き続け、わずか17歳で自殺をした長沢延子……。数えあげてゆけば、夭折者のリストはかぎりなく続くことだろう。それははかなげにして、無念さの遺るリストである。
結核と政治的動乱が夭折者を作り出した。ジャズとロックンロールの世界では、それにドラッグを加えるべきかもしれない。ペニシリンが発明され、戦争に由来する混乱が一段落すると、夭折者は急速に少なくなってきた。しばらく前まではエイズによる芸術家の受難が新聞を賑わせたこともあったが、それもいっこうに話題にならなくなってしまった。
要するに、夭折は時代遅れのものとなってしまったのである。若く死んだからといって、書いた詩や小説がヴィンテージものとなる時代は、とうに昔のことになってしまった。
「人生は短いが芸術は長い」という格言は、今では逆さまになってしまった。次々とすべてのものが商品として消費されてしまう現在の社会では、芸術の寿命は驚くほどに短いのだ。それに比べて、人生は退屈なまでに長いときている。
ある必要があって、世阿弥の『風姿花伝』を読み直すことがあった。14世紀から15世紀への転換期にこの天才的演劇人によって執筆され、長い間、秘中の秘の巻物とされてきたこの書物には、教えられるところが大きい。たとえば彼は、12や13の子供がみごとに能を舞ったとしても、それを本当の「花」、つまり芸術的達成とは見なさない。それはどこまでも「時分の花」、若さがゆえに華やいでみえるだけのことにすぎないと、退けてしまう。能役者としての真実の花が開くのは、さらに修行と研鑽を積み、34、5になってからのことだと説く。夭折の美学などありえないという立場である。
では、年老いてしまった者には「花」はありえないのだろうか。世阿弥はひとまず「麟麟も老いては駑馬に劣る」という俗言を引いたあとで、しかしながら本当に才能のある役者であるならば、すべての華麗さや派手さが喪われてしまったあとにでも「花」が残るものであると説いている。その証拠に、自分の父親は52歳で、死の2週間ほど前であるが、みごとな舞を披露したと聞いている。細かなことは若い者に任せておいて、自分の力でできる程度の簡単なことを、ほんのわずかでかまわないから演じてみるだけでいいのだ。その方が「花」は、以前に増して優れたものに見えるだろうと、世阿弥はいっている。けだし長い経験から来る実感なのだろう。
夭折者への思い出に耽るのはいい。だが、すべてが脱落してしまった後に遺る「花」の達成にこそ、われわれは心を配るべきではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする