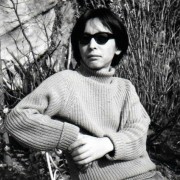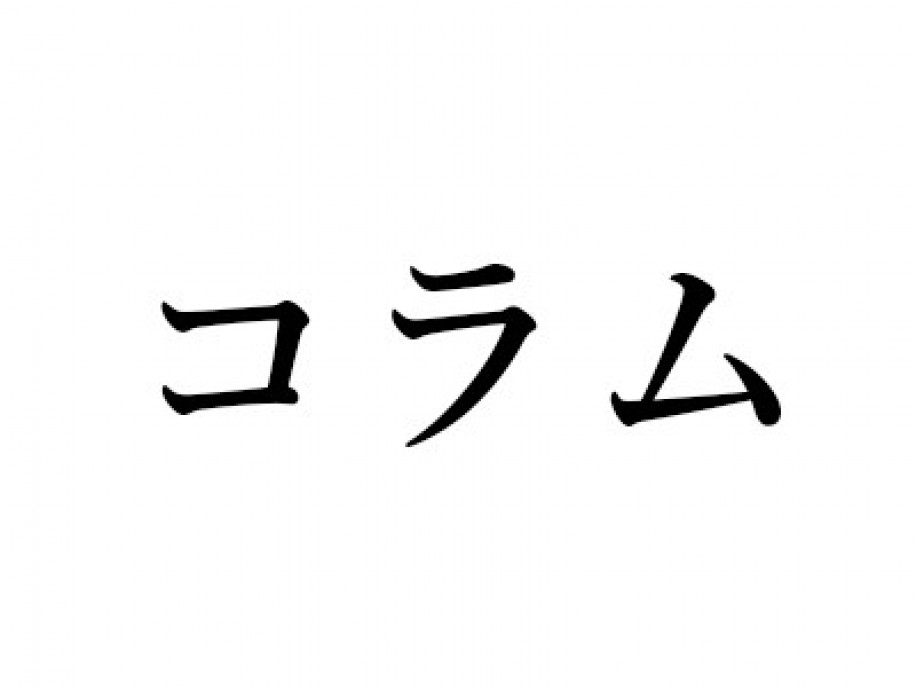書評
『瘋癲老人日記』(中央公論新社)
食事とか、薬とか、病気とかいうものは、もともと極端に抽象的なものであって、さればこそ、それだけの材料から小説を組み立てるということは、なまなかの人間にはとても考えられない異常事であるにちがいない。どんなに薬の名前を具体的かつ詳細に列挙したところで、この抽象性が具体性に変化するわけのものではない。まさに、これがこの小説の第一の不思議というべきである。
第二の不思議は、日記という形式である。『鍵』以来谷崎氏が自家薬籠中のものにした日記という形式は、これまた、具体的な日常性の連鎖を抽象的な構図に変化させる驚くべき効能をもっている。日記が抽象的だという理窟は、一見、奇異の念を抱かせるかもしれないが、しかし、一人称小説である『卍』が、あれほどの細々とした風俗描写から一つの見事な抽象的構図を浮かび上らせた事情と、これはよく似ている。つまり、一人称も日記も、ある全体性への邪悪なマニアックな志向を容れる器であったのであり、それが奇妙にも、抽象化のモメントになっているのであった。
要するにトランプの遊びで、マイナスの札を全部集めてプラスに変えるような邪悪な操作が、この作品の基調になっていて、そこが私には、この作家の資性に完全に合致した、すぐれて独自な点だと思われる。
描写のなかのトリヴィアルなものは、決して主題との関連において選択されているのではなくて、少なくともこの作家の関心に映じたトリヴィアルなものは、細大洩らさず、ぜんぶ洗いざらい羅列されていると言ってよく、また、あくまで具体性に執着した完全な羅列であるからこそ、世界が一変して、抽象的になるのである。むろん、この作家のマニアックな関心以外のものは、ぜんぶ思い切って切り捨てるという手段がとられている。
さて、そこにエロティシズムが結びつく宿命は、必然的すぎるほど必然的である。エロティックな関心が先か後かの問題ではない。いったい、食事よりも、薬よりも、病気よりも、もっと抽象的なものがエロティシズムにほかならないからだ。谷崎氏が一人称とか日記とかいう器を使ったように、ラクロやサドは書簡体とか年代記とかいうフラスコを使った。エロティシズムを扱う物理学者のマニアックな手は、洋の東西を問わず、どこでも似たような器を選ぶものだ。
ところが、このような谷崎氏の最近の傾向を、老人性退歩ないしは衰弱の現象とみる論者もある。しかし、人間の成長には必らず魂のドラマがつきまとわねばならないものであろうか。自然主義からアクチュアリティ説にいたる、日本文学を蝕んだ抜きがたい謬見を、この作品ほど徹底的に愚弄しているものはない。
小説の冒頭の部分、芝居の帰り、伊勢丹の特選売場から銀座の浜作にいたる瘋癲老人のプロムナードに、それと平行して、全学連だのデモだのいう話題がひょこひょこ飛び出してくるあたり、(作者はおそらく無意識であろうが)絶妙の面白さがある。
もう一つ、中期以後の谷崎氏の作品に、モラルとの対決あるいはメタフィジックが徐々に欠落して行ったという非難がある。しかし、さきほど私が述べたごとく、トランプのマイナスをぜんぶ集めてプラスに変えるという、ある邪悪な全体性への志向が、中期以後の谷崎氏の心に芽ばえてきて、それが具体的なトリヴィアルなものへの執着と一つになり、この最近の作品でもまた、作品全体を一つの形而上学に転換するはたらきを示していることに注目すべきであろう。
思うに、戦争中の『卍』から戦後の『鍵』を経て『瘋癲老人』にいたる過程は、たしかに一部の論者の指摘するごとく、欠落の過程でもあり、衰弱の過程でもあったであろう。だが、欠落によって、衰弱によって本物になる作家もあるものだ。
薬の名前の羅列など、ある意味でまさに衰弱の証拠でもあろうが、この作家の具体性と抽象性に対する奇怪な関心のあり方を、これほどはっきり暴き出して見せてくれるものはなく、その意味で『瘋癲老人』こそ、谷崎氏の到達した窮極の世界だと言えば言えないこともないのである。
衰弱によって本物になる、と私は書いたが、早い話が、『群像』の合評会で、この小説に直接ふれて、「メタフィジックスが足りないね」などと言っている花田清輝氏御当人にしたところで、初期の『復興期の精神』あたりのキラキラしたメタフィジックスが、年月とともに白粉のようにどんどん剥げ落ちて、ついに『鳥獣戯話』のあまりに平俗な、あまりに野卑な処世訓に到達することによって、ようやく本物の、何やら凄味をおびた、破戒無慙な花田清輝の素顔があらわれてきたのではなかったか。
【この書評が収録されている書籍】
第二の不思議は、日記という形式である。『鍵』以来谷崎氏が自家薬籠中のものにした日記という形式は、これまた、具体的な日常性の連鎖を抽象的な構図に変化させる驚くべき効能をもっている。日記が抽象的だという理窟は、一見、奇異の念を抱かせるかもしれないが、しかし、一人称小説である『卍』が、あれほどの細々とした風俗描写から一つの見事な抽象的構図を浮かび上らせた事情と、これはよく似ている。つまり、一人称も日記も、ある全体性への邪悪なマニアックな志向を容れる器であったのであり、それが奇妙にも、抽象化のモメントになっているのであった。
要するにトランプの遊びで、マイナスの札を全部集めてプラスに変えるような邪悪な操作が、この作品の基調になっていて、そこが私には、この作家の資性に完全に合致した、すぐれて独自な点だと思われる。
描写のなかのトリヴィアルなものは、決して主題との関連において選択されているのではなくて、少なくともこの作家の関心に映じたトリヴィアルなものは、細大洩らさず、ぜんぶ洗いざらい羅列されていると言ってよく、また、あくまで具体性に執着した完全な羅列であるからこそ、世界が一変して、抽象的になるのである。むろん、この作家のマニアックな関心以外のものは、ぜんぶ思い切って切り捨てるという手段がとられている。
さて、そこにエロティシズムが結びつく宿命は、必然的すぎるほど必然的である。エロティックな関心が先か後かの問題ではない。いったい、食事よりも、薬よりも、病気よりも、もっと抽象的なものがエロティシズムにほかならないからだ。谷崎氏が一人称とか日記とかいう器を使ったように、ラクロやサドは書簡体とか年代記とかいうフラスコを使った。エロティシズムを扱う物理学者のマニアックな手は、洋の東西を問わず、どこでも似たような器を選ぶものだ。
ところが、このような谷崎氏の最近の傾向を、老人性退歩ないしは衰弱の現象とみる論者もある。しかし、人間の成長には必らず魂のドラマがつきまとわねばならないものであろうか。自然主義からアクチュアリティ説にいたる、日本文学を蝕んだ抜きがたい謬見を、この作品ほど徹底的に愚弄しているものはない。
小説の冒頭の部分、芝居の帰り、伊勢丹の特選売場から銀座の浜作にいたる瘋癲老人のプロムナードに、それと平行して、全学連だのデモだのいう話題がひょこひょこ飛び出してくるあたり、(作者はおそらく無意識であろうが)絶妙の面白さがある。
もう一つ、中期以後の谷崎氏の作品に、モラルとの対決あるいはメタフィジックが徐々に欠落して行ったという非難がある。しかし、さきほど私が述べたごとく、トランプのマイナスをぜんぶ集めてプラスに変えるという、ある邪悪な全体性への志向が、中期以後の谷崎氏の心に芽ばえてきて、それが具体的なトリヴィアルなものへの執着と一つになり、この最近の作品でもまた、作品全体を一つの形而上学に転換するはたらきを示していることに注目すべきであろう。
思うに、戦争中の『卍』から戦後の『鍵』を経て『瘋癲老人』にいたる過程は、たしかに一部の論者の指摘するごとく、欠落の過程でもあり、衰弱の過程でもあったであろう。だが、欠落によって、衰弱によって本物になる作家もあるものだ。
薬の名前の羅列など、ある意味でまさに衰弱の証拠でもあろうが、この作家の具体性と抽象性に対する奇怪な関心のあり方を、これほどはっきり暴き出して見せてくれるものはなく、その意味で『瘋癲老人』こそ、谷崎氏の到達した窮極の世界だと言えば言えないこともないのである。
衰弱によって本物になる、と私は書いたが、早い話が、『群像』の合評会で、この小説に直接ふれて、「メタフィジックスが足りないね」などと言っている花田清輝氏御当人にしたところで、初期の『復興期の精神』あたりのキラキラしたメタフィジックスが、年月とともに白粉のようにどんどん剥げ落ちて、ついに『鳥獣戯話』のあまりに平俗な、あまりに野卑な処世訓に到達することによって、ようやく本物の、何やら凄味をおびた、破戒無慙な花田清輝の素顔があらわれてきたのではなかったか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする