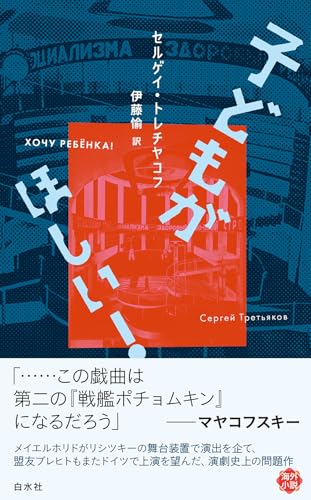書評
『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房)
すべては想像から始まる
現代アラブ文学を専門とする著者による、パレスチナ問題をめぐるエッセー集である。封鎖が長く続き悲惨な状況に陥っている現代のガザのことを考えただけでも、明るい内容になるわけがないが、それでも希望に貫ぬかれているところが心を打つ。本書は、私たちが普通「文学」と考えるものについて論ずる部分は少ないが、未来を切り開く想像力の営みこそが文学だということを教えてくれる。特に際立っている著者の姿勢は、ともかく現場に足を運んで、自分で見聞し、現地の人々と直接話をすること。分厚い辞書をひきながら机に向かって静かに本を読む、といった研究者の姿からはほど遠い。本書はある意味では、エジプト留学時代から数えて三〇年以上になる著者のパレスチナ探訪の経験を通じての自伝でもあり、その自伝がそのまま激動と惨禍に彩られた現代パレスチナの歴史にもなっている。本書のあちこちに、「二〇〇四年八月、私はヨルダンの首都、アンマンにいた。」「一九九〇年十二月の暮れ、私はジブラルタル海峡にいた。」「二〇〇二年九月、レバノン南部にあるラシーディーエ難民キャンプ。」「(二〇一四年)三月、私は完全封鎖下のガザに入った。」といった言葉が、目印(ランドマーク)のようにちりばめられているのだ。
記述は必ずしも時間順でもなければ、関係する国際情勢が詳しく解説されているわけでもないので、時代背景や現地の地理にうとい私のような読者には、正直なところ、分かりやすいとは言えない。しかし、それだけに個人史のあちこちの記憶の層から、難民の痛ましい経験の数々が、掘り起こされ、波状攻撃のように押し寄せてくるという印象を受ける。この現実の中で「文学は何の役に立つのか」という昔から繰り返されてきた疑念は、もう頭をもたげない。著者はいま大事なのは文学よりはジャーナリズム、しかしそれは「情報に還元されない文学的強度をもった」「緊急のエクリチュール」なのだと信じ、それを実践している。
本書で浮かび上がってくるのは、イスラエル建国とともに七十五万もの住民が難民となった一九四八年の「ナクバ」(大災厄)以来、最近のガザに至るまで、パレスチナ人が家を追われ、時に大量虐殺され、所属する国家を持たないがゆえに一切の権利を剥奪され、人間としての尊厳と希望を奪われていく過程である。しかし著者は、系統的な歴史記述を目指すわけではない。あちこちの難民キャンプで出会った人々、アーティストや活動家たちとの個人的な出会いを大事にしながら、人々がそこで何を考え、いかに絶望し、そしてそれにもかかわらず希望をもって生き続けられるとすればそれはどうしてなのか、を伝えてくれる。このように世界のマスコミがきちんと報道しない場所に入っていき、催涙ガスを浴びる経験までしながら、人間として現地の人々と触れ合う人がいなかったら、私たちはどうして世界を本当に知ることができるだろうか。
本書は、ガザのアーティストが制作した、「ガザの地下鉄」という想像上の地下鉄路線図で結ばれる。なんと美しいイメージだろうか。完全封鎖され、食料や医薬品や電気・水にも事欠き、移動の自由が奪われているガザの現実にとって、それは途方もない夢物語だ。しかし、著者は、すべては想像することから始まる、と力強く言う。私も同じように、いやもっと実現しがたいことを夢見たい。イスラエルとガザの人々が抱き合い、愛し合う日が来ることを。
ALL REVIEWSをフォローする