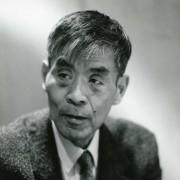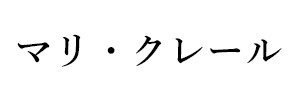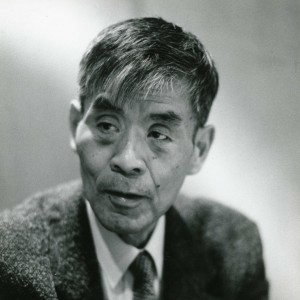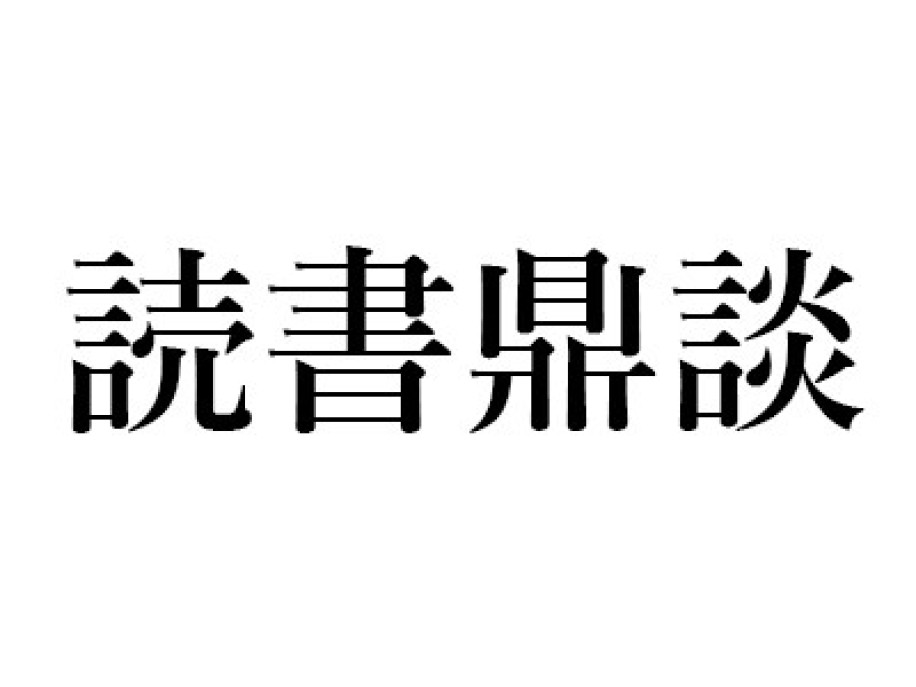書評
『ジェンダー 女と男の世界』(岩波書店)
この本を解くキイ・ワードは、題名にもなっている〈ジェンダー〉という言葉だ。イリイチはこの言葉に、過剰な概念やら微妙な思い入れやら、思想的な強調やらを、いっぱい詰めこんでいるので、なかなか汲みつくせない含みをもっている。わかりやすくたとえてしまうと、むかし親たちが、こんなときもっと男手があったらとか、女手があったらとかとよく言っていた、あの〈男手〉とか〈女手〉とか分けたときの、男と女の区別がジェンダーという概念にあたっている。こんなときの男と女の区別は、手にする道具のちがいにも関連するし、日常の生活の風習や、共同体のしきたりにも結びついている。かならずしも性(セックス)、性行動というふうに収斂してゆく男女の区別にはならない。ジェンダー、つまり男手とか女手とかいうように、包摂的であった男女の区別や役割のあり方が、性(セックス)とか性行動という縮こまった概念に変ってしまったのは、産業社会(近代資本主義と近代社会主義)以後になってからだ。それ以前の社会では、性(セックス)や性行動よりもはるかに豊饒なひろい概念で、男女の区別や役割は生きいきと存在していた。これがこの本を流れるイリイチの思想だといってよい。
イリイチによれば、産業社会はジェンダーという概念を性(セックス)という概念にまで貧弱にしてしまうことで、いくつか根本的な欠陥をさらけだした。ひとつは経済人間(ホモエコノミクス)としてみるかぎり、男も女も中性者に変わってしまった。経済社会のなかにいるときは男性も女性も、ひとしく性の区別のない人間として評価されるし、またそう振舞うほかはない。しかもそれなのに実際には、女性は近代産業社会になって賃金、社会的な待遇、仕事などで、いつでも男性の下位におかれて、かつて一度も平等が実現しなかった。収入をとってみれば、女性はこの一世紀、男性の五〇~六〇パーセントを超えたことはない。イリイチによれば、ジェンダーという男女の区別を失って、性(セックス)という区別に追いやられたあげく、産業社会は、賃金労働とシャドウ・ワーク(家事労働など収入にならない仕事)に分割され、賃金労働は性(セックス)としての男性の仕事になり、シャドウ・ワークは性(セックス)としての女性の仕事になるという傾向に向った。そこで両性の仕事はいずれも地獄に陥こんでいった。
こういったいくつかの根本的な弱点や欠陥をもつ産業社会は、さまざまなところで行きづまりを、露呈しはじめている。たとえば教育制度が発達すればするほど、若者たちから自発性や創意や活力が喪われてゆき、医療設備が発達すればするほど、新たに病気が作られて人間は病弱になってゆき、交通が発達すればするほど、混乱も増加して、ますます場所の移動がわずらわしく難かしくなる傾向が増大してゆき、どこかに限界があるとおもわれる姿が、露わになってゆく一方である。その徴候は現在誰の眼にもはっきりするまでになりつつある。産業社会がどこまでも発達すれば、人間生活の福祉がますます増加してゆくわけではないことが、はっきりしてきた。この状態は、もとをただせば、産業社会以前にあったヴァナキュラーなジェンダーが失われたためである。いいかえれば地域、共同体、家族などに結びついて、それぞれに固有な男手と女手の役割や相互に補完しあう関係が失われて、性(セックス)の体制としての男女というところに追いこまれてきた産業社会のあり方に問題があったからである。
イリイチは、性(セックス)、性行動としての男女というところまで追いつめられ、性差別や、性格差を増大させ、しかも経済的には男も女も性的な中性者に均等されてゆくような現在の状態のなかから、ジェンダーの姿を解きはなすように現わしてゆくことが重要だと説いている。
イリイチが、資本主義体制であれ、社会主義体制であれ、人間が産業主義を採用するかぎり、その限界と危機は明らかであると考えているところには、おおきな刺激を与えられる。また男だとか女だとかは問題ではなく、労働時間だけが問題なのだという経済的中性人の考え方に慣れきったわたしたちの思考にたいして、イリイチがジェンダーの復権を説く姿には、予言者的な衝動を与えられる。わたしたちが対幻想という考えの復権を考えてきたこととも重なる部分があるようにおもえた。敢えて批判がましいことを云わせてもらえば、イリイチの現代産業主義社会にたいする批判は、どこか根底のところで歴史の不可避性の核をよけて通っていて、その分だけが牧歌的な言説になっている気がする。この本の訳文は文脈が活性化された、とても見事なものだった。
【この書評が収録されている書籍】
イリイチによれば、産業社会はジェンダーという概念を性(セックス)という概念にまで貧弱にしてしまうことで、いくつか根本的な欠陥をさらけだした。ひとつは経済人間(ホモエコノミクス)としてみるかぎり、男も女も中性者に変わってしまった。経済社会のなかにいるときは男性も女性も、ひとしく性の区別のない人間として評価されるし、またそう振舞うほかはない。しかもそれなのに実際には、女性は近代産業社会になって賃金、社会的な待遇、仕事などで、いつでも男性の下位におかれて、かつて一度も平等が実現しなかった。収入をとってみれば、女性はこの一世紀、男性の五〇~六〇パーセントを超えたことはない。イリイチによれば、ジェンダーという男女の区別を失って、性(セックス)という区別に追いやられたあげく、産業社会は、賃金労働とシャドウ・ワーク(家事労働など収入にならない仕事)に分割され、賃金労働は性(セックス)としての男性の仕事になり、シャドウ・ワークは性(セックス)としての女性の仕事になるという傾向に向った。そこで両性の仕事はいずれも地獄に陥こんでいった。
こういったいくつかの根本的な弱点や欠陥をもつ産業社会は、さまざまなところで行きづまりを、露呈しはじめている。たとえば教育制度が発達すればするほど、若者たちから自発性や創意や活力が喪われてゆき、医療設備が発達すればするほど、新たに病気が作られて人間は病弱になってゆき、交通が発達すればするほど、混乱も増加して、ますます場所の移動がわずらわしく難かしくなる傾向が増大してゆき、どこかに限界があるとおもわれる姿が、露わになってゆく一方である。その徴候は現在誰の眼にもはっきりするまでになりつつある。産業社会がどこまでも発達すれば、人間生活の福祉がますます増加してゆくわけではないことが、はっきりしてきた。この状態は、もとをただせば、産業社会以前にあったヴァナキュラーなジェンダーが失われたためである。いいかえれば地域、共同体、家族などに結びついて、それぞれに固有な男手と女手の役割や相互に補完しあう関係が失われて、性(セックス)の体制としての男女というところに追いこまれてきた産業社会のあり方に問題があったからである。
イリイチは、性(セックス)、性行動としての男女というところまで追いつめられ、性差別や、性格差を増大させ、しかも経済的には男も女も性的な中性者に均等されてゆくような現在の状態のなかから、ジェンダーの姿を解きはなすように現わしてゆくことが重要だと説いている。
イリイチが、資本主義体制であれ、社会主義体制であれ、人間が産業主義を採用するかぎり、その限界と危機は明らかであると考えているところには、おおきな刺激を与えられる。また男だとか女だとかは問題ではなく、労働時間だけが問題なのだという経済的中性人の考え方に慣れきったわたしたちの思考にたいして、イリイチがジェンダーの復権を説く姿には、予言者的な衝動を与えられる。わたしたちが対幻想という考えの復権を考えてきたこととも重なる部分があるようにおもえた。敢えて批判がましいことを云わせてもらえば、イリイチの現代産業主義社会にたいする批判は、どこか根底のところで歴史の不可避性の核をよけて通っていて、その分だけが牧歌的な言説になっている気がする。この本の訳文は文脈が活性化された、とても見事なものだった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする