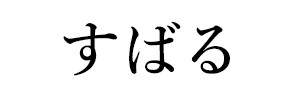書評
『探偵小説あるいはモデルニテ』(法政大学出版局)
私立探偵オイディプスの影
二十世紀におけるすべての偉大な小説は探偵小説だというあのボルヘスの言葉をまつまでもなく、優れた文学作品と探偵小説には、主題と形式において、また形式の模索が主題に返されるメタレベルの構造において、あきらかな類縁関係が見られる。伝統的な物語の型を崩しつつ、あらたな定型を創り出すために「語る行為」の恣意性を最大限に活用する遊戯精神と修辞的な追求。しかも探偵が最終的に行き着くのは、いずれも近代小説の根幹に据えられた過剰なる自意識の、つまりはアイデンティティの危機という問題なのである。犯人は誰かと問うことは、他者とは、「私」とは誰なのかと問うに等しいのだ。ジャック・デュボアの『探偵小説あるいはモデルニテ』は、今世紀の先端的な文学に無視できない影響を及ぼしている探偵小説の特色を、その生成期にあたる、自由主義的資本主義が到来した十九世紀なかばにさかのぼって、ボードレールの言う「近代的なるもの」との関わりから説き起こした手堅く刺激的な一書である。社会の変動と文芸の歴史が交錯したこの時代に隆盛をむかえた新聞小説やユゴー風の社会史的叙事詩、ゴンクール兄弟が開拓した芸術小説、そしてとりわけ写真をはじめとする多様なジャンルと競合しながら「めぐりあわせの圧制」を享受してきた表現の磁場こそが探偵小説なのであり、そこにはつかのまの生を謳歌し、はかなさの神話から個の魅力を引き出していく『悪の華』の詩人の思想と時代の力学が残されている。
探偵と犯人、探偵と容疑者、あるいは犯人とその犠牲者は、大都市にうごめく、たがいに必然的な結びつきなどありはしない群衆のなかでその場かぎりの関係をとりむすぶ。いっさいの権力と無縁の散策者=フラヌールたる探偵は、一見したところ意味のなさそうな細部を「手がかり」として、謎を地道に解読する記号学者となり、熱き英雄ではなく醒めた観察者の相貌を獲得する。真実を求めて容疑者や犯人に自己同一化し、ついにはみずからの存在理由を疑うにいたって、彼はすべての役割をひとりで背負わされたオイディプスの神話をなぞりはじめるのだ。犯人と探偵が同一人物であるかもしれないという差し迫った謎に父親殺しの変奏を読み、ルルー、シムノン、ジャプリゾの小説を通して立証する第III部がその意味でもっとも生彩に富んでいる。
ただし、探偵小説に植えつけられた中間領域の宿命を「モデルニテ」の概念に連結し、いわば学術的に神話化しようとする行為の自己矛盾にたいして、著者はさほど意識的であるように見えない。文芸社会学的な視線でつづられた箇所よりも、具体的な作品に即した分析を実践する末尾の数十頁のほうが説得力においてはるかにまさっているのは、そのためではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする