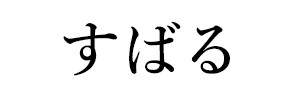書評
『リゾート世紀末―水の記憶の旅』(筑摩書房)
水、この両義的なるトポス
「一一章からなる項目の一つ一つが、それぞれ一冊の本にできそうなほど幅広いテーマばかりである。(中略)その多彩さは裏返せば本書の短所でもあり、どのテーマも中途半端な研究になっているかもしれない」とあとがきにあるのは、むろん謙遜だろう。本書が上田敏の『海潮音』の水脈に連なるきわめて個性的な、それでいて普遍的な仏文学受容史であると同時に、フランス十九世紀を俯瞰する優れた「水の文化史」であることは、明らかだからだ。十九世紀末、オスマンによる大改造を済ませたパリの「城壁」の外側には、田園と工場地区の混淆地帯がひろがっていた。都心に豪奢なアパルトマンを構える上流階級のエリートたちは、やがて交通機関の発達によって身近になったこの緑と水のあるセーヌ沿いの「郊外」を「発見」していく。まぎれもない田舎暮らしを敢行して引きこもりに美を見出したロンドンのインテリたちとは逆に、パリ人たちは、彼らの視線なくしてはひとつの光景ですらなかったはずの外部に、積極的な意味を立ちあげたのである。しかもそこに現出したのは、日常のきらびやかなサロン生活の、いわば出先機関だった。
一方、壁の外に追いやられた庶民にとって、セーヌ沿いの緑地は厳しい仕事から解放された週末にこぞって出かけるかりそめの逃避場所であった。アッパーミドル階級の住む合衆国のサバービアなどと決定的に異なるそうしたパリ郊外の構図は、二十世紀にいたっても受け継がれ、貧民層の住むゾーンから移民たちが寄り集う一種の掃き溜めへと変転を重ねて機能しているのだが、壁の内側と外側の境界を無化し、都市の内部で保たれた階級序列をつかのま破棄する特権的な無法地帯こそ「水」の領域だったとする仮説は、豊富な事例によってみごとに立証されている。
海の生命力を力説したミシュレ、ピクニックと水上の散策を愛したモーパッサン、ブヴァールとペキュシェに田園への憧憬を語らせたフロベール、海底二万里の水を描いたヴェルヌ、そして瑞々しい少女が群生する浜辺のリゾートを描ききったプルースト。病を癒す霧深い北の海と湯治場、美しくはかない幻想を生んだオフェーリアと結核患者の蒼白い相貌の美化、万博を支えるエギゾチスムをあおった大洋と、旅行ではなく「逗留」を許す豪華ホテルの鮮やかなネオン、そして清潔な浴室。
水とは、いかがわしくもあり、またこのうえなく官能的でもある暖昧なトポスなのだ。セラピー効果と疫病の媒介という相反するふたつの極をあっけなく結合してしまう大胆不敵なその水の行方をたどって見えてくるのは、十九世紀的な欲望の果てとしての二十世紀であり、あらたな世紀末だと思われてならない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする