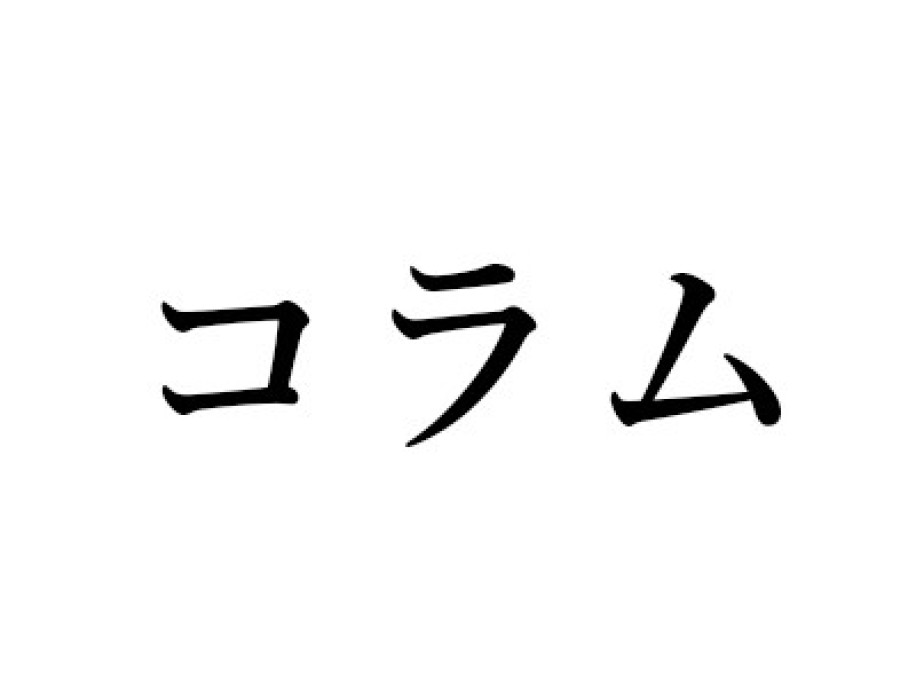書評
『免疫学個人授業』(新潮社)
免疫アレルギーはこの一冊で解消
東南アジアに行くと、腹を下すから生水は絶対に飲むな、と注意される。水分が欲しかったら果物を食うようにとも言われる。そしていつも不思議に思う。土の中の細菌はどうして水と一緒に根から果物の中へは入ってゆかないのか、と。この本『免疫学個人授業』(新潮社)によると、レクチンという物質が植物の中にはあって、外から入ってきた細菌にくっついて殺してしまうそうだ。このレクチンで身を守るのは植物と、昆虫とか軟体動物の類。それ以上に進化した人間をはじめとする高等っぽい動物が病原菌から身を守るのが“免疫”。
免疫は、長い間、予防接種がらみでしか考えられてこなかった。読書界ではカヤの外のごく専門的なテーマとして扱われてきた。ところが、ここ数年、フイに、進化論や脳や遺伝子研究と同じように、思想的、文化的、社会的な影響を与えはじめ、自然科学と文化の境界領域の主役におどり出たのである。地味な免疫がどうやってこのヒノキ舞台に登場したかというと、多田富雄の背中に負われて出てきたのだった。健サンの背中には唐獅子牡丹、多田サンの背中には免疫グロブリン。
自分の背中で実験し、その成果と以後の研究により世界トップの免疫学者の一人となった多田先生が、免疫という複雑怪奇なテーマについて生徒の南伸坊に教授したのがこの一冊。生徒は、名からしてもテッペンに行くにしたがい小さくなる頭の形からしても自然科学向きじゃないことは万人承知のとおりだが、この生徒でも分かるように教えてくれた内容が、普通の読者に分からないはずはない。免疫学アレルギーはこの一冊でまちがいなく解消する。
免疫には、細菌や花粉や他人のタンパク質など外から侵入してきたツブツブに対し、それを異物と認識する能力がある。目に見えないミクロ圏で、自分と他人の区別が何億人相手でもちゃんと出来るわけで、これはもう極小の自分が体の中に充満している状態。考えただけで体の中がムズムズしてくる。そこにミクロの他人が入ってくるからことは複雑で、戦ったり、妥協して受け容れたり、自分の体の中に自分と他人による世間が出来たりしている。
極小の自分のことをT細胞というらしいが、これが感動的で、胸腺という器官で作られたT細胞のうち九〇%以上はすぐ死ぬ。悪い働きをする可能性があるから。そして、ごく一部のT細胞が極小の自分となる。九〇%以上の無駄があってはじめて自分になる。体の中には世間だけじゃなくて人生まで詰まっているのだ。
この辺の授業についての生徒のノートに先生が書き加えたコメント、「私たちが自己というものを確立してゆくときにも、たくさんの可能性を試し、自分に適合したものだけを残して、個性というものを作り出してゆくのではないでしょうか」。
免疫は科学の最先端課題としてだいぶ分かってきたが、初歩的な謎もあるらしい。他人や動物のタンパク質のような異物が注射や手術で体内に入ると、たとえば臓器移植の場合、猛烈な拒否反応が起こるのに、口から入ると、つまり牛のタンパク質が牛乳を飲むという経路で血液中に入ってきても、何も起こらない。
なぜなのか、まだ全然分からないそうだが、この謎解きが出来れば臓器移植やアレルギーの問題も解決する可能性があるとのこと。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする