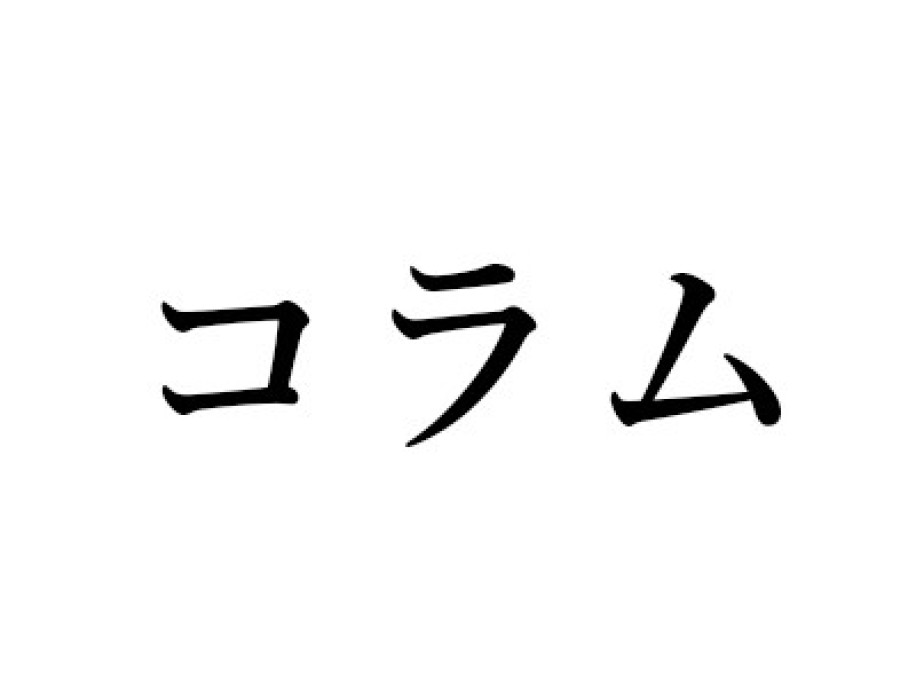書評
『免疫の意味論』(青土社)
善なる「王国」の崩壊
数学者や物理学者は大変なんだそうな。一プラス一は千年先も二であり、積み重なった真理は消え去ることがない。この先息苦しくなるばかりだというのだ。それに較べると人文諸科学は自由でいい。歴史学はもちろん過去の見直しの連続だし、まして文学においてをや。伝統など糞くらえとまではゆかなくても、よほどのんきであることはまちがいない。さて、そこで憂鬱そうな数学者の友人にむかって、それなら君たちはこの際、数字や記号で考えるのをやめて、いっそ小説家のように文章で考え、文章で発表するようにしてはどうか、といってみたら、ピタゴラスの昔からそうだった、と一笑に付された。数学者だって基本は文章で考えているのだ。そんな初歩的な事実に気付かされてみると、道理で寺田寅彦をはじめ湯川秀樹は言うに及ばず、名だたる科学者はみんな文章家であったことを再認識させられた。しかもあちらは宇宙・森羅万象に渉(わた)る思考、こちとらはせいぜい人事のあれこれ、惚れたのはれたの、切ったのはったのの世界だ。
近ごろの科学者の書いたもので、文章が良くて、その内容がまた僕にとって飛び切り衝撃的だったのは、世界的な免疫学者・多田富雄の『免疫の意味論』だ。名著である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は1996年頃)。
ニワトリとウズラの受精卵の神経管の一部を入れ替えると、白いニワトリに黒いウズラの羽根がはえる。キメラの誕生である。しかし、生後三週から二ヵ月たつと、羽根が麻痺してぶらさがり、歩行も摂食もできなくなり、やがて全身麻痺が進行し、衰弱して死ぬ。ニワトリの免疫系がウズラを「非自己」=異物と認め、拒絶したからだ。
この実験を導入部に、多田は免疫学の最新の成果を駆使して一挙に「自己」とは何か、「非自己」とは何か、を考察し、哲学者の問いなどよりはるかにスリリングで、広大深遠な世界へと読者を誘いこむ。
ニワトリとウズラの話にもどると、ニワトリの「自己」がウズラという「非自己」を認識するのは、どうやら「胸腺」という胸の中にある軟らかな、白くてちっぽけな臓器に関係があるらしい。
非自己の排除は免疫系の働きだが、この免疫系を構成するのはHLA抗原と呼ばれる一群のタンパク質で、これがいわばわれわれの身体的自己だ。胸腺の中では、このHLA抗原に対して、非自己である異物が入ってくれば、抗体をつくって二度目からは絶対に入らせないシステムの、想像を絶するような教育が行われている。古代ギリシャ人は早くからこの胸腺の存在を知っていて、それを「魂の座」と呼んでいたという。
しかし、ここから先に悲劇が待っている。自己が非自己を攻撃し、排除するという免疫システムが狂って、もし自己が自己に対する抗体をつくったらどうなるか。自己が自己を攻撃し、殺しあう終末的事態。エイズ・ウイルスはまさにこのような免疫システムという、美化された、善なる「王国(エスタブリッシュメント)」を崩壊させるべく到来した。現代、その他の難病と呼ばれる病気のほとんどもこの免疫システムの崩壊によるものだ。
われわれの近代、その進歩主義もヒューマニズムも、自己が自己を攻撃しない免疫系という善なるネットワークの上に築かれていたのだ。
そして、多田の論述は、もともと自己と非自己を識別し、自己を非自己から守るなどという、そんな王国は一度も存在したことはなかった。砂上の楼閣にすぎなかったのだ、とまで及んで、われわれを混沌の中に宙吊りにする。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする