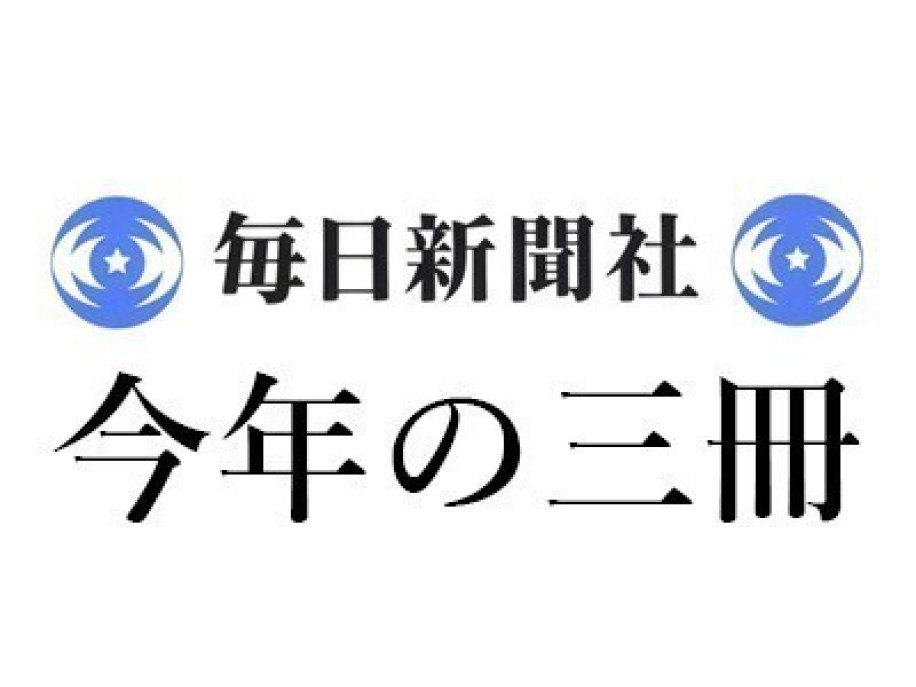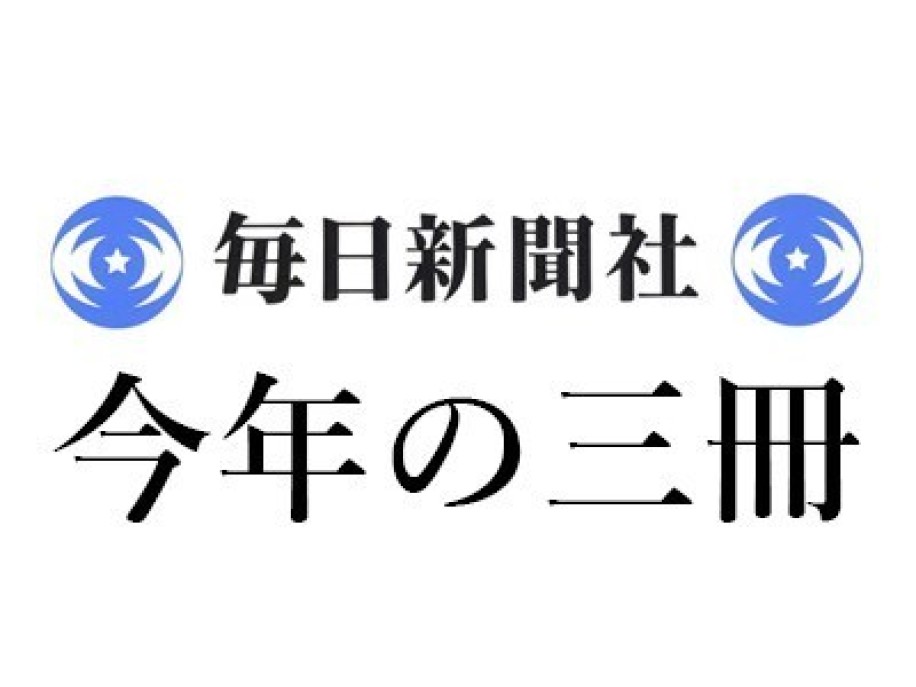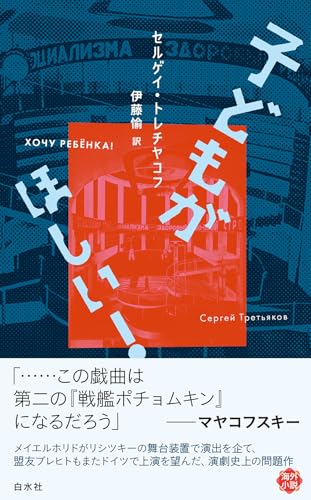書評
『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29』(新潮社)
「福袋」のような予期せぬ発見
アメリカの日本文学者、ジェイ・ルービンが編纂(へんさん)した近現代日本小説選集である。もともと英語圏読者のためにペンギン・ブックスの一冊として英訳で出版されたものだが、それが言わば「里帰り」して日本版が出ることになった。この本のために、村上春樹が長い序文を書いている。彼は日本の近代・現代文学については詳しくないと謙虚に断ってはいるが、優れた作家ならではの緻密な読解が随所に光る。例えば、若い軍人の切腹をエロスと一体化させて描いた三島由紀夫の「憂国」について、「ひとつの想念の徹底した純化」は文学として評価できても、「想念を行為として純化させる」(つまり作家自身がハラキリをする)のは別のことだ、と言う。吉本ばななの独自性については、「文学とはこういうものだ――というような旧来の決めつけは、彼女の小説にはまったく無縁」だと評し、芥川龍之介の作風については、一貫して「暗闇の中に浮かぶ明かりの、短く儚(はかな)い美しさのようなもの」が見受けられるという印象的な比喩で説明する。
序文はさておき、肝心のアンソロジーの中身はどうか? 大づかみに言えば、古くは国木田独歩の古典的名作「忘れえぬ人々」から、東日本大震災の被災地を描いた佐伯一麦の「日和山」までの、大きな幅がある。ただし日本の近現代文学をまんべんなく通覧しようという意図は、編者にはもともとない。じつはこれまでも日本近現代小説の選集が英語で出版されることは珍しくなく、英語原著の巻末には二二点もの先行アンソロジーのリストが挙げられているのだが、そのうちの正統的なものは――先駆的なドナルド・キーン編、最近ではテッド・グーセン編など――明治から現代まで時代を追って著名作家の代表作を選び、文学史の流れが辿(たど)れるように工夫されている。
しかし、ルービンは時代順をやめ、「忠実なる戦士」「男と女」「自然と記憶」「恐怖」「災厄」といったテーマに即して作品を配置した。「レンタルビデオ屋の陳列方法」に倣ったのだと言う。しかも収録作品には文学史上名作として知られているものは少なく、むしろ大部分は編者の個人的な趣味と思い入れによって選ばれたものに見える。一冊ですべてを収めることなど不可能だとはいえ、ここには太宰治も、安部公房も、大江健三郎も入っていない。
しかし、序文で村上春樹が言うように、これは一種の「福袋」として、予期せぬ発見を喜ぶべき本なのだろう。選ばれた作品には、編者が一生を通じて関わってきた日本文学との様々な出会いの記憶が刻印されており、彼自身の文学観が強く打ち出されている。特に「災厄 天災及び人災」というセクションには力が入っていて、大震災、原爆、戦争などの経験を何らかの形で反映した作品が並ぶ。ここでは、加藤清正・小西行長らの朝鮮出兵を題材にした芥川の伝奇的小説「金将軍」が、関東大震災の際の朝鮮人虐殺への作家の反応として採られている。この含蓄ある選択には驚嘆した。一方、広い意味での災厄をめぐる星野智幸、松田青子の尖端(せんたん)的作品も異彩を放つ。
このような本である以上、日本版の『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇29』というタイトルは、実体からかけ離れているのではないか。収録作の多くは、正統的な意味での「名短篇」とは言い難いし、作品を選んだのは「ペンギン・ブックス」という非人格的な主体ではなく、独自の見識と趣味を持ったジェイ・ルービンその人だからだ。
ALL REVIEWSをフォローする