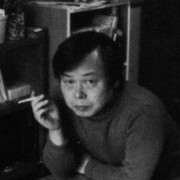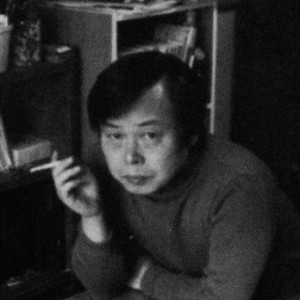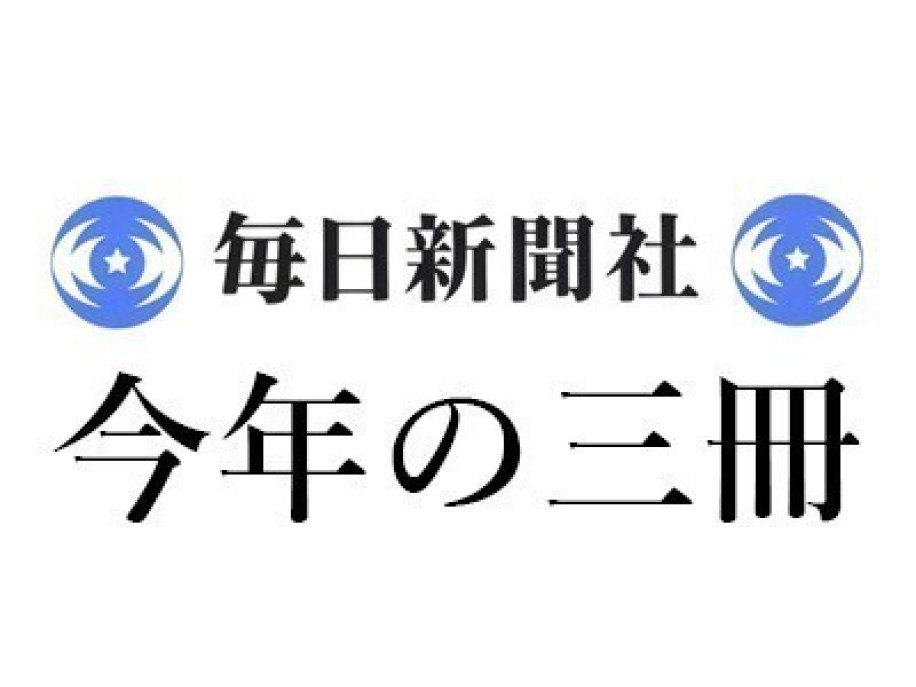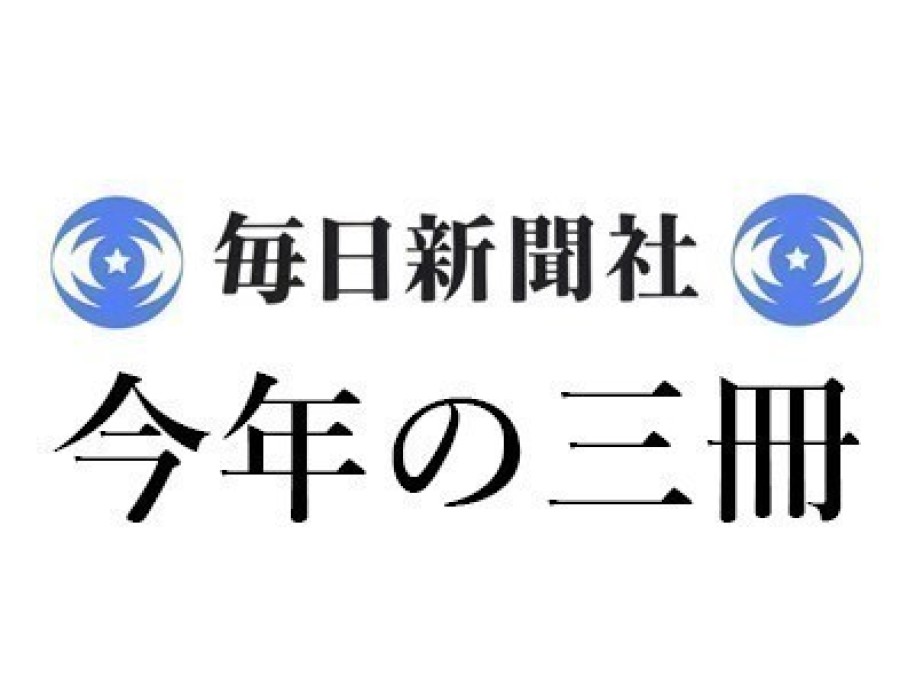書評
『感じる日本語』(思潮社)
言語体験でつづられた「自伝」
正しい日本語、美しい日本語が、このところとみに話題になる。正しい日本語を書くのは大いに結構。しかし一方では、そうするとなにか大切なものがポロッと落ちてしまうような気がしないでもない。正しい、美しい、という限定がつくと、それ以外の正しくない日本語、美しくない日本語は、落第生みたいに枠外に落とされてしまうのではないか。詩人の川崎洋さんの『感じる日本語』はそういう分け方はしない。のっけから「汚い日本語などない」という。きれい、または汚い、という限定された日本語などはない。あるのはまるごとの日本語だけ。上記「汚い日本語などない」という一文は、とりあえず「文化としての方言と悪態語」を論じているのだが、明治以来の政府当局による共通語、標準語の性急な押しつけのために落ちこぼれてしまった言葉は、方言や悪態語以外にもいくらもある。
すぐに消えてしまう流行語、嘘(うそ)、無意味な言葉遊び、隔離病棟の病者や子供の詩。そうした余白に落ちこぼれた言葉を、著者は永らく現場で採集してきた。そしてたとえば幼稚園児の幼児語の詩のまばゆいばかりの輝きを取りだしてくる。
無理強いの、歪(ゆが)んだ経過をへて流通している、いわゆる標準語は、まだまだインスタントな人工語で、(中略)方言の側から輸血しないと、ますます貧血の度が進む。
そうはいっても、標準語に対するマージナルな言葉の復権といった、気負った論争調はない。著者は戦前東京生まれの野球少年。生まれつき方言をしゃべっていたのではない。戦中は福岡県に疎開した軍国少年、戦後は米海軍基地勤めで米軍兵士と英語でやりとりした。いやおうなく異文化・異言語のあいだに立たされて、異質の言葉との差異のニュアンスに敏感にならざるをえない。そうした過去からの一切をまるごと、気負いも衒(てら)いもなく、今に現前させる語り口の妙を、ときにはユーモアたっぷりに堪能させてくれる。まるごとの日本語で語った、まるごとの人生体験としての言語体験。そうか、詩人にはこういう形式の自伝があったのだ。
朝日新聞 2002年11月17日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする