書評
『日の名残り』(早川書房)
古き良きイギリスを象徴する主人公の品格と潔さ
『女たちの遠い夏』『浮世の画家』に続く、著者の長編第三作である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1990年)。前二作が日本を主な舞台としていたのに対し、本書はイギリスが舞台であり、日本人は登場しない。その意味で彼は、日系人であることへのこだわりに決着をつけたとも言えるが、大戦にともなう社会の変化を、「私」という一個人の視点を通じて捉(とら)えている点では本書も前二作と同じである。つまり彼の小説では、大文字の歴史が登場人物の私的歴史と同じレベルで語られるのだ。ことに本書ではその傾向が強い。語り手でもある主人公スティーブンスは、人生の最後の黄昏(たそがれ)にさしかかった老執事である。彼にとって世界は、主ダーリントン卿の屋敷を中心に動いていた。一九二三年にはここで米仏独の政治家や外交官を集めての国際会議が開かれるのだが、それを項点にダーリントン家は凋落の一途を辿(たど)り、やがて屋敷は執事ごとアメリカ人の手に渡る。どこかブニュエルの映画『ビリディアナ』のラストを思わせる筋立てである。
物語は一九五六年七月、この老執事が新たな主人の勧めと一通の手紙の到着に心を動かされ、短い旅に出るところから始まる。手紙の差出人は、かつて屋敷で女中頭(がしら)を務めていた女性だった。彼との間にほのかなロマンスのあった彼女と再会するための旅、それが物語の一つの枠組みとなっている。そして主人公は道中、折に触れ、過去の様々なエピソードを語り続ける。名執事だった父親のこと、ダーリントン家での日々。わずか六日の旅の間に、実に多くのことがモノローグで、また途中、出会った人々との会話という形で、淡々と語られる。
このスタイルに、『カンタベリー物語』やピカレスク小説の伝統を認めることもできるだろう。だが物語は時折、かすかなエロティシズムが現れることはあっても、猥雑という言葉からはほど遠い。なぜなら語り手が、執事としての職業意識から、可能な限り感情を抑制しているからである。ダーリントン卿の名づけ子に「生命の神秘」について教えようとする件や、女中頭の求愛がほとんど、ほのめかされるにすぎないのも、この自己抑制が原因なのだが、しかしそれが上質なユーモアを生んでいることも見逃せない。
このようなユーモアはもはや過去のものになってしまった感があるが、主人公が冒頭で、アメリカ人的ジョークが理解できないと言い、また末尾でそれを研究するつもりだと述べているのは、皮肉であると同時に「モンティパイソン」的ユーモアとなっている点で実におかしい。イシグロは、やはりイギリス人である。
この小説のキーポイントは、主人公を老執事に設定したことだろう。その存在は、複数の階層を結ぶ仲介者であると同時に、古き良きイギリスを象徴するものであり、彼の個人史はそのまま文化史ともなる。披露する執事の技術の数々、ドアで聞き耳を立てることは、いきなり入っていって中の人間に迷惑をかけないようにするためだとか、客人の前では無知を装うことが執事の務めだといった心得、あるいは銀器を磨くことの意味やその歴史といった、真偽のほどは不明だが、虚構としてのリアリティーをもつ多くのディテールに、読者は興味を惹かれるにちがいない。
ことに、かつて名執事であった父親が寄る年波に勝てず、盆を運べなくなると、今度はワゴンを操ることに情熱をかけ、そしてついに倒れるエピソードは感動的である。しかも語り手は今やそのときの父親同様、意思に反して過ちを犯す年齢になっているのだ。ナチに利用されたというダーリントン卿やこの父親、そして職務に忠実なあまり、女中頭の気持ちを無視した主人公自身にも、父親的独善性が見られる。にもかかわらず、彼らは愛すべき存在である。
それはおそらく、名家や名執事の条件とされる「品格」が彼らには備わっているからなのだろう。だからこそ主人公は、時代の変化を認め、それを受け入れていく。イシグロの作品の爽やかさの秘密は、文体、そしてこの主人公たちの前向きの潔さにある。
初出メディア
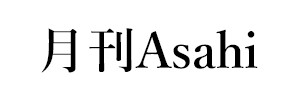
月刊Asahi(終刊) 1990年10月号
ALL REVIEWSをフォローする


![ビリディアナ ルイス・ブニュエル HDマスター [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51tmgFSvDLL.jpg)




































