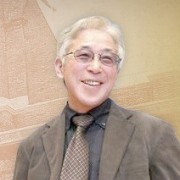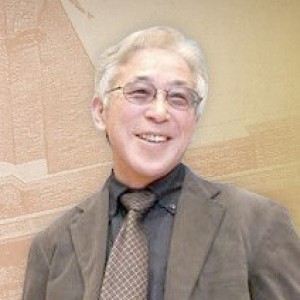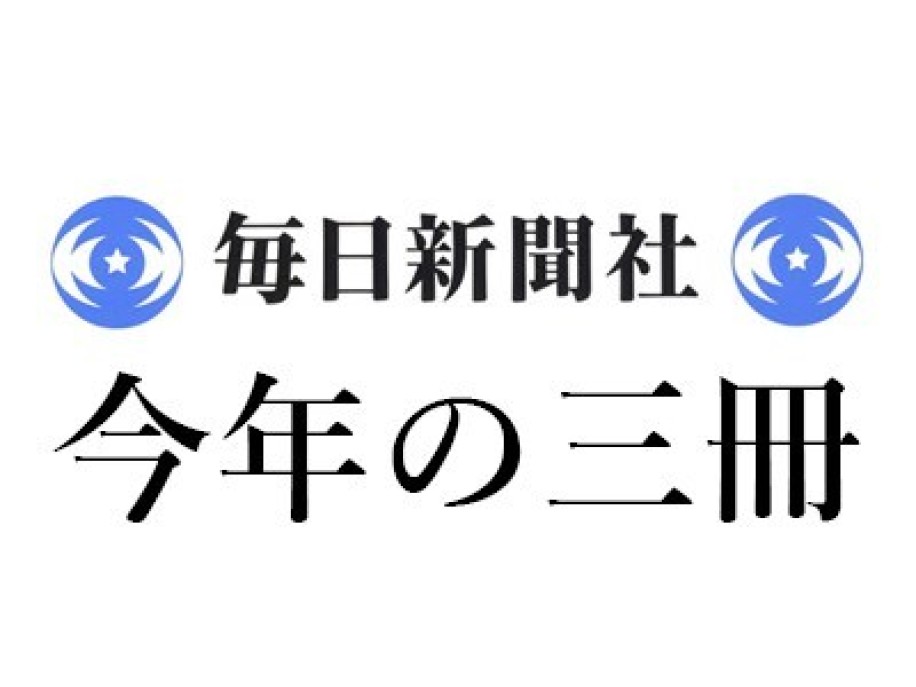書評
『ヨーロッパ史 拡大と統合の力学』(岩波書店)
社会の中核を担った「イエ経済」
アルプス以北のヨーロッパが歴史の舞台に登場するのはローマ人との出会い以後のこと。そこはまだ大半が鬱蒼とした森林におおわれていたし、小さな村々があり半農半牧の生活にすぎなかった。地中海を内海とするローマ帝国に編入された地域では、耕地が開発され、葡萄畑も北進していた。古代末期には、ガリア(ほぼ現フランス)北部に進出したフランク族は着実に勢力をのばし、五世紀末、有力豪族のメロヴィング家は分立諸族を統一して確固たる覇権を築いた。ここでは正統派キリスト教が受容され、ローマ・カトリック教会に支持されたために、後世のヨーロッパ世界を形成する中核らしくなった。
八世紀になると、フランク王国の実権はカロリング家に掌握され、軍事力の強化とともに、離反した諸部族の統合が進められた。やがて、イベリア半島から北上してきたイスラム勢力を斥け、カトリック世界での声望が高まった。
とりわけカロリング家のカールは武勇にすぐれ、領土の統合と征服に努めた。このために失われつつあったヨーロッパの統一が実現し、八〇〇年、この勇将は教皇から「ローマ皇帝」として戴冠され、カール大帝(仏語ではシャルルマーニュ)として名実ともにヨーロッパ世界の支配者になった。
ここまでは、高校「世界史」ほどの記述。でも、本書の議論の独自性は、このヨーロッパ形成論の背景に古代にさかのぼる「オイコノミア」論をもってきたことである。語源となるオイコスは本来「家」を意味しており、前キリスト教時代の地中海世界にあって「オイコノミア」は「家政」に関する概念であった。そこでは、イエ経済(家政)は社会の中核としての役割を担っていたのだ。
古代において家父長に求められる徳目は「財の活用のあり方」であり、なによりも財と家人(一族郎党)を監督する能力であった。家父長の権限は生活のあらゆる局面におよび、それらのイエ経済が都市国家(ポリス)の政治・経済的活動を支えていた。
この含意で、五世紀初めの教父アウグスティヌスにあっても「イエの秩序」は「神の秩序ある支配」を反映するとみなされていた。このような家政としてのオイコノミアは一八世紀に至るまで旧ヨーロッパ世界の基軸をなす概念であり、「全き家」というキーワードで、前近代ヨーロッパ社会の編成問題が論じられてもいた。
近世以降の国家を考える上でも、統治技術の起源は、M・フーコーが指摘したように、キリスト教的な司牧、つまり「霊魂の統治」であった。統治とは、極言すれば「オイコノミアというかたちで権力を行使する術」でもあるのだ。
近代ヨーロッパの古層にはキリスト教的世界観による社会秩序論があり、やがてそれと異質な「近代的思考」の発生から、自由で平等な個人の結びつきをもつ「近代市民社会」が生まれ出ることになる。
狭義のヨーロッパは西欧として理解されるが、著者は東欧のビザンツ社会の研究者であり、そうであればこそ西欧近代社会への新たな視角があざやかになる。西洋史研究の流れをながめれば、福田徳三、三浦新七、上原専禄にさかのぼる一橋学派が目に浮かぶが、そのマクロ史学の伝統が著者のなかに息づいているかのようである。
ALL REVIEWSをフォローする