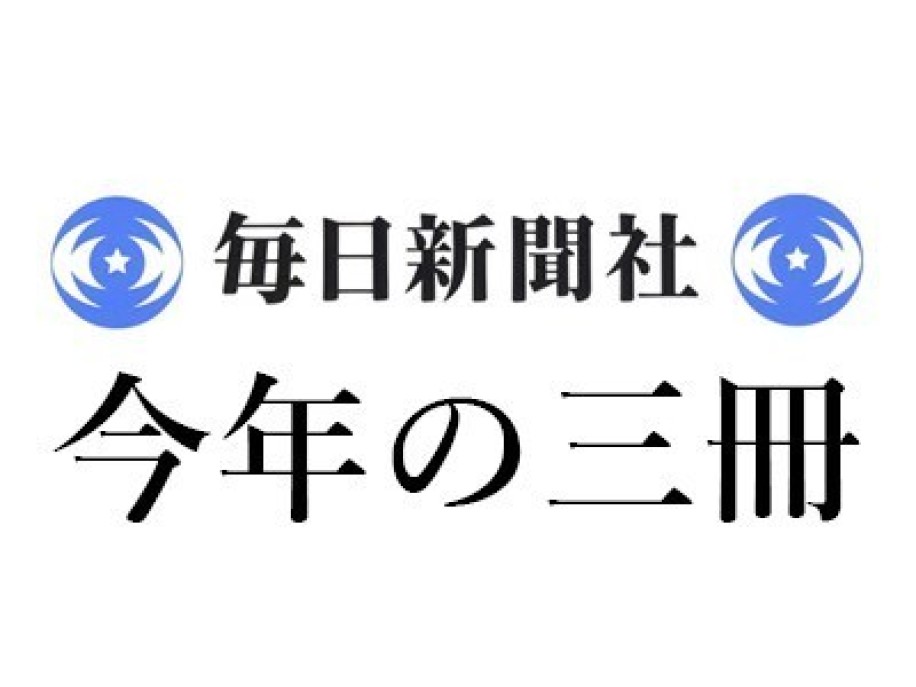書評
『地獄めぐり』(講談社)
死者の国では王もゴタマゼで その融通無碍ぶりが興味深い
ときおり旅先で出くわすことがある。古い温泉町のことが多い。町角に何かを祀(まつ)った祠(ほこら)がある。木造の粗末なものだが、古ぼけていても独特の威厳と雰囲気があって、つい足をとめる。格子の奥に幕がめぐらしてあって、石像の半身が見える。色の褪(あ)せた木像のこともある。闇をすかして目をこらしていると、通りすがりのおばあさんが足をとめ、みんな「ばば堂」と言うが、ほんとうは「姥堂(うばどう)」でしょうねといったことを説明してくれる。三途の川のほとりにいて、亡者の衣類をはぎとる人。こわいこわいおんばさま。
この本では「地獄へ旅立つ」章に出てくる。「死の山」をこえると三途の川。この世とあの世を分かつ暗い流れ。おんばさまは正確には「姥尊」と書き、「脱衣婆(だつえば)」のことのようだ。現世の飾り物をはぎとられ、亡者は素裸で地獄の沙汰にさらされる。それだけではないという。
脱衣婆は一方で奪う者でありながら、他方では与える者でもあるという両義性をもつ。
死者の国の約束は、われわれが思っているような単純なものではないらしい。三途の川にしても現世と来世の境界であるとともに、「初恋(あるいは初体験)の人と出逢う」ところという考え方があった。それとなく死が性愛と結びついていることを暗示していて、『地獄めぐり』がこよなく楽しくなってくる。
以前、信州・野沢温泉で十王堂に行きあったことがある。共同湯の向かいの神さびた建物は、板間にゴザが敷いてあって、ズラリと木像が並んでいた。まん中でカッと口をあけているのが閻魔(えんま)大王。
地獄の総帥と目される「閻魔」とは一体何者なのだろう? まずは、その出自を追ってみることにしたい。
以下、そもそもにはじまって、かつての子供を恐がらせた地獄の王がくわしく語られ、いかに民間伝承とちがうものかがわかってくる。中国の十王経では、閻魔王はようやく第五の王とされているが、わが国の民間信仰と合いにくいので、十王を不動や文殊や薬師にわり振ったのだろう。そのゴタマゼのぐあいが日本人の信仰の融通無碍(むげ)ぶりを示して興味深いのだ。
『地獄めぐり』には、無数の絵図がちりばめてある。「影の国」を経文で語るのはやさしいが、絵解きするのは、とてつもなく難しい。昔の絵師たちは恐怖をかきたてるイメージを、怪異譚(たん)や縁起物をかりながら、そこに創意工夫を加えていった。
かりに「地獄物」を一つのジャンルと考えれば、そこに共通する手法といったものが見てとれる。一つはデフォルメによる誇張法である。炎々と燃えさかる地獄の業火がなんとあざやかに描きとめられていることだろう。誇張がそれなりの効果を生むためには、細部のリアリズムがなくてはならない。地獄の鬼たちの毛ずねなども、一本一本克明に描かれている。
共通する特色のもう一つは、類型化だろう。いずれを問わず型にはまっていて、恐怖の一方で笑いをかきたてる。特有の愛嬌をそなえており、しかも時代が下るにつれて地獄の住人が戯画化されて明るくなる。もっともあざやかに新時代の動向を伝えるものだろう。つまり、ひとことにしていえば、「地獄の沙汰も金次第」なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする