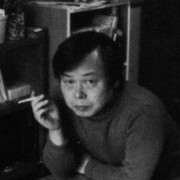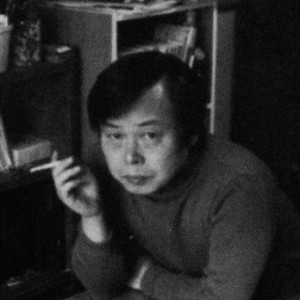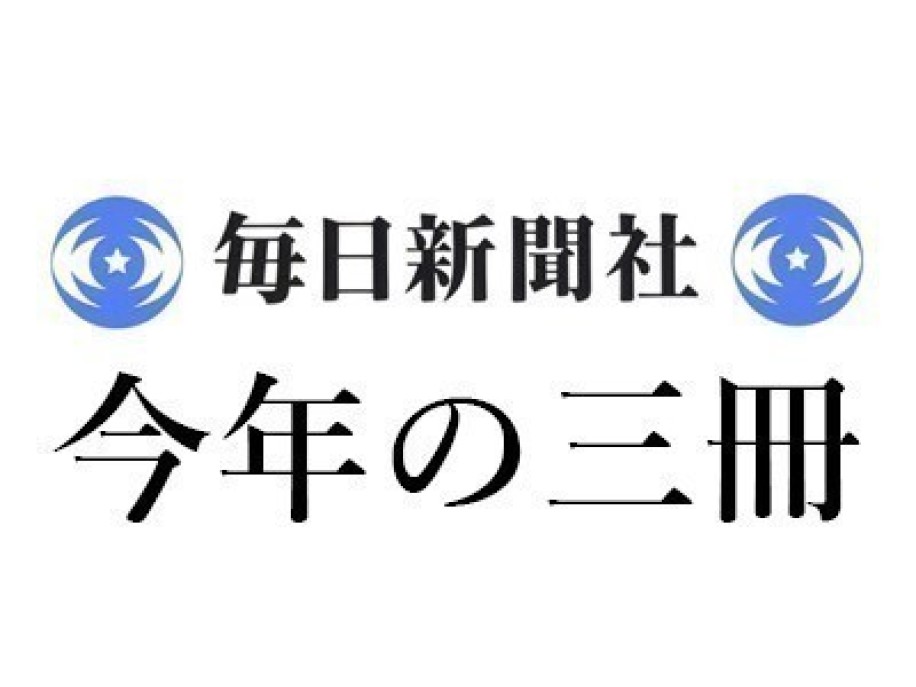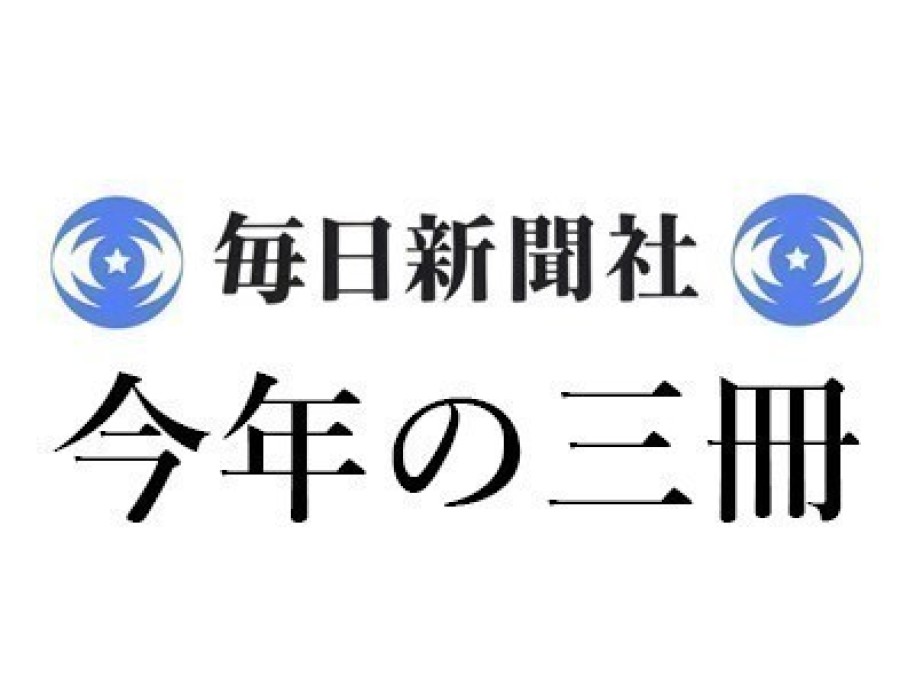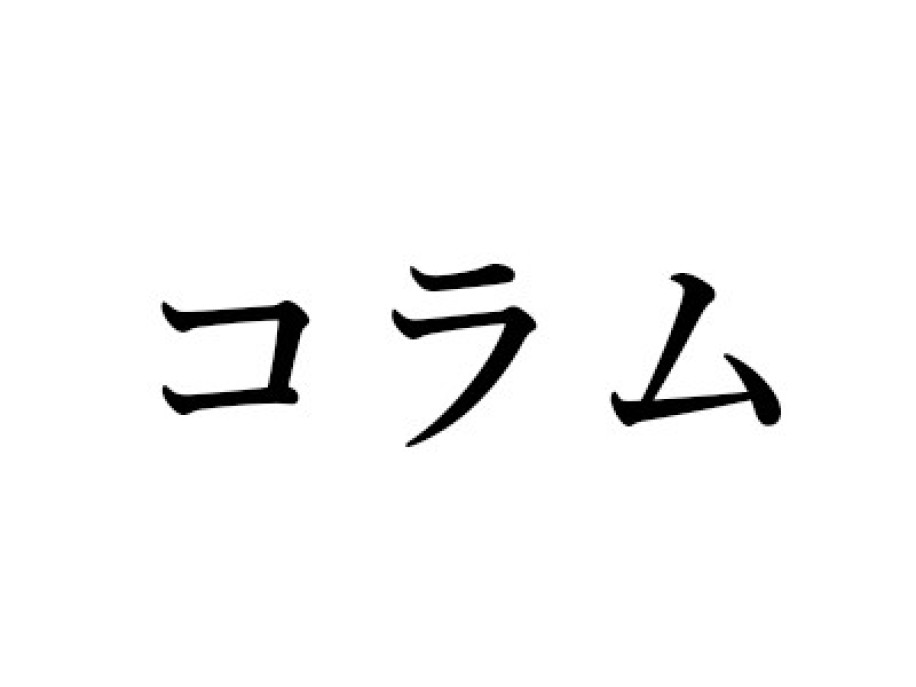書評
『ネロ』(みすず書房)
きらめく悪の実存的分析 栄華と悲惨の極限を極めつくした"母親"
わたしたちの場合ならさしずめ講談講釈の類いを通じて親しいような、ネロのような人物を主題にした伝記物語はすくなくないだろう。しかし、精細な資料が人物の魅力を減殺するどころか、いよいよ光彩陸離たらしめる態の史伝はそう滅多にあるものではない。そういうある端倪すべからざる歴史家の手になった丹念な伝記としてだけ見れば、たとえばネロがローマを焼き払ったという通説がほとんど推理小説さながらの傍証推理によって完膚なきまでに論破しさられている章などが、本来の歴史愛好家にとってはこたえられぬのであろう。
しかし、わたしにとってそれよりも面白かったのは、恐るべき母親アグリッピナの演出の糸に操られ、御用哲学者セネカの書いた科白を口ずさみながら、天成の喜劇役者としてローマ帝政史上に登場した少年皇帝ネロが、さながらあたえられた悪の仮面が肉化してしまったかのように、突如「怪物」の情熱にとらえられ、己れを育くんだ近親知己をつぎつぎに粛清して、ついに史上最大のグロテスクな流血劇の主人公へと変貌してゆく、悪の実存分析ともいうべきくだりであった。
しかもこの人物年代記を十分に多彩な絵巻たらしめているのは、いずれ劣らぬ巨人的な情熱家の的確な配置である。とりわけ皇帝のいわゆる「最良の母親」アグリッピナの生涯、栄華と悲惨の極限をともども極めつくして凄艶というにふさわしい。実兄カリグラ帝に処女を奪われたのを手始めに、この稀代の淫女はつぎつぎに時代の権勢家に肉を売り、奸策を弄して伯父クラウディウス帝と結婚するやこれを暗殺して息子を王座に送る宿望を果し、あまつさえ実の子たる皇帝ネロと媾って衰えゆく権勢の挽回をはかるが、老犬のように惨殺されて息絶える。
読み進むにつれて、奇妙なことに、わたしは、今日の世界が急速に小さくなっていくような、一種空想科学小説風の幻覚を禁じえなかった。芸術家気取りの独裁者、堕落した元老院と買収された軍隊――すべてが二十世紀の今日と相似形でありながら、ここではすべてが途方もなく巨大で激情的なのだ。だが、同じ事情がイロニーとしてはたらけば、にわか仕立ての風俗と顕微鏡的な性心理学に明け暮れる現代小説に疲れたわたしたちは、あのローマ帝国に響く軍馬の蹄音とキリスト教徒の叫喚をありありと耳にしながら、おそらくふたたび少年の日の夢想にめぐり会うことになる。
歴史家はネロが暴君であったという事実を否定はしないが、同時にネロの治世がローマ帝政史上でも稀な繁栄と安定の時代であったという事実をも隠そうとはしていない。ほかならぬこの繁栄の眠りが怪物をはらんだのではないか、と問いかけるには歴史家の筆はあまりにも慎ましい。ということはしかし、そういう読み方があらかじめ排除されている、という意味ではない。
初出メディア

日本読書新聞(終刊) 1967年6月19日
ALL REVIEWSをフォローする