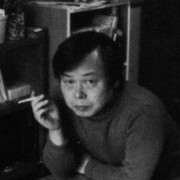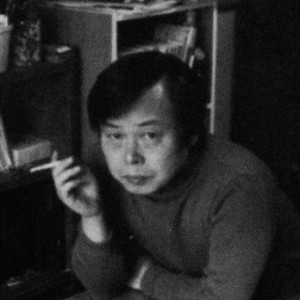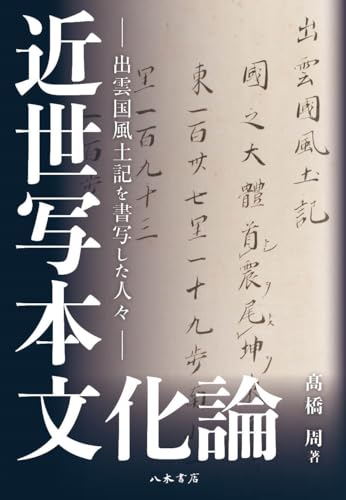書評
『中国文学の愉しき世界』(岩波書店)
おもしろずくめの手ごわい迷路
亡くなったさる中国文学の大家の蔵書が即売会に出た。すこしおくれて行くと、めぼしいのはあらかた売れて、一冊百円の線装本が数冊残っている。ろくに題名も見ないで買い、しばらくしてからふと手にとってみると、これがすこぶるおもしろい。『世説新語』。竹林の七賢人の奇行や、その衣鉢を継ぐ奇人たちの言動を躍如と描いた書物。時代は魏晋の政治的変動期。魯迅の「魏晋の気風および文章と薬および酒の関係」をお読みになった方はご存じだろう。文人たちは奇行愚行で韜晦(とうかい)しながら権力の介入をはぐらかしたのだった。それはそうと、ここで若き日に百円の線装本に遭遇してからの博大な読書体験を披露しているのは、著者の井波律子さん。もともとフランス文学志望だったのが、学部入学で中国文学専攻に切り替えたのだそうだ。ところが、これがいたって狭き門だった。中国語はずぶの素人に近い。それがいきなり演習で老舎を読まされる。しごきにしごかれた。おかげで中国三千年の文化を自在に享受できるようになった。中国の夢物語の構造として著者が要約した言葉を借りれば、とても小さな「枕の穴の奥や槐(えんじゅ)の木の穴の奥に、広がる異界を夢遊して快楽を尽く」せるようになった。
内容も、奇人や隠者、大長篇(ちょうへん)『三国志演義』や『西遊記』、仙界訪問記や奇書の話と盛りだくさんだが、それぞれが短いエッセイにまとめられていて読みやすい。もともとが修辞学の専門家であるだけに機知的表現に長(た)けていて、文章も平明で軽快。中国文学の古典といえば、老大家が白髯(はくぜん)をしごきながらものものしく講釈するものと思われがちだが、ロックと探偵小説に目がないという女性文学者ともなれば、そこは自(おの)ずとちがってくる。
でもあまくみてはいけない。百円の線装本や枕の穴がいい例で、入り口は壷(つぼ)の口のように小さく狭くても、なかには大廈高楼(たいかこうろう)が連なり、美女に注がれる盃(さかずき)の酒はいくら飲んでも尽きるということがない。なまじ与(くみ)しやすしとみてうっかり踏みこんだら最後、中国三千年の奥は千畳敷。おもしろずくめで帰れなくなりそう。
朝日新聞 2003年2月2日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする