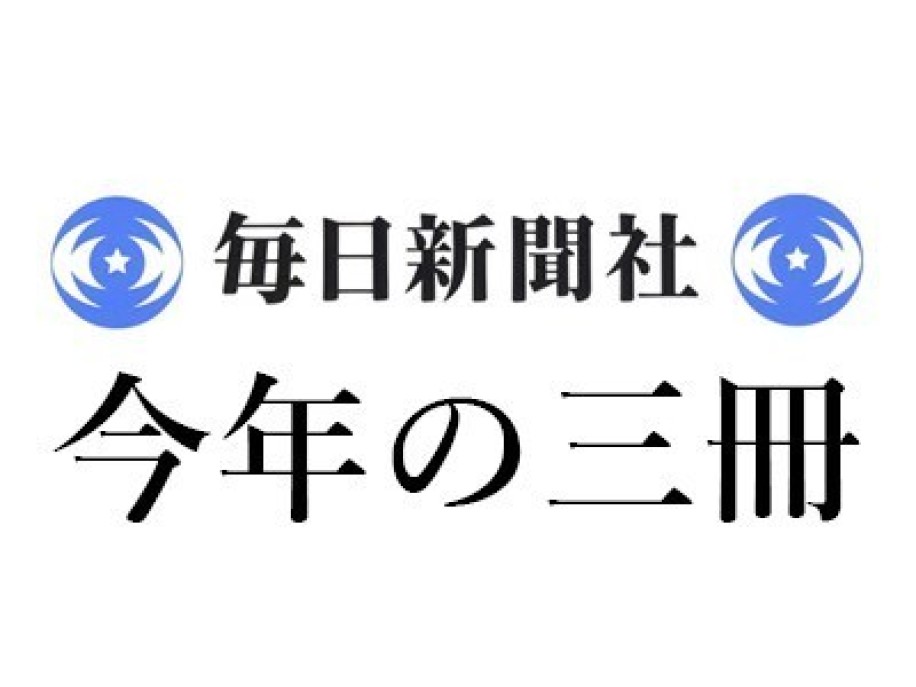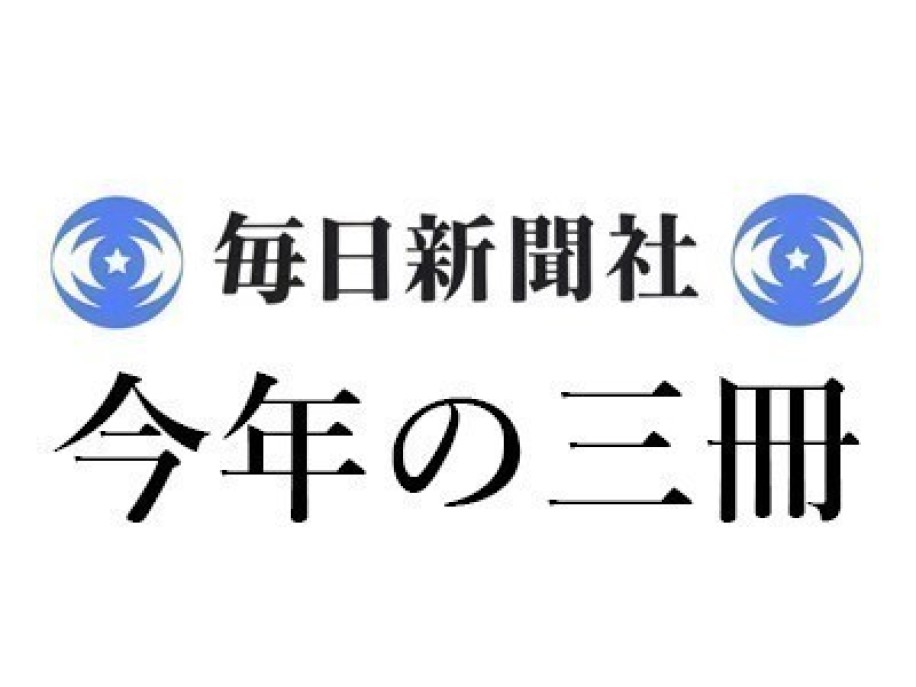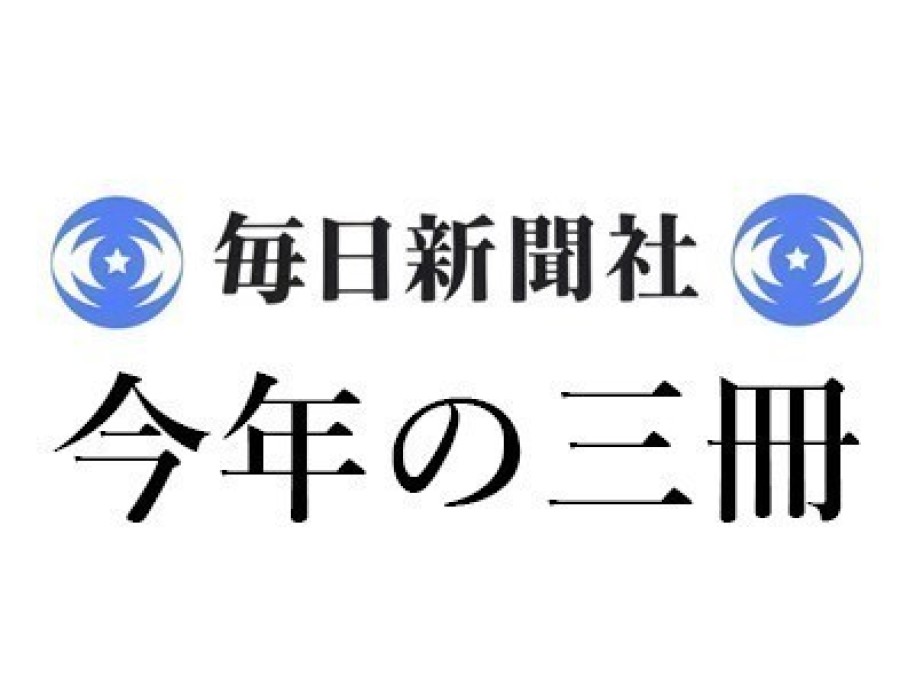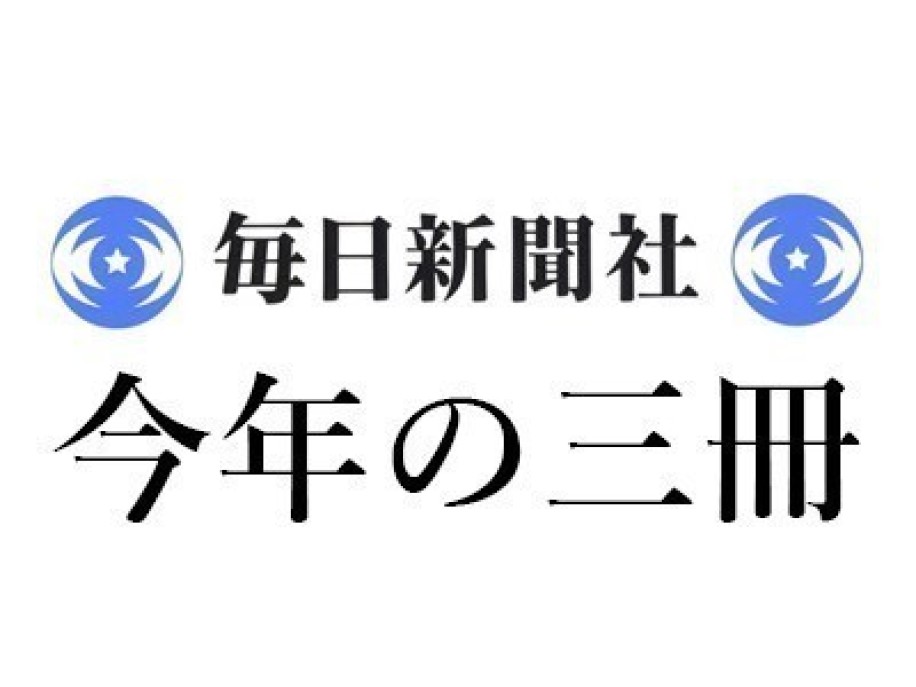書評
『人間・野上弥生子―『野上弥生子日記』から』(思想の科学社)
九十の女でも恋は忘れない
九十九歳まで生きた野上弥生子は、日本の女性作家の中でとびきり知的な存在とされている。侵略戦争に協力せず沈黙を守り、夫との家庭を全うし、小説を書きながら三人の息子を大学教授に育てた。エライナーと思う反面、優等生すぎてヨソヨソしい感じがある。晩年の随筆を読んでも、東大病院に入院中、東大生の孫が見舞いに来るくだりや、安倍能成(よししげ)や岩波茂雄がまるで普通名詞みたいに出てくると、自分と、この作家との隔たりを感じざるを得ない。中村智子さんがその日記を精読した『人間・野上弥生子』(思想の科学社)は快い裏切りである。著者自身、「これがあの野上弥生子か?」とぶったまげている。
例えば夫野上豊一郎について。「男といふものは実際にくらしい獣である」。夫は弥生子が仕事関係の用事で人に会うのも嫉妬(しっと)した。「私見たいな束縛と監視の下に生きてゐる女が一人だつて生きてゐるだらうか」。そのくせ夫は外出し、交友があり、広い世界を見てくる。知的好奇心の強い弥生子にとっても、家庭はやはり「鎖」「獄中」であったと知り、私はホッとした。ああ、野上弥生子も人間だった。
夫は浮気もする。「私は自分の家庭生活に少しうぬぼれすぎてゐた」。「これがもつとも円満幸福の見本の家庭だからおどろくべきことである」。しかし「この苦痛と怒りの中で、私は如何に彼を愛してゐるかをますます強くかんじる」とも書く。
法政大学総長となり、能の研究家としても知られた夫は、晩年「長いあひだの仲間」のようになり、しばしば別居もした。
「一人ゐるといふこと、これはなんとしづかに和やかで、愉しいことか」
夫の生涯の嫉妬は中勘助と弥生子の昔の恋に向けられたが、この思いも日記につづられている。
「逢はれぬ人ほどこひしくなつかしい」、「すべてのおもひでは快い詩として今はこころに浮ぶ」……四十年を経て対面したかつての恋人は眉(まゆ)も半分白く、顔は細面になっていかつかった。耳も遠かった。「これでは昔の私たち二人のひめごとなどしめやかに語ることは出来ないわけだとおもふと、なにか微笑ましく、運命の皮肉を深く感じた」。余裕とユーモアがある感想だが、中勘助の文学自体には手厳しい。
お互い伴侶をなくした田辺元との老年の知的な恋愛は、弥生子ではないが「びつくら」である。六十八歳の弥生子は北軽井沢の別荘を女学生のようにノートを抱えて彼に哲学を学ぶために行き来する。ライプニッツ、プラトン、パスカル……そして「情勢と心の動き次第では、私はもつと積極的な熱情にだつて応じ得られる」とすら書いている。しばらくののち「やつぱり遠くから眺むべき高山」だと思いいたるのではあるが。
書きも書いたり六十二年分。三十八歳から九十九歳までの日記は全集の十九巻分をしめ、全集は岩波書店の予約出版なので、このダイジェストは大変ありがたい。著者自身は鋭くも簡潔な解説にとどめ、日記そのものに語らせる。
弥生子の友人評は正確にして辛辣(しんらつ)をきわめる。例えば芥川龍之介評「人生の花形といふものは結句人生のクラウンではないか」。安倍能成評「本質的な保守性が、目下のポストとからみあひ、彼らしいリコオ者にするのである」。宮本百合子評「あの人は他人のことだと実によく分かるくせに、自分を中心にして行為するとき、まるで無思慮になる」。
ダイジェストのさらに恣意的な引用をしてしまった。ともかく自称「多感な動揺しやすい女」は、あくまで心のうちを人にもらさず、表面「清教徒的に」生きた。その内面は日記、まさにここにある。「人間は決して本質的には年をとるものではない気がする。九十の女でも恋は忘れないものではないであろうか」。
はじめて野上弥生子という人の体温に触れた気がする。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
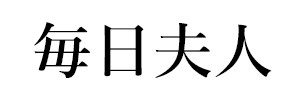
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする