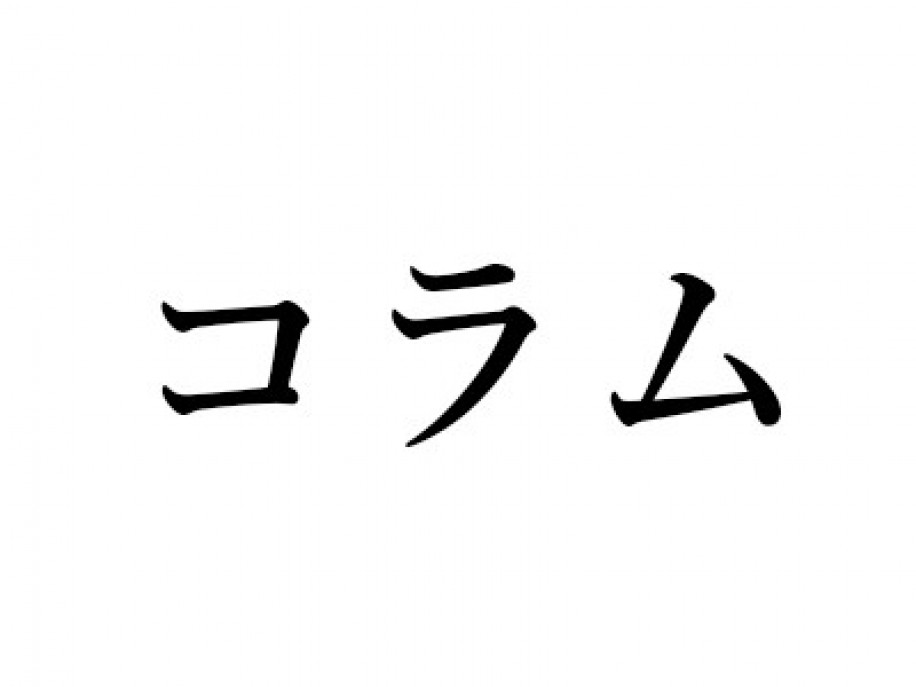書評
『人の樹』(潮出版社)
生命の底の底にふれる「植物の私生活」
タイトルの意味? わかるようでわからないが、そんなことはかまわないで読んでいく。村田喜代子の小説がたのしいのは、発想がユニークだからだ。モチーフがリアルな日常をこえている。その上でリアルな日常を書くための強力な表現力をそなえている。ここでは樹が人のように考え、語り、結婚し、仲間とつれだって恩人の葬式に出かけていく。そんな短篇が十八篇。どれもごく短いが、小品というのではなく、よけいなものを捨てていったら、あとに残ったものの短さ。
サバンナに一本きりのアカシアはつぶやく。「孤独はわたしたちの属性なのよ」
雲南の山また山の中の谷間にはえるニーム。センダン科の木でハーブの一種。「木婚(もっこん)式」によって人間と婚姻をむすんだが、幸福のさなかに悲しくなった。夫を楽しませることが何もできない。「……夫を抱く手がないの。暖かい乳房のついた胸がない。彼にキスする唇がない」
マダガスカル島のバオバブの木は、チョコまかとせわしない猿に言ってきかせた。自分たち木は「自然の仕掛けで生きている。体はこんなにでっかいが、じつは静かな生きものなんだ」
シベリアのカラマツは林をなして歩きまわる。どうして歩かないことがあろう? カラマツだって動き出したくなる。「一ヶ所に根を生やして立ってると、胸が焦げてくるんだ。せつなくてな」
お世話になった「猿田の爺(じい)さん」が死んだと聞いて、太郎スギと、モチノキ科のタラヨウと、大王クスと、ヒノキ科のビャクシンが打ちそろって通夜にいく。葉っぱの裏に、「御霊前 多羅 葉助」なんてのも用意した。香典袋を差し出すと、森林組合の若い事務員がうやうやしく受け取った。太郎スギには人間という生物の死がピンとこない。太郎スギは今年七百歳。大寺の柱用に伐(き)られても、柱になってさらに七百年は生き続ける。人間の猿田の爺さんは、たった八十九歳で、まだ若いのに死んで、焼かれて、それっきり。「それで終わり。スッパリ、と断ち切られる」
なんと興味深い「植物の私生活」がつづられていることだろう。一点に根を下ろす。これが植物の宿命だ。きびしい条件が意味深く、むだのない生活様式をもたらした。不自由な中で果敢に闘っている。その私生活を通して、タイトルの意味がわかってくる。生命の底の底にふれる思いがする。
「動物とはよく言ったものだ。人間はじつに動きまくり、じっとしているときがない。手も足も、眼(め)や口も、頭の中も、コマネズミのようだ」
その人間が気づこうとはしないことだが、植物は見ることができるし、数を数えることもできる。仲間どうしで意思を伝え合うこともできる。時間を正確にはかることができるのは、春になると桜前線が整然と北上していくことからもあきらかだろう。お化粧上手はアンズの花をかぐとわかる。まったくシャネルの5番どころではないのである。
どうしてこのつつましやかな地球の住人と共存できないのだろう。自然界のバランスをぶっこわす凶徒は唯一人間なのだ。しめくくりの一篇「深い夜の木」の夫は、「前世は木だった」ことを妻に打ち明ける。とくに告白することでもないので言わなかっただけ。妻は思った。
「それにしては人間になった夫はどうということもない、普通の男である」
こんな物語を、こんなふうに書けるのは、ひとり村田喜代子だけである。
ALL REVIEWSをフォローする