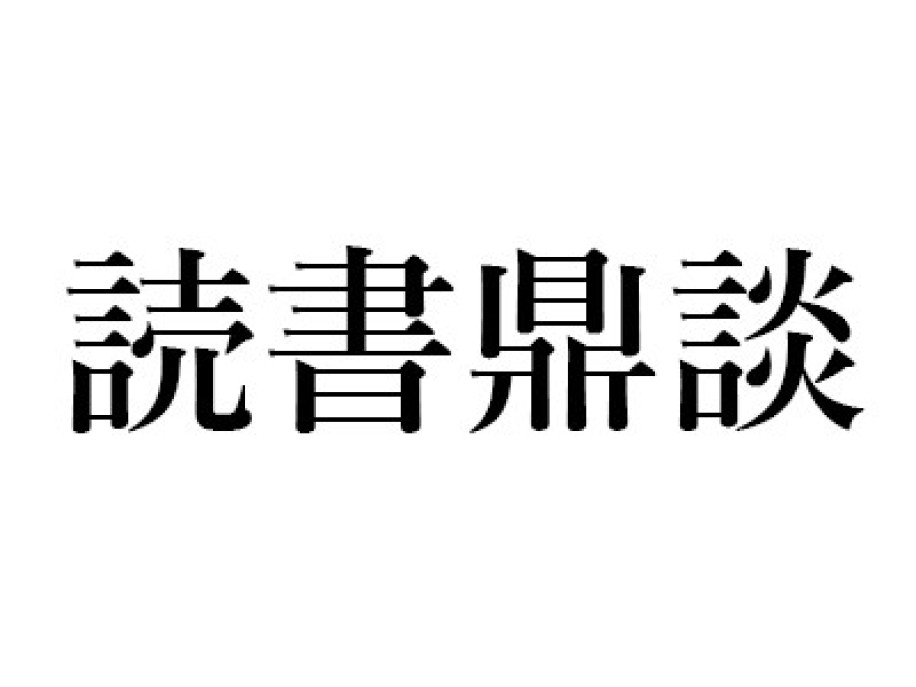書評
『山本容子のアーティスト図鑑 100と19のポートレイト』(文藝春秋)
小さな肖像画から立ち現れる物語
ちょうどいい具合に大きくて、草色の地に濃いピンクの背文字が美しい。ひらいて、と言っているかのようにやわらかな表紙。この鮮やかな朱色の本はとても愉しい。題名にある通り「図鑑」なので、どの頁から読み始めてもいい。そこにはマルグリット・デュラスがいて、円地文子がいて、グレアム・グリーンがいる。エディット・ピアフがいて、ピアソラがいて、モランディがいて、ロートレックがいる。河上徹太郎がいて、佐藤春夫がいて、志ん生がいる。私は強烈になつかしいと思った。誰にも会ったことがないのに、ああ、この気配、と思った。それは何の、誰の、いつの記憶なのだろう。
蔵書票を模したという一一九枚の肖像画は、一一九人のアーティストたちの姿かたちばかりじゃなく、作品や作風、趣味嗜好、さらにそれ以上の何かまで立ちのぼらせる。やや不気味だったりユーモラスだったり、シュールだったりシニカルだったり、一つずつの風味はちがうけれどどれも見事に美しく、洒脱で、慎み深い。これらの絵が映すのはその人の物語だ。だからパブロ・カザルスの絵からはチェロの音がきこえてくるし、エスコフィエの絵を見ると気に入りのレストランに外食しに行きたくなる。エミリ・ディキンスンの肖像からは詩が立ち現れる。なかでもとりわけ息をのんだのは、トーベ・ヤンソンのポーズおよび表情、澄んだつめたい空気と、コルトレーンの足元に咲いているすみれ。最高。
どの絵にも、短い文章が添えられている。「水彩紙の上の、水をたっぷりと含んだ筆致に感じる信頼」(ヴァレリィ)とか、「身体全体を使って、見えない世界をこちらに引っぱってきた人達」(アレン・ギンズバーグ)とか、「素朴さは、ひとつの力になりえても、持続するうちにこわれてしまう」(武者小路実篤)とか、「ふるえるような指が未来派の絵のように連続して何本もあらわれる」(ジョージ・ガーシュイン)とか。作者が当該アーティスト達との「架空対談の後日談のようなイメージ」で書いたというその文章は、遊び心に満ちている上に真摯だ。絵画や音楽や文学のつくり手たちへの、というより絵画や音楽や文学そのものへの、敬意と共感。それがとても率直に親密に書かれているために、一つ一つ読むうちに、そのアーティストについてよりむしろ山本容子という人について、感じとれてしまうしかけになっている。
この本にはさらに、知らない人たちと出会う愉しみもある。たとえば私は、「絵は色を塗っていなくても線を描かなくてもよい」と言った、シュヴィッターズというアーティストの存在を知らなかったし、「夢と妄想の違いを言葉にしてくれた」という詩人、ジュール・ラフォルグも知らなかった。巻末に、全部のアーティストの簡潔な紹介文がついているので便利だが、紹介文によってではなく肖像画によって、気配をたしかに垣間見ることができる。
どの絵もどこか、含羞(はにか)んでいるように見える。私的な何かを掬いとられて、ほんのすこし困っているように。色や匂いや手ざわりや音、言葉、そして時間。小さな絵のなかにいる、その多くがもうこの世にいない人たち。なんて贅沢な本なのだろうと思う。なにしろ、これらは肖像画だけれど、閉じ込められているのは人ではなく、音楽であり、絵画であり、文学なのだ。だから誰もがなつかしく思う。ひそやかであかるい、芸術家たちに励まされる気がする本だ。
ALL REVIEWSをフォローする