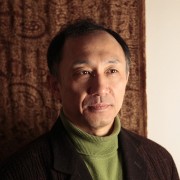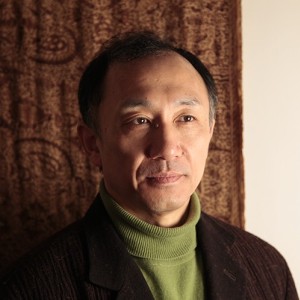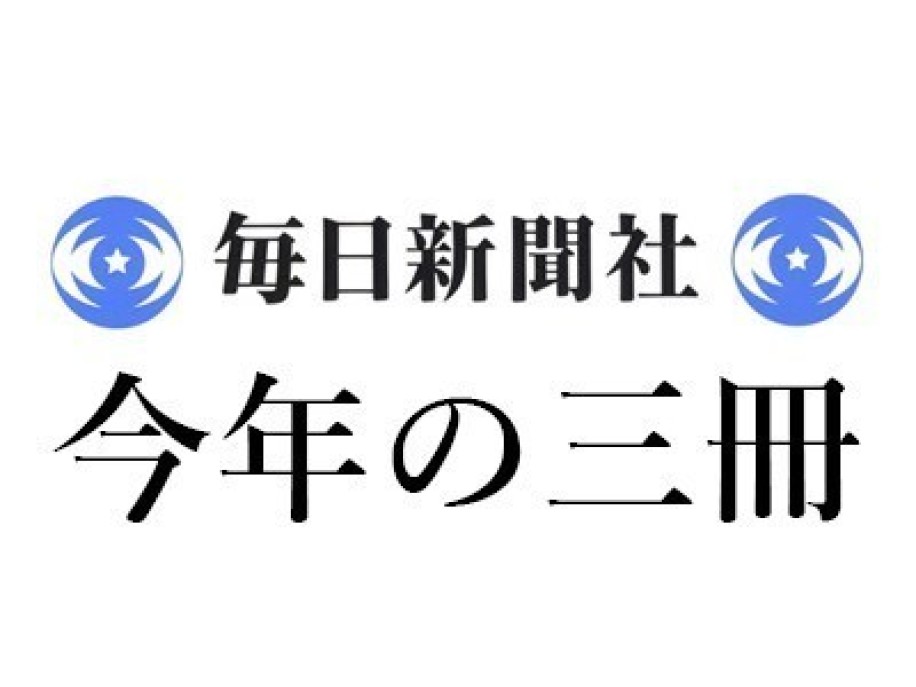書評
『教養の書』(筑摩書房)
愚行を繰り返さないために
大学新入生向けに「大学で学ぶ意味」を説く体裁ではあるものの、著者が語っていない位置づけをすると、文科省主導による大学改革の混乱とビジネス界における「教養本ブーム」の後を受け、大学側から投げ返された教養への誘いの書である(とはいえ文体は香具師(テキヤ)風)。「教養書ブーム」といえば大正時代から昭和初期にかけ旧制高校生がむさぼり読んだ阿部次郎『三太郎の日記』や西田幾多郎『善の研究』が思い浮かぶが、戦後の新制大学の教養学部では、丸山真男や大塚久雄、川島武宜ら「市民社会論」の旗手たちの著作が輪読された。
本書もまたその線上にあって、教養人の定義は「社会の担い手であることを自覚し、公共圈における議論を通じて、未来へ向けて社会を改善し存続させようとする存在」。教養を修得すれば、利害関係ある人々があくまで話し合いで問題を解決し意志決定する理想的な社会を担いうるというのだ。
では、新味は何か。教養学部は1991年以降、東大を除き大半の大学で廃止された。大学審議会が答申した「大学設置基準の大綱化」を受けてのことだ。折しも世間では、専門教育に3年間は短く一般教養は無駄、という大合唱が湧き起こっていた。教員にしてからが腹の底では「専門課程こそ大学」と考えた。
ところがここ10年で風向きが変わる。豹変したのが財界だ。日本がチマチマした新製品しか生み出せず「イノベーション」でGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)に大きく後れを取った理由として、専門教育の視野が狭いせいとみなしたのだ。昨年ベストセラーとなった山口周の『ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式』(ダイヤモンド社)は、サイエンスが「与えられた問題」を解くツールに過ぎず、社会がどうあるべきかを考えるのはリベラルアーツ(人文社会学)に根ざした構想力だと唱える。
タイトルからして教養に無縁なビジネス書までが後押しするのだから、世間の期待は膨らんでいる。一方著者は、映画にはやたらと強いがツイッターもフェイスブックにも手を染めず、教養への道として「ソサエティ5・0」といったビジネス界のバズワードを使うなと訴え、痛快だ。この間に生まれた学術の新潮流を渉猟し、教養論をリニューアルしたのが本書である。
むしろ本書が目標とするのは、科学の専門家が水俣病問題でチッソ側に有利な説を唱えて患者を苦しめたり、福島原発では津波は来ないとか全電源喪失は起きないとか、みずから疑いに目隠ししたような愚行の再発防止である。
以前の市民社会論では、市民は理性的かつ合理的と前提されていた。ところが急速に進展している認知心理学によれば、ヒトは認知のコストを節約するため、現実を代表例や思い浮かべやすい事例、ステレオタイプで理解しがちになる。だからこそ専門分野で愚行は繰り返された。「より普遍的な価値を希求し、それに照らして自己を相対化し反省」する能力としての教養こそが必要なのだ、と。
評者としては、市民個人のモラルよりも結果責任を取らせない法制度設計に病根ありと感じるが、語彙ノートを開陳し実用文章の書き方を指南するなど、著者のサービス精神には脱帽する。大学発教養本の現在形だ。
ALL REVIEWSをフォローする