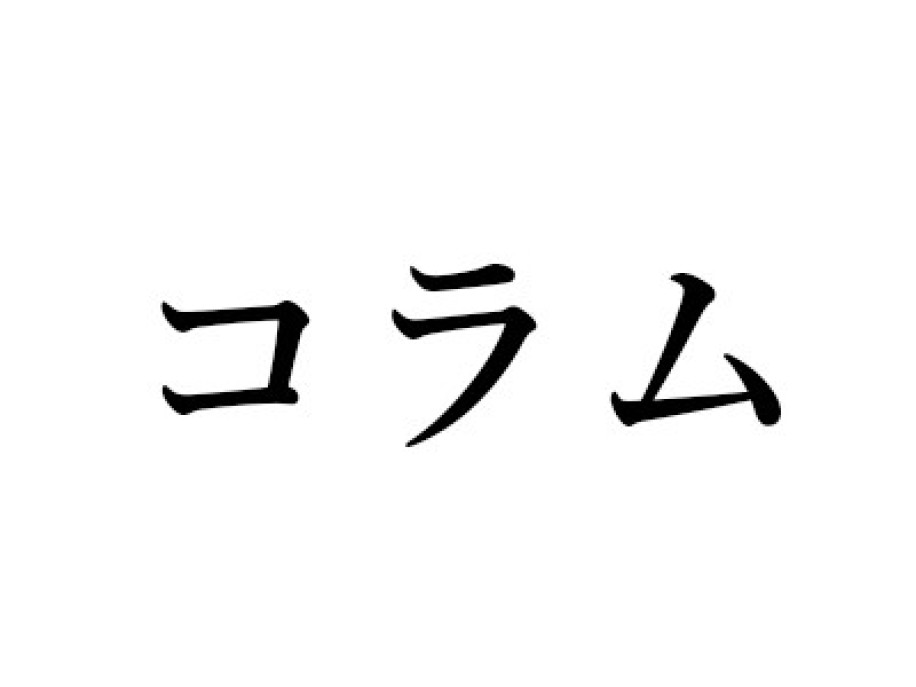書評
『幸田文全集〈第1巻〉父・こんなこと』(岩波書店)
邦さんと文さん
格子柄の全集で親しんだ幸田文の文業に、今度は紺の凛とした装幀で出会う。扉の枠の紫も素敵だし、口絵の写真にも見とれる。おおむね発表順というのが面白く、巻が出るたびの待ち遠しさ、ほかの仕事が手につかず読みふける。それだけでもう、何も書くことがないほど胸いっぱいなのだけれど、この岩波版の『幸田文全集』が出てみると、今まで見逃していたことはやはりある。
露伴が娘に家事全般を仕込む「あとみよそわか」に樋口一葉の妹、邦子が登場する。少女の文さんが向島蝸牛庵で畠をやらされているところに邦さんがやってきた。
「浮世の砥石にこすられて、才錐の如く鋭い」ところのある邦さんは一目で察した。
「よくまあなさいます。あゝいふおとうさまおかあさまです、あなたはお若い、御辛抱なさいませ。あなたのおかあさまはそれはそれはよくお働きになりました。あなたもどうか」
いきなり邦さんは白い両手に文さんの泥の手を包み、高い鼻のわきを玉がつらなり落ちた。
「お怪我などなさいませんやうに、御十分お大事に遊ばしませ。」さっとからだを折って、「も、そのまゝにいらして、どうぞおしごとを」……
邦さんの人となりが鮮やかに立ち上る名文だ。一葉以来のつきあいだから、生母幾美子も継母の八代(やよ)も知っている。この件で文さんは「いたはりのことばを聞いた潤ひ」と「まゝつ子だからの特別のお涙はいやなこつたといふ生意気」の背反する感情を味わった。しかし自分のために泣いてくれる人はそうはいない。「私は畠をやらされたおかげで一人の知己を得た」というのである。
幸田露伴は明治二十九年七月二十日、鷗外の弟で劇評家の三木竹二と一度だけ一葉をたずねている。
「色白く、胸のあたり赤く、丈はひくゝしてよくこえたり。物いふ声に重みあり」
一葉『みづの上日記』。眼力のある二十四歳の評である。露伴は三十歳。このときひょうきんな三木竹二は『たけくらべ』のキャスティングに興じ、信如を露伴、美登利は一葉、田中の正太は兄鷗外、横町の長吉には緑雨がぴったり、おどけの三五郎はかく申す拙者などと座は盛り上った。しかし節度のある露伴はそののちむやみと一葉を訪問しはしない。さすが、というより、一葉にはあと数ヵ月のいのちしか残されていなかった。
幸田文「一葉の季感」には「胸のあたり赤く」を「こんな若いときから酒やけの胸だつたのだから白い胸でゐたのは何歳までだつたか、などと思つてをかしい」とある。一流のユーモアである。一方、露伴の一葉の印象は「薄皮だちで顔に血のさしひきが早かつたといふことである。それがいかにもからだのか弱さと気の張りの強さを見せてゐるやうなものであつたらしい」
一葉の死後、邦さんは姉の仕事を守るための相談に、しばしば露伴を訪れた。
「色白にすらりとして、高い鼻と鮮やかに赤い口をもつた西洋人のやうな美しい人」である。本郷区に生れ育っただけに、「地味は粋のつきあたりといつたすつきりした様子」だった。こんな浮世の辛味をなめて意気張ずくの東京の女の流れるような応対術を、学問ばかりがプライドの信州人の継母八代は疎んじて、“外交官”と仇名した。
幸田文には「一葉きやうだい」の随筆がある。露伴も邦さんの姉思いの才女ぶりにときに閉口していたが、最後には、
「早く死なせた姉なのだ、故人を懐ふ情が厚いのもあたりまへだが、さすがだな。年を隔てるとだんだんに人情がすがすがしくなつてきたのは、いゝ妹ぶりだ」
と誉めたという。法事、遺作の出版、上映、碑の建立、資料の蒐集整理、展覧会、すべて邦は一葉のあとを処世実務の才をもって“目やすく”取り行なってきた。
さて文さんの生母、幾美子は「中背、やゝ肥り肉」、すました顔の写真を見てよく人は一葉女史に似ているといった。対するに露伴は一葉さんとは全然似ていなかったとも、また美人という類ではなかった、ともいっていたらしい。
文さんの一人娘青木玉さんにそのことをうかがったら、
「そうねえ。露伴先生は健康でよく働く女が好きだから、一葉さんよりどちらかというと邦子さんの方じゃない」
とイタズラっぽく笑われた。幸田一家が小石川表町、伝通院の隣に越したのも、すぐ近くに住んでいた邦さんの世話という。近所づきあいもあって、邦子さんの孫の陽ちゃんは、色白のきれいなひとで、すぐ赤くなるから“紅しょうが”って仇名だった、と玉さんは懐しそうだった。露伴が愛したお幾美さんはたしかにもたもたした気性ではなく、しごとがきびきびと手早かったという。
またあるとき、本の取次店、栗田書店の創業者栗田確也氏は出版関係の会で幸田文に会い、
「いやどうも、身のこなしといい、雰囲気といい、一葉の妹さんにそっくりだ」
と評したと聞いた。若いころ、よく邦さんの経営する書店小石川礫川堂(れきせんどう)に、本を運んだという。娘さんの話である。
私にはどうも、邦さんと文さんが多少似ていたように思う。文さんもまた、「才錐の如く鋭い」人である。あの露伴先生と丁丁発止塚原卜伝流の毎日だったのだから鈍いはずはない。「みそっかす」では早世した姉歌子を「聡明英敏、性質温雅」と称しているが、文さんは少くとも総領娘のおっとりぼんやりではない。なにおッと弟を追っかけ回すお転婆でもあり、気働き、行き届き、これはどうしても次女のものである。
邦さんは文さんの母の世代である。同じ年ごろの女の子がいた。「子をもつ女のやはらかさに感化された」と文さんはいう。邦さんにはやわらかなところもあったに違いない。
父は「利口な女さなあ」と云ひ「大した鼻だよ、立派だよ」と云つた。父の鼻は低いのである。(「あとみよそわか」)
ここでまた一本やられた。文さんの「清潔で端正な文体」や「すさまじい眼の力」は定評のあるところだけれど、それだけでは窮屈である。窮屈でないのは、文さんにはユーモアがあるからだ。余裕といってもいい。男社会の中で背のびして肩ひじ張ってふんばるだけではどうもだめだ、と思い知らされる。このユーモアは邦さんにはなかったかもしれない。
「一葉きやうだい」は昭和三十年十一月二十日の「毎日新聞」に載ったもの。二十三日が一葉忌、という時評である。「一葉さんの六十年忌だといふ。りつぱだなあとおもふ」。宿命はたしかに似ていた。文さんは文豪の父を見事に送らねばならなかった。そのあとも父の業績をしっかり守り、全集を二度、完成させている。「あとといふものはなかなか目やすくは行かないものだ」
「りつぱだなあとおもふ」には、嘆息があり、共感がある。「一ツの星のまはりにある六十年の年月は長くかなしい」
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする