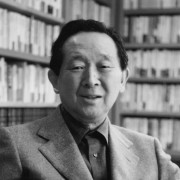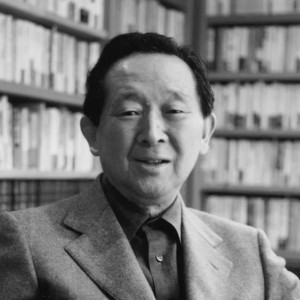書評
『行動する作曲家たち―岩城宏之対談集』(新潮社)
対談は登場した人物の性格と思想によって作られる演劇的空間である。岩城宏之氏と十二人の音楽家の対談集『行動する作曲家たち』(新潮社刊)を読んで感じたのは、この至極あたりまえの事柄が内包している面白さであった。
その理由のひとつは、彼が天衣無縫というか、何ものにも拘束されない自由な精神の持ち主だからであるだろう。黛敏郎氏からはじまって武満徹、湯浅譲二、石井眞木氏と続き芥川也寸志氏で終る作曲家は、周知のようにそれぞれ固有の感性に基いた音楽空間を創造している世界的な作曲家であり、彼等のいわゆる思想的立場、音楽と歴史社会とのかかわりあい方は、それこそ千差万別である。にもかかわらず、その誰とも全く屈託なく、お互に構えてしまうことなく会話が流れてゆく状況は、岩城氏の闊達な心の動き、通念を無視した旺盛な好奇心、総てのものの上に音楽への愛情を置く姿勢なしには実現不可能であったと思われる。
例えば、いわゆる前衛音楽、現代音楽という呼称について彼は石井眞木氏との会話のなかで卒直な疑問を投げかけている。確かに前衛があるからには別に本隊がある訳であり、その本隊とは何かが問題にされなければならないはずだと読者は気付かされる。
第二、この対談集が説得力を持っているのは、総ての登場者が常に現場からの声を発しているからであろう。現場離れをするほど議論が深くなるという、我国における思想への誤解はいつの頃から生れた歪みなのかと思わず考えさせられるのは、この対談集が意図せずに発揮している教育的効果のように思われる。
第三の魅力の根源として、彼が一人一人の個性について、切り込むという具合にではなく、ごく自然に話題に乗せ、不思議なことに、相手がまた素直に心を開いて答えている様子が読む者に一種の臨場感を持って伝わってくる点があげられる。
「一つ一つの音を大事にしたい、響きの流れよりも」という一柳発言、「君は厳然として作曲家であるが、いわゆる作曲家の概念外にいる」と言われて寛いでいる高橋悠治氏、音楽社会を超えて外へと説く林光氏、「日本は輸入ばかりして来た」と歎く日本音楽集団のリーダーであった三木稔氏、東西ではなく南北の軸で今日以後の音楽世界を透視し民族音楽を視野に収めている柴田南雄氏、文化の領域で仕事をする者として「何かを動かす生き方」を主張する芥川也寸志氏……と、発言はまさに万華鏡のような多彩な趣きを見せている。
こうした会話のなかから、アメリカやヨーロッパと日本の音楽の世界とは今や国境のない状態になっていること、音楽家と他のジャンルの芸術家との交流が拡がっている姿が現れてくる。もしかすると、日本の音楽は文学や演劇の世界よりも遥かに深く世界同時性のなかに生きているのかもしれないという印象が新鮮であった。
その理由のひとつは、彼が天衣無縫というか、何ものにも拘束されない自由な精神の持ち主だからであるだろう。黛敏郎氏からはじまって武満徹、湯浅譲二、石井眞木氏と続き芥川也寸志氏で終る作曲家は、周知のようにそれぞれ固有の感性に基いた音楽空間を創造している世界的な作曲家であり、彼等のいわゆる思想的立場、音楽と歴史社会とのかかわりあい方は、それこそ千差万別である。にもかかわらず、その誰とも全く屈託なく、お互に構えてしまうことなく会話が流れてゆく状況は、岩城氏の闊達な心の動き、通念を無視した旺盛な好奇心、総てのものの上に音楽への愛情を置く姿勢なしには実現不可能であったと思われる。
例えば、いわゆる前衛音楽、現代音楽という呼称について彼は石井眞木氏との会話のなかで卒直な疑問を投げかけている。確かに前衛があるからには別に本隊がある訳であり、その本隊とは何かが問題にされなければならないはずだと読者は気付かされる。
第二、この対談集が説得力を持っているのは、総ての登場者が常に現場からの声を発しているからであろう。現場離れをするほど議論が深くなるという、我国における思想への誤解はいつの頃から生れた歪みなのかと思わず考えさせられるのは、この対談集が意図せずに発揮している教育的効果のように思われる。
第三の魅力の根源として、彼が一人一人の個性について、切り込むという具合にではなく、ごく自然に話題に乗せ、不思議なことに、相手がまた素直に心を開いて答えている様子が読む者に一種の臨場感を持って伝わってくる点があげられる。
「一つ一つの音を大事にしたい、響きの流れよりも」という一柳発言、「君は厳然として作曲家であるが、いわゆる作曲家の概念外にいる」と言われて寛いでいる高橋悠治氏、音楽社会を超えて外へと説く林光氏、「日本は輸入ばかりして来た」と歎く日本音楽集団のリーダーであった三木稔氏、東西ではなく南北の軸で今日以後の音楽世界を透視し民族音楽を視野に収めている柴田南雄氏、文化の領域で仕事をする者として「何かを動かす生き方」を主張する芥川也寸志氏……と、発言はまさに万華鏡のような多彩な趣きを見せている。
こうした会話のなかから、アメリカやヨーロッパと日本の音楽の世界とは今や国境のない状態になっていること、音楽家と他のジャンルの芸術家との交流が拡がっている姿が現れてくる。もしかすると、日本の音楽は文学や演劇の世界よりも遥かに深く世界同時性のなかに生きているのかもしれないという印象が新鮮であった。
ALL REVIEWSをフォローする