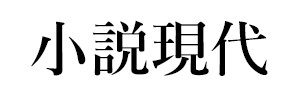書評
『指揮のおけいこ』(文藝春秋)
夢は音楽家
中学一年のとき、同級生に音楽好きの男子がいた。バッハに凝っているらしく、下敷きに、ふつうならアイドル歌手の写真でも差し挟むだろうところを、バッハの肖像画を入れていた。「BACH」と大きくプリントしてある。他の男子が「バッチ」「バッチ」とからかうと、
「バッハだよっ」
顔をまっ赤にして言い返すのだった。
休み時間は、メロディを口ずさんだり、譜面を眺めて過ごした。譜面が読めず、音楽の時間も、とにかく人の歌う後についてそのとおりを声に出すしかなかった私には、♯や♭のたくさんついた譜面にうっとりできるというそれだけで、「異人」なのだ。
極めつきは指揮棒だ。彼は廊下を教室移動するときも、常に指揮棒を持ち歩き、ぶつぶつとひとりごとを言いつつ振っていた。菜箸を小刀で削り、それらしい形にするらしい。一度など授業中、机の下で削っているのがばれて、大目玉をくらった。
(そんなに好きなら合唱部なり合奏部に入って思う存分振ればいいのに)と思われるだろう。が、悲しいかな、わが中学には運動部しかなかったのだ。
そんな彼に、晴れの指揮台に上るチャンスがやって来た。学校の行事で、クラス対抗合唱大会があるとわかったのだ。情熱的な練習がはじまった。が、彼の指揮は女子には不評だった。ノッてくるとリズムに合わせ唇まで「ンパーパ、ンパンパ」と閉じたり開いたりするので、唾が盛大に降りかかるのである。結果は覚えていないが、猛練習の割りには、たいしたことなかったようだ。
高校では当然合唱部に入るものと、同じ中学の誰もが思っていた。が、意外にも、中学のときのサッカーをそのまま続けた。大学も音楽とは関係ない医学部に進んだから、十代の日々の趣味というのは、わからない。
高校には彼とは別に、音楽で知られる人がいた。私が一年のとき、三年だった男子である。高校には合唱部と合奏部があり、文化祭ではそれぞれに出し物をするのが恒例となっている。が、その年は合同でオラトリオをするという。ショスタコーヴィチの「森の歌」。なんでも合唱部にすごい指揮者がいて、彼によって実現したらしい。
合唱部の友だちに「ぜひ聞きにきて」と請われ、当日、体育館に行ってみた。迫力だった。(おおーっ)と鳥肌が立ってしまった。
(高校生だと、ここまでできるのか)
中学の合唱大会とはまるで違う。
文化祭が過ぎても、合唱部の一、二年の女子は感激がさめやらぬようで、指揮者の先輩にメロメロだった。雨の日、彼が濡れながら歩いてでもいようものなら、駆け寄ってパッと傘を渡して、走り去る。相合い傘なんて、恐れ多くてとてもとても、なのである。
「先輩、芸大を受けるんだって」
友だちが噂を仕入れてきた。
「ゲー大?」
耳慣れぬ大学名に、聞き返した。音楽教育を施しているわけではない県立の普通校にとって、芸大なんて東大に入るよりはるかに難しく、非現実的でさえあったのだ。
にもかかわらず先輩は、芸大の指揮科にあっさり合格し、女の子たちに「はー」と溜め息をつかせた。今、世界で活躍している大野和士さんである。
岩城宏之著『指揮のおけいこ』(文藝春秋)によると、岩城さんは芸大ではタイコを叩いていて、指揮者になる「おけいこ」をしたわけではなかった。入学してみたら、まわりは専門の音楽教育を受けてきた人ばかり。コンプレックスに陥り、たまには少しはデカイ顔をしたいと、出身校のオーケストラに指揮をしにいき、先輩ヅラをかましていた。指揮棒は、菜箸を削ったものという。形状が似ているから、誰もが考えることなのか。
N響を振ることになったが、教えてくれる人なんていないから、夜、庭に面したガラス戸の前で、レコードに合わせ練習した。鏡だとはっきり映り過ぎ、正視に耐えないから。半年間それを続けた。
デビュー演奏の録音を聞いてわかったのは、半年間徹夜で踊りまくったことには意味がなかったということ。スコアを睨み、曲の分析を徹底的にする、その上で理想の演奏を、ひたすら「思う」。
指揮とは、この『思い』だけだと言っていいだろう。
音楽史上いかにたくさんの指揮者が指揮台から転落しているか、燕尾服はそれを着て汗みどろになって暴れるとどれくらいもつかなど、面白い話がいっぱいだ。一方で、指揮歴四十数年の間には、聴衆を前に間違えて演奏が止まってしまったり、病気のため指揮者生命が危ぶまれたりと、いろいろな危機があったことがわかる。それもこれもひっくるめ楽しく読ませてしまうのは、著者の人間的な大きさのためだろうか。
専門の音楽教育を受けなかった点は、朝比奈隆もそうである。京大法学部を出て阪急に入社、京大哲学科に入り直した。指揮者になったいきさつは、対談『朝比奈隆 わが回想』(中公新書)に詳らかだ。バイオリンを弾いていた彼は、大学オーケストラで指揮をしていたロシア人の先生から、「俺はもう日本を去る。お前、振れ」。どう振ればいいか、教えを乞いにいくと、「自分で考えろ」と門前払いされた。
「当時はそういう乱暴な時代なんですね。職業の転換とか自分の方向転換が急角度にいくわけですよ」と朝比奈さん。対談の聞き手をつとめた矢野暢さんもあとがきに記している。「昭和の時代は、このような巨大な人間を生み出し、自在に泳がせるだけの器量をもっていたのである」。
「急角度」と言えば、この人が四十七歳で音大に入学したときも、世間はアッと驚いた。「ベルばら」の作者、池田理代子さんだ。劇画家のキャリアを捨て、声楽家をめざし一から勉強し直した努力のほどは『ぶってよ、マゼット』(中央公論新社)に詳しい。
「音楽を学びたいという憧れはいよいよ諦め難く、まして、自分に残された人生の可能性のことを考え」、三十年ぶりに鍵盤に向かい、「これで試験に失敗したら、私って“ただのデブ”になるんだな」とおののきつつ、体重の増量につとめる日だった。
最終章に書かれた、ふたつのことが印象的だ。「多くの人生経験を経たのちの学生生活にもかかわらず、学ぶべきことはまだまだ人生に、これほどにも幾らでもある」そして「何かを選ぶということは何かを振り捨てるということでもある」という言葉に表される、人生への謙虚で厳しい立ち向かい方。
おそらく医者となっただろう、中学のときのバッハ少年も、いつの日かもう一度指揮棒を握ることがあるのだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする