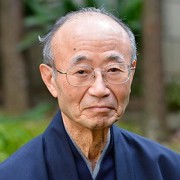書評
『日本は自らの来歴を語りうるか』(筑摩書房)
諭吉、蘇峰らに学ぶ外交術
日本は外国とどうつき合ってきたか。つき合おうとしたか。つき合うために、どのようなリクツをつけてきたのか。それを福沢諭吉や中江兆民、大杉栄や徳富蘇峰の言説を材料にし、手玉にとって縦横に論じている。それが本書のいわば基礎工事である。その上で著者が本当にいいたいのは、そうした過去の遺産を鏡にして、今後日本が外国とどうつき合っていったらいいのか、その方針や処方箋を描き出すところにある。本書の本建築の部分である。
だが私の見るところ、基礎工事の方は用意周到に出来上がっているのにたいして、本建築の方はかならずしも威風堂々の構成になっているわけではない。やはり反省は易しく、予見は難しいということなのだろう。もっともその予見のなかにも、ときにはっとするような創見がちりばめられてはいる。
事柄はあくまでも「外交」の問題である。それはしばしば個人と個人がつき合う枠組みを、国民とか文化とかいう名の二重扉の中に封じ込めてしまう。かつての日本ナショナリズム、今日の「日本異質論」が合わせ鏡のような恰好でいまなお議論されつづけている理由がそこにある。むろんそのような主題はすでに手垢によごれてしまった観があるのだが、しかし本書の随所にたんなる国際的な政治力学や外交交渉術などの水準をこえた、注目すべき観点が提出されている。たとえば兆民の対外政治論の中からあぶり出されている「自己犠牲」の論、諭吉の文明進化論の中に見出される「無常」の感覚、また大杉や蘇峰の政治論に沈澱している「気分」や「気の哲理」、といったようなテーマがそれだ。
これらの問題はひょっとすると、個のレベルにおける交際と国のレベルにおける外交のあいだのギャップをもみほぐし、日本人における対外観の特質を占う上で欠かすことのできない鍵概念となるものかもしれない。そこにこそ日本の来歴の影がさしているのである。
ALL REVIEWSをフォローする