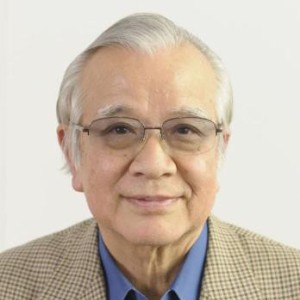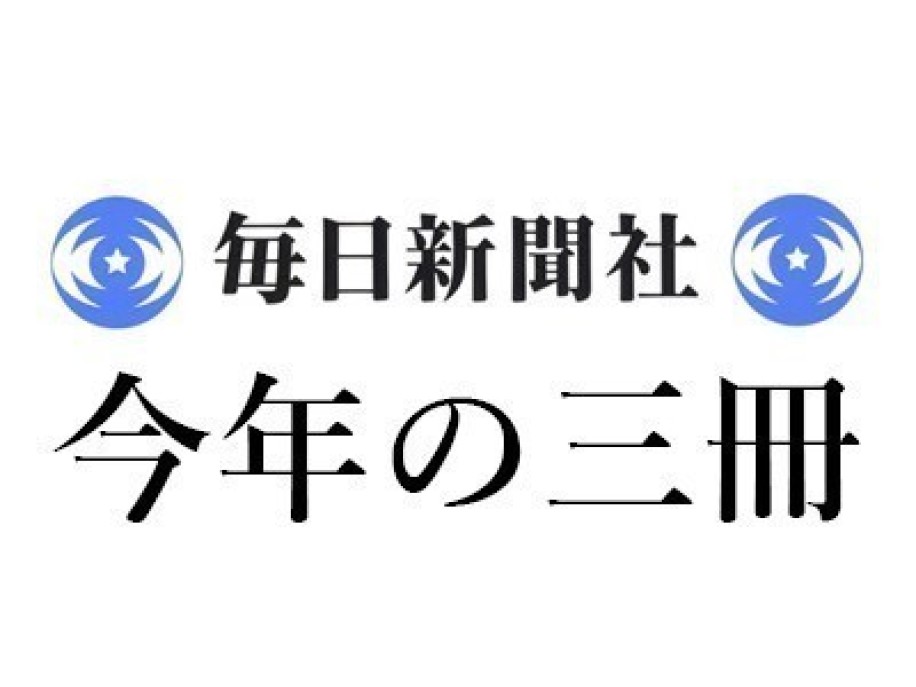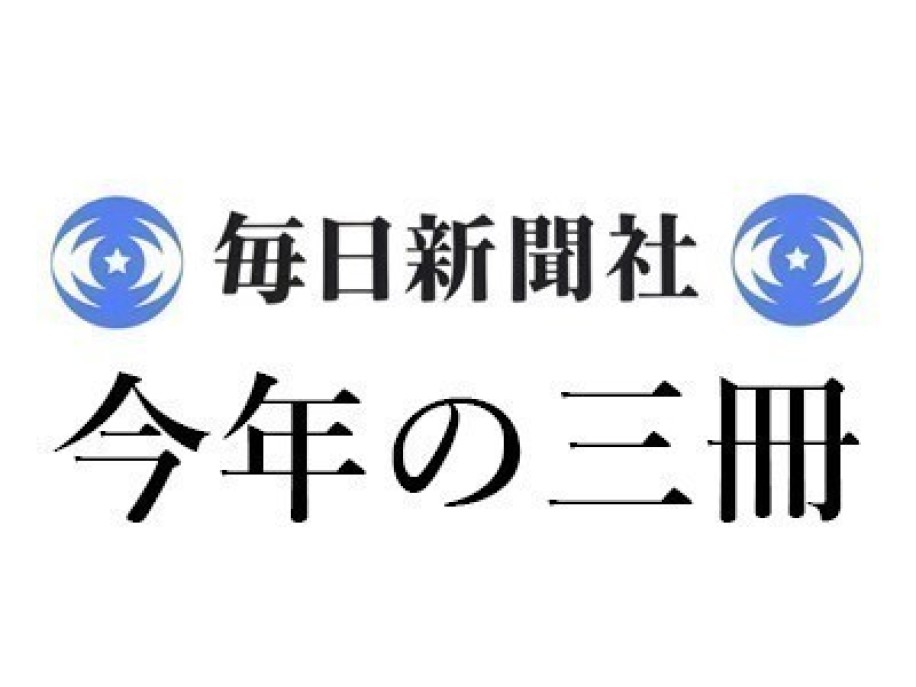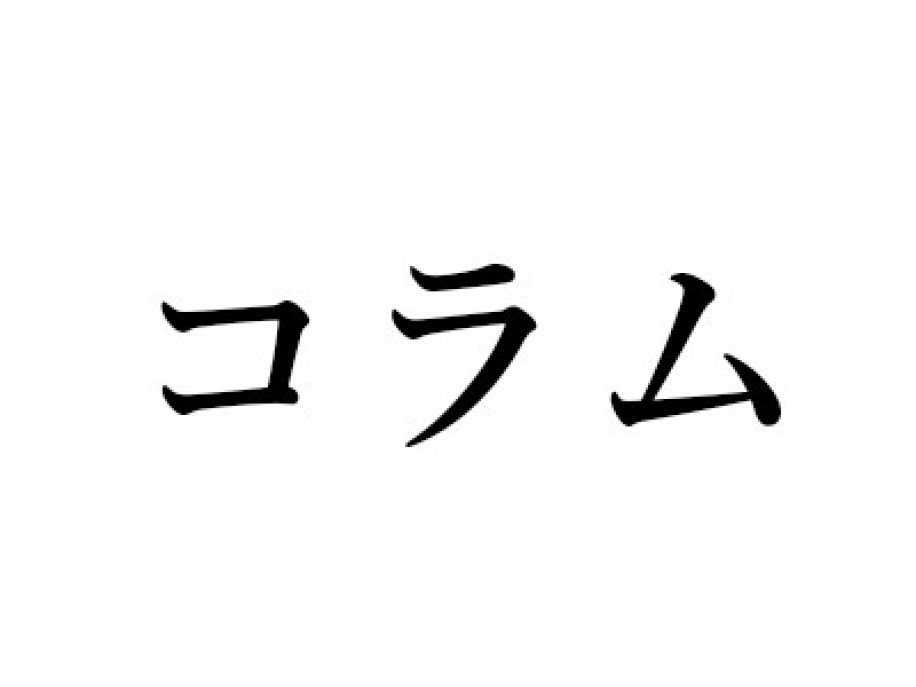書評
『錦』(中央公論新社)
人間像を生き生きと織りなして
小説の読み始めは舟に乗るときに似ている。大きな舟ではない。猪牙(ちょき)くらいの小舟。「船頭さん、頼むよ」
快く舟が滑り出すのを感じて、ひとときの悦楽に心身を委ねる。あいにく相性の悪い船頭だったりすると、のっけから不安が募り気分が苛立(いらだ)ち、いっこうに楽しみがやって来ない。けっしてレアケースではあるまい。
長年、佳編を書き続けた宮尾登美子は、さすがに手だれの船頭だ。とりわけこの『錦』は、読みだしたとたんに設定が頭に入り、興趣が増し、
――これは大丈夫――
確かな安心感の中で読み進むことができる。
内容は“龍村の帯”で知られる典雅な織物の、その創始者、龍村平蔵の生涯を綴(つづ)った伝記小説だ。作品の中では菱村吉蔵と名を変えて虚構化されているけれど、事跡については、また主人公の心の変転については、事実に近いものを追っている、と見てよいだろう。
大阪・船場で没落した商家の跡取りとして育ち、呉服の行商から京都・西陣で独創的な織物の開発に情熱を傾け、同業者の抵抗にあいながら艱難辛苦(かんなんしんく)のすえ、さまざまな錦を織りあげ、名物裂(ぎれ)を復元し、正倉院の名品から遠い時代の秘宝にまで迫っている。今はボロボロでも、かつては大変な貴品であったにちがいないミイラの顔布からペルシャの技を探るくだりではシルクロードへの夢が膨らむ。
大阪の職人社会と京都の職人社会、そして台頭する東京のビジネス界、日常の中に散っている人々の気配の差異も
――こんな感じだったろうなあ――
と、つきづきしい。
総じていきいきとした人間像が示され“たった一人の(もちろん協力者はあったが)みごとな美術工芸史”として読み取れるが、それにつきそうように、主人公を囲む3人の女たち、妻、愛人、弟子が登場して、そのありようもおもしろい。糸の織りあわせも厄介だが、
「こっちも難儀でしたなあ」
作者の筆はこの方面にも行き届き説得力がある。
朝日新聞 2008年8月24日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする