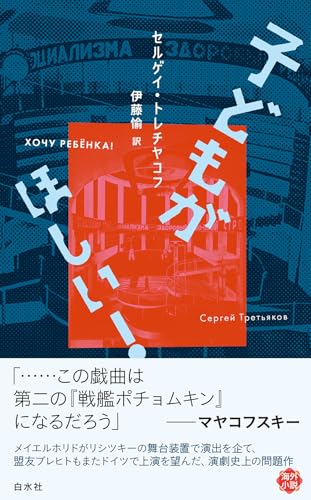書評
『日ソ戦争 1945年8月――棄てられた兵士と居留民』(みすず書房)
徹底解明 「終戦」ではなかった8・15
第二次世界大戦はどのように終結したのだろうか? 一九四五年五月、ドイツが無条件降伏し、七月末には連合国首脳がポツダム宣言を発表、なおも戦い続ける日本に対して降伏を迫った。ところが日本政府はこれをすぐには受け入れず、「黙殺」すると発表した。国際的にはそれが「無視」「拒否」と受け止められ、アメリカは八月六日と九日、広島と長崎に原爆を落とし、これが決定的な打撃となって、日本は八月一五日、天皇の玉音放送によって降伏の受諾を公表した。つまり、日本の戦争は八月一五日に終わったことになる。それでは本書が表題に掲げる「日ソ戦争」とは一体何なのか?この本の主題は、戦争の本当の終結のために、アメリカによる原爆投下と同様に決定的な役割を果たしたのが、ソ連による対日参戦だったという歴史的事実である。八月九日、ソ連は日本との中立条約を破って対日参戦を通告、満州への侵攻を開始して関東軍を圧倒したのだが、それでも関東軍が正式に降伏したのは八月一九日であり、さらにソ連軍による樺太・クリル(千島)の侵攻・占領作戦は九月初旬まで続いた。
日本の教科書などではソ連による「満州侵攻」「対日参戦」などと片づけられることが多いが、富田氏は、最近ロシアで機密解除された膨大な資料を調査し、露・日・英の文献に基づいて、満州の戦闘の実態を軍事的に解明していく。従来正統的な歴史研究者には敬遠されがちだった軍事史に大きく足を踏み入れる研究と言えるだろう。原爆とソ連参戦と日本降伏をめぐっては、国際的な広いキャンバスで米ソの息詰まる駆け引きを劇的に描き出した長谷川毅の『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏』という名著があるが、富田氏の本はこの時期の日ソ戦争という局所に虫メガネを当てて真実をより緻密に追求している。
本書はこの「戦争」の前史としてのヤルタ秘密協定(一九四五年二月、英米ソの間で、ソ連の対日参戦が秘密裡(り)に合意された)から、戦争後の日本軍捕虜の「シベリア抑留」や「戦犯」の裁判までの流れを視野に入れているが、最大の功績は、日ソ双方の記録・証言を突き合わせながら、場所別に日を追って戦闘の経過を克明に示していることだ。これは紛れもない「日ソ戦争」だったのである。
降伏を呼びかけるためにソ連軍から派遣された軍使(日本人捕虜)は日本軍将校に斬殺されたが、そのことは日本側の公式記録からは削除され、ソ連軍が居留民に対して行った略奪やレイプ、虐殺などはソ連側の文書では言及されない。読み進めるだけでもつらい、悲惨な出来事の全体を富田氏は歴史学者として客観的に見つめ、ソ連軍による蛮行を暴くと同時に、日本人居留民を置き去りにした関東軍の責任、そして集団自決を美徳とした軍国主義の問題からも目をそむけない。
いや、「客観的」とは言ったが、ここには著者の深い個人的思い入れも秘められている。著者の大伯父の一人はレイテ戦で自決、もう一人はシベリア出兵と抑留の両方を経験したという。本書のあとがきは、「兄二人レイテ自決とシベリア送り 祖母の語りも遠くなりぬ」という著者自作の短歌で――ご本人は「下手な」と謙遜しているが――結ばれているのだから。
ALL REVIEWSをフォローする